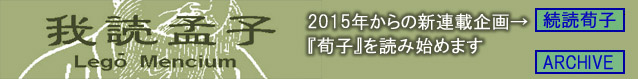これまでの各章で孟子が滕の文公に儒家の主張する政策を提言した直後に、この章から農家・墨家の論客が登場する。その意図は明らかである。これらの者たちの説を孟子が論破することによって、儒家の優位性を主張したいのだ。本章句のここから後は、完全に宣伝目的で書かれている。
孟子が文公を動かして、滕の葬制・土地制度を改めさせた。本章ではその仁政の噂を聞きつけて、許行という「神農の道」を奉ずる徒が滕にやってきたと書かれる。もうこの書き出しですでに儒家の悪意は露骨に表れている。孟子の説いた正道により滕国は仁政を行なうようになったのである。許行などは孟子の業績の上に乗っかってノコノコやって来たにすぎない。ましてや陳相のごときは元は儒家であったのに許行にだまされて宗旨替えし、孟子を批判しようとする。まるっきりの愚者である。彼らを嘲弄するのがこの章の目的なのだ。新約聖書の福音書もまた、パリサイ人を嘲弄することが主要なテーマとして流れている。宗教書とはこういうものだ。
この章で登場する許行、陳相の信奉する「神農の道」の内容については、この『孟子』の中の叙述が最もまとまっているようだ。諸子百家の中の「農家」として後世分類される。墨家が都市の商工業者のためのイデオロギーであったのに対して、農家は農民のためのイデオロギーだといえよう。神農とは『史記』三皇本紀(司馬遷の作ではなく、唐の司馬貞の補筆)によれば庖犠(ほうぎ)・女媧(じょか。カは「おんなへん+"堝"の右側)に続くはるかいにしえの三皇の一で、正式名は炎帝神農氏(えんていしんのうし)。ところがこの三皇はいずれも人外のバケモノであって、神農氏は人身牛首と書かれている。つまりギリシャ神話のミノタウロスと同じだ。祖先神が人外のバケモノであったという神話は世界中にあるので、三皇は中国の最も古い層の神話が反映されているに違いない。人間の王の歴史は神農からさらに下った時代の黄帝(こうてい)の即位から始まる(『史記』で司馬遷の筆に成るのは黄帝から始まる五帝本紀以降である)。
三皇本紀によれば、神農は木を切って鋤(すき)を作り、鋤・鍬(くわ)の使い方を万人に教えて農業を創始したという。また百草をなめて医薬を発見した。五弦の瑟(しつ。大ぶりの琴)も作った。易学においては八卦を重ねて現在の六十四卦を制定した。そして日中に市を開いて物を交易することを教えたという。人間に農業・医薬・音楽・占法・交易を教えた文化神である。ギリシャ神話やメキシコ神話などにも見られる文化神の一バリエーションで、別にユニークなところはない。許行らの農家は、この神農を主要神として奉る一派である。一方墨家は禹、道家は黄帝、儒家は尭・舜・周公・孔子を最も信奉した。これは思想の争いであったと同様に神々の争いでもあった。ギリシャでもそうであったように、古代の思想闘争は信奉する神の間の闘争となって現れる。
さて、許行らの農家の主張するところはこの『孟子』の章の叙述によれば国民皆耕の理想である。王公士大夫らの不生産階級の存在は否定される。商工業については否定はされないが、商人が暴利をむさぼることを封じるために自由な価格設定は規制される。これだけ読めば、最も素朴で粗雑な形のコミュニズムである。墨家思想もまた利他心を倫理の根幹に置いた点で近代のコミュニズムと通ずるが、墨家は都市商工業者がその担い手であるだけあって、各人のヴォランタリーな行動を強く求める。一方農家は素朴な農民のための思想であって、もっと上からの規制的側面が強い。
『孟子』の叙述は悪意でゆがめて書かれているに違いないから、許行の本当の説がここで陳相が語るような生半可なものであったのかどうかはわからない。だが近代になってもほとんど似たような説が繰り返し主張されたところを考えると、そのエッセンスはほぼ『孟子』の叙述と近いものであったのではないだろうか。当然、統治エリートの指導者階級としての価値を激しく擁護する孟子の儒教とは全く相容れない。この章の孟子の陳相への反論は、社会には分業が必要でしたがって肉体的労働と精神的労働との分業もまた必要だという分業論のような体裁を取っているが、真意はそんなところにはない。孟子には分業が生産力を発展させるというようなアダム・スミスの主張など無縁であり、肉体的精神的に関わらず全ての労働は等しく尊いという近代社会の職業観などはこれっぽっちも持っていなかったに違いない。全てはこれ王公士大夫の存在を擁護し、エリートの支配を正当化するための物言いである。分業と交易の利益など説いているが、儒教は本質的に商業資本の流通に果たす意義を認めない思想である(公孫丑章句下、十参照)。そしてエリートたる君子とただの人民とは平等でない(離婁章句下下、十九参照)。つまりガチガチの保守主義なのだ。孟子の思想は各人が心の「天爵」を十分に使い切るように生きろという個人の自由と努力を薦める教えであるが、その教えの信奉者たる士大夫階級の社会的ステータスを守るための制度を国が採用すべきことを同時に主張する。戦国時代の社会の実情を反映して、ごく限られた範囲の目覚めた人たちのための自由を擁護する主張なのだ。その時代的制約を考慮に入れなければならない。
保守主義はひとつの識見である。孟子は春秋時代の大政治家子産(しさん)のエピソードを批判して、「冷たい冬の川を困しんで渡っている人民を見かねて子産は自分の乗り物に載せてやったというが、そんな小さな徳よりも川に橋をかけるという大徳のほうが大事だ」と言う(離婁章句下、二)。政治家が細かい善事に捕われて大局を見誤ることへの戒めは、まさにエリートは「大きな仕事」に注意を集中せよという保守主義の倫理のよき点である。だが現代は戦国時代と違って、人民各個人の権利と自由が全ての政治の前提にあるという点を、決してないがしろにできない。
(2005.11.28)