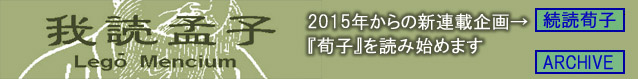春秋後期の名宰相晏嬰の説話を引いた章である(晏嬰の名を借りて作られた説話集『晏子春秋』に元ネタの話があるという)。晏嬰は少し後の世代の孔子も評価している政治家である。いわく、「晏嬰は人とよく交際し、その後に人から敬われる交際の達人だ。」(論語、公冶長篇「晏平仲善與人交、久而人敬之」)
だが孟子はここでは晏嬰を取り上げて手本にしているが、後の章では先の管仲と共にその功績を軽視している。管仲・晏嬰よりずっと下った時代に思想家として生きて、墨家や告子などとの論争の中でドグマ的な教説を固めていく孟子の傾向が見て取れる。「二人の生きた時代の後には、このようなますます激しい乱世が続いている。二人とも後のわれらの生きている時代を救えはしなかったではないか。救えるのはその時代に理解されなかった孔子の道、倫理的に唯一正しい儒教の道だけだ。この道はその場しのぎではなくて普遍的だ。だから一時的に政治で功績を成した管仲、晏嬰などは評価するに当たらない。」
この章も、梁恵王章句上、二や同章句下、一などと同様の主張である。晏嬰の意見は見も蓋もないことを言えば人民はサーヴィスの提供で釣れということだ。孟子は一般の人民にあまり高級な理性を期待していない(離婁章句下、十九)。身分による先天的な能力の差を認めはしないものの、実際はエリートに向けた教えである。儒教は個人の修養の大切さを説く点で個人道徳に焦点を合わせるが、その個人が人の上に立ってどのような政策を行うべきか、となると、老婆心の世話焼き主義になる。
民可使由之、不可使知之。(『論語』泰伯篇)
民はこれを由(よ)らしむべし。これを知らしむべからず。
というのが政治原則となる。儒教には「礼」による上下の社会関係が必須の倫理として入っているため、個人道徳の修養は社会秩序の道徳と不可分であって、したがって統治道徳を伴うからだ。結局儒教と自由主義が衝突するのは、この「礼」である。いずれもう少しこの辺について考えてみたい。
(2005.09.16)