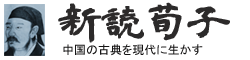|
王者を補佐する者(注1)について。動作を礼儀によって戒め、訴えを聞くときには法判断(注2)を用い、明察はわずかなことでも見分け、動作を臨機応変にして尽きることがない。これが、原理を持つ者というのである。これが王者を補佐する者のあり方である。 王者の制度。夏・殷・周の三代の正道の先は、考えない。現代の君主(注3)の法律から、外れることをしない。三代の正道の先を考えるのは、資料不備ではっきりしない。現代の君主の法律から外れることは、正しくない。衣服には規制があり、宮室には規定があり、役務の員数には定数がある。葬礼・祭祀の器具には、身分秩序に応じた格差がある。音楽は、雅正な音楽でないものは全て廃止する。宮廷の色は、古式どおりの色調でないものは全て撤廃する。器具は、すべて古式の器具でないものは全て廃棄する。これが復古であり、王者の制度である。 王者の等位について。徳ある者は必ず尊重し、能力ある者は必ず任官させ、功績ある者は必ず褒賞し、罪ある者は必ず罰する。こうして「朝廷には幸運で出世した者はおらず、民には幸運で豊かな者はいない」という古語を実現させるである。賢明な者を尊び能力ある者を使用して、これらを遺すことなく等位で区別して、誠実な者を選抜して凶悪な者を禁圧し、刑罰の命令には間違いなくする。こうすれば、人民は覚るのである、「家の中で善行を行っても、朝廷から褒賞される。こっそりと不善を行っても、公然と刑罰を受ける。」ということを。これが万古不変の等位であり、王者の等位である。 王者の法。地租に等級を付けて民事を正し、万物を差配するのは、万民を養うためである。田野の税は十分の一とし、関所と市場は検査は行うが課税はせず、山林での伐採および沢地での梁(やな)による魚採りについては、入山禁止・禁漁の時期を定めるにとどめて課税はせず、田地の検地を行って肥沃度に応じて地租に等級を定め、道の遠近を計算して貢納させ、財物と食料を流通させ、滞留させることなく、物資を必要な地域に運搬させるならば、四海のうちは一家のように治まるであろう。ゆえに、近い者は能力が隠れることはなく、遠い者は労役を忌避することもなく、遠方の僻地といえども王者のために奔走してこれに安らがない者はいない。これが人の師であり、王者の法である。 中華の向こうの北辺地方は、馬と犬を産する。中国は、これを入手して飼育する。南辺地方は、大鳥の羽、象牙に皮革類、上質の青銅、丹砂(たんしゃ。赤い顔料)に琅玕(ろうかん。宝石)を産する。中国は、これを入手して宝とする。東辺地方は、紫の衣に白絹、塩に魚を産する。中国は、これを入手して衣食する。西辺地方は、獣の皮革、旄牛(からうし)の尾を産する。中国は、これを入手して使用する。こうして漁師でも木を入手できて、山人でも魚を入手できて、農夫でも木を切らず器を作らずして道具を入手できて、職人と商人は田畑を耕すことなくして豆と穀物を入手できるのである。虎や豹は、猛獣である。しかし君子はこれらの皮を剥いで使用する。こうして天の覆うところ、地の載せるところ、すべてその美を尽くして人間の利用するところとならないものはない。これら世界中の物資を流通利用することによって、上は賢良の装備を装飾し、下は人民を養って安楽とするのである。これが、治世の極み(注4)である。『詩経』に、この言葉がある。:
この言葉は、今言った原理によって実現される。 (注1)原文「王者之人」。楊注は「王者の佐」、王者の補佐と言う。(注2)原文「類」。王制篇(1)と同じだが、より簡単に「法判断」としておく。(注3)原文「後王」。楊注「言うは、当世の王を以て法と爲す。離れて貮(たが)い、之を遠くに取らず。」下のコメント参照。(注4)原文「大神」。集解の郝懿行は「大神」を「大治」のことと言う。荀子は「神」の字に超越的な存在の意味を与えることはしないようである。勧学篇(1)のコメント参照。
|
|
《原文・読み下し》 王者の人。動を飾(いまし)むる(注5)に禮義を以てし、聽斷するに類を以てし、明は毫末(ごうまつ)を振い、舉措(きょそ)は應變(おうへん)して窮まらず。夫れ是を之れ原(もと)有りと謂う。是れ王者の人なり。 王者の制。道は三代に過ぎず、法は後王に貮(たが)わず。道三代に過ぐるは、之を蕩(とう)と謂い、法後王に貮うは、之を不雅と謂う。衣服制有り、宮室度有り、人徒數有り、喪祭・械用、皆等宜(とうぎ)有り。聲は則ち雅聲に非ざる者は舉(みな)廢し、色は則ち凡そ舊文に非ざる者は舉息め、械用は則ち凡そ舊器に非ざる者は舉毀(こぼ)つ。夫れ是を之れ復古と謂う。是れ王者の制なり。 王者の論(りん)(注6)。德として貴ばざること無く、能として官せざること無く、功として賞せざること無く、罪として罰せざること無く、朝に幸位無く、民に幸生無し。賢を尚(とうと)び能を使いて、等位遺さず、愿(げん)を析(わか)ち悍(かん)を禁じて、刑罰過(あやま)たず、百姓曉然(ぎょうぜん)として皆夫の善を家に爲して、賞を朝に取り、不善を幽に爲して、刑を顯(けん)に蒙(こうむ)るを知る。夫れ是を之れ定論と謂う。是れ王者の論(りん)なり。 王者の法。(注7)賦を等し、事を政(ただ)し(注8)、萬物を財(さい)する(注9)は、萬民を養う所以なり。田野は什(じゅう)が一、關市(かんし)は幾(き)して征せず、山林・澤梁(たくりょう)は、時を以て禁發して稅せず、地を相して政を衰(さ)し(注10)、道の遠近を理して貢(こう)を致さしめ、財物粟米(ぞくべい)を通流し、滯留有ること無く、相歸移(きい)せしめ、四海の內一家の若し。故に近き者は其の能を隱さず、遠き者は其の勞を疾(にく)まず、幽閒隱僻(ゆうかんいんぺき)の國と無(いえど)も(注11)、趨使(すうし)して之に安樂せざるは莫し。夫れ是を之れ人師と謂う。是れ王者の法なり。 北海は則ち走馬・吠犬(はいけん)有り、然り而(しこう)して中國得て之を畜使(ちくし)す。南海は則ち羽翮(うかく)・齒革(しかく)・曾青(そうせい)・丹干(たんかん)有り、然り而して中國得て之を財とす。東海は則ち紫紶(しかん)・魚鹽(ぎょえん)有り、然り而して中國得て之を衣食とす。西海は則ち皮革・文旄(ぶんぽう)有り、然り而して中國得て之を用う。故に澤人は木に足り、山人は魚に足り、農夫は斲削(たくさく)せず陶冶せずして械用(かいよう)に足り、工賈(こうこ)は耕田せずして菽粟(しゅくぞく)に足る。故に虎豹は猛爲るも、然も君子剝ぎて之を用う。故に天の覆う所、地の載(の)する所、其の美を盡(つ)くし、其の用を致さざること莫く、上は以て賢良を飾り、下は以て百姓を養いて、之を安樂す。夫れ是を之れ大神と謂う。詩に曰く、天高山を作り、大王之を荒(おお)いにす、彼作り、文王之を康(やす)んず、とは、此を之れ謂うなり。 (注5)楊注は「かざる」。集解の王念孫は「飭」字に通じると言う。「飭(いまし)める」。(注6)「論」を楊注は賞罰の論説と言い、集解の王先謙は「倫」と読み、等級の意味とする。王先謙に従う。(注7)原文には「法」の字はない。集解の王念孫は「法」字が入るべきと言う。(注8)「政」を集解の王念孫は「正」と読み、民事を正すことと言う。(注9)「財」は「裁」の意味。(注10)「衰」は「差」の意味。「政を衰す」とは「征(せい)を差す」の意味であり、土地ごとに地租の軽重の等級を付けること。(注11)猪飼補遺は「無」字を「雖」と読む。
|
王制篇のここから後はとみに興味が薄れるので、ほとんど訳を置くだけに留めたい。全中国での流通を活発化し、交通を促進させよ、という荀子の流通重視の主張は、孟子に欠けているところである。この辺は、さすがに荀子は視野が広くてかつ経済を理解している。だが自然を全く人間の奴隷とみなしていて、どうも自然への畏敬の心が見えないが、これは荀子に限ったことではなくて孟子もそうで、儒家思想は人間中心の思想であり、いきおい自然に対して人間を越えた力を持った存在としての畏敬心が少ない。これは、悪い面でもある(しかし孔子は、必ずしもそうではなかったと私は考える)。
交通網の発達は、僻地と大都市を連結して、人材を中央に吸い上げる効果がある。ゆえに中央集権国家は、交通網の整備に熱心である。このことは僻地の人心にも沿ったことであり、やむをえない面がある。だが私は、結果として各地の多様性が破壊されて均一な人間を作ってしまう、つまり熱力学第二法則に類比すれば社会のエントロピーを増加させて利用可能な社会のエネルギーを削いで行くという、負の面もまたあると思う。
ここで「後王」の用語が出てくる。訳では、「現代の君主」としておいた。なので、荀子固有の思想として言われる「後王思想」について、一応は述べたいと思う。
上のくだりの「道三代に過ぐるは、之を蕩(とう)と謂い、法後王に貮うは、之を不雅と謂う。」は、いま後回しにしている儒效篇にも出てくる。後王について集解の劉台拱は周の諸王のことを指していると考え、つまり先王に分類される開祖の文王・武王・周公の後を守った王たちの掟を指す、というわけである。いっぽう楊注は当世の王という。このように荀子の「後王」は、それが単に古い周代の制度を指しているにすぎないのか、それとも荀子に近い時代の諸王が立てた新しい制度のことを指しているのか、二説が対立しているのである。荀子は服装などの形式的な制度については古来の制を復古すべしという立場なので、集解の劉台拱の意見にも一理がある。しかし重澤俊郎氏など荀子思想の孟子思想に比べた開明性を強調する論者は、後王は当世の王を指すという説を取る。しかしながら荀子は「後王思想」を一篇を割いて体系的に説いたわけではなくて、非相篇、栄辱篇、儒效篇などに断片的に現れる叙述から論者たちが類推したものである。
私としては、二つの点からやはり楊注・増注あるいは重澤氏の視点を取りたい。
一つは、荀子は君子官僚が法の届かない分野において「類」すなわち類推適用あるいは類する判例を参照することを薦めているところにある。これは、法の運用者が理性を進めて法判断を行うことを認めるものである。この視点は、単に古くから伝わってきた掟をそのまま古い伝統だから無批判に尊重する、というM.ウェーバーの「伝統的支配」からは出てこない。むしろ荀子が君子官僚に期待することは、先王の掟ではなくてその中に貫かれている原理をよく理解して、それを理性に基づいて適用判断させよ、ということである。掟そのものではなくて、掟から抽象化された原理による理性判断を尊重する視点は、むしろウェーバーの言う「合理的支配」に近づいている。なので、荀子が現代の諸国が発布する法にも先王たちが依拠した合理的な原理が大なり小なり貫かれている、という認識を持っていたとしても、彼の思想から大きく外れることはないであろうと私は考える。荀子がそう考えていたのであろうと匂わせるくだりは、『荀子』の中に確かに散見される。しかし論証によって明言した、というところまで長大な証拠を残しているわけではない。
二つ目としては、荀子の同時代の諸国の法律は、すでに法治官僚国家の運営マニュアルとして高度な発達を遂げていたことが、近年の発掘文書から見て取れることができるからである。荀子が同時代の諸国の官僚制度をおおかた肯定し、この制度のままに統一帝国が成立すれば平和な中華世界が訪れる、と考えていたことは、私には十分想像できる。私としては、荀子は服装などの形式的な制度については儒家として古来の制が美しいと考えていたが、法律の内容についてはより新しい時代に発布されたものに優位性を認めていた、と考えておきたい。
1975年、中国の湖北省で秦国の官吏の記録が大量に出土した。出土地の名を付けて、雲夢秦簡(うんぼうしんかん)あるいは睡虎池秦簡(すいこちしんかん)と呼ばれている。その中には法律関係の文書が含まれていて、戦国末期の秦国の地方行政を担った官吏の実際の仕事内容が読み取れて興味深い。尾形勇氏の紹介するその文書の内容を見ると、法は詳細に住民の義務について規定し、官吏が法の判断に迷ったときの判例集もまた詳細に例示されていた(尾形勇・平セ隆郎『世界の歴史2 中華文明の誕生』第6章、中央公論社)。私は元地方公務員であったので、秦代官吏たちのそんなマニュアルを一覧したとき、市役所が守るべき法規則の体系、あるいはそれらについて中央の霞ヶ関から降りてくる法規判断集にそっくりだという印象を持った。
雲夢秦簡は戦国時代末期の文書であり、荀子の同時代である。その時代の官吏は、これほど詳細な法をもって住民を支配していた。古代人の水準が高かった、というよりも、法治官僚国家がいったん成立すると、時代に関わりなく法の運用技術は発達するものなのだ、と捉えたほうがよいと私は考える。
法治官僚国家を動かすテクノロジーである中国法は、このように古代の段階ですでに完成されていた。これを周辺国の日本や新羅もまた導入して、中国にならった専制王朝を運営するテクノロジーとしたのである。これが日本のいわゆる律令国家である。
しかしながら、日本ではその後、土着の法が中国法を駆逐する経過を辿った。つまり律令国家は、12世紀末に鎌倉幕府が成立したときに崩壊した。鎌倉幕府は、律令国家と別種の統治システムを採用し、承久の乱に勝利して以降はそれが全国で中国法のシステムを食い破ってしまうこととなったのである。
まず第一に、官位。中国法に従えば、官位任命権は最高権力者である天皇が持つ。しかし鎌倉幕府以降は、事実上それが武家のコントロール下に置かれるようになった。事実上の最高権力者は天皇ではなく、天皇が任命する形式で征夷大将軍が掌握することとなった。官位によらない権力が、日本では通用するようになったのである。第二に、中国法では地方の行政官を天皇が任命するシステムであった。しかし鎌倉幕府はこれを有名無実化し、地方の支配は幕府が任命する守護と、地方に土着して幕府に存在を認可された国人領主たちが担うようになった。○○守、○○介といった地方の行政官の官位は、武家政権においては名目上の栄誉しか意味をなさないことになった。第三に、中国法の法典に追加条項という形で御成敗式目(貞永式目)が制定された。武家政権においてはこちらが日本の法として実効力を持つようになり、裁判権は中央集権政府である朝廷から、地方領主の盟主である幕府に移ることとなった。
このように鎌倉幕府は、中国法を殺したのである。それは中央集権的な法治官僚国家のシステムを解体し、地方領主の自治権を優先する封建社会の成立に即した法体系の革命であった。鎌倉幕府が滅亡した後、後醍醐天皇が建武の新政で中国式の法治官僚国家の再導入を目指した。しかし、何ら実施されることなく終わった。それは、日本ではすでに土着の法が普及していたために、中国式の法治官僚国家を受け付けることができなかったからであった。
したがって荀子の「王者」の法は中国では通用したが、周辺諸国でも常に通用したわけではない。日本はしかし明治維新以降、法治官僚国家の法体系を再導入した。いわば再び荀子の「王者」の法に戻ったのであった。これは日本が列強と対抗するために、中央集権的な法治官僚国家を再導入することを余儀なくされたからであった。