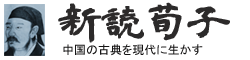|
世俗の説をなす者は、「堯と舜は教化する能がなかった」と言う。どういう意味かと言えば、「丹朱(たんしゅ)と象(しょう)(注1)を教化できなかったからだ」というのである。だがこれは、まちがっている。堯・舜は天下の者をよく教化する最上の人間であった。南面して天下の訴えを聞き、人民のたぐいは震え畏れて服従し、教化され従順とならない者とていなかった。それなのに、ただ丹朱と象だけが教化されなかった。これは堯・舜のあやまちではなく、丹朱・象の罪である。堯・舜は天下の英傑であった。丹朱・象は天下の狂人であり、天下の屑であった。いま、世俗の説をなす者は、丹朱・象を怪しまずに堯・舜を批判する。それは、なんというはなはだしい過ちであろうか。これこそが、妄説というものである。羿(げい)と蠭門(ほうもん)(注2)は、天下の弓手で最上の人間であった。しかしながら、彼らとて歪んだ弓と曲がった矢を与えられたならば、的に当てることはできないであろう。また王梁(おうりょう)・造父(ぞうほ)(注3)は、天下の御者で最上の人間であった。しかしながら、彼らとてもまともに走らない駄馬と壊れた車を与えられたならば、遠くに駆けさせることはできないであろう。堯・舜は、天下の者をよく教化する最上の人間であった。それでも、狂人や人間の屑を教化することはできはしない。いつの時代でも狂人はいるし、いつの時代でも人間の屑はいる。はるか原始の太皞(たいこう)・燧人(すいじん)(注4)の時代から、こういう輩は尽きなかったのである。(ここ以下のくだりは、正論篇末尾に移す。下の注8参照。)
世俗の説をなす者は、「太古の時代は薄葬であった。棺(ひつぎ)の板の厚さは三寸(6.75cm)しかなく、死者に着せる支装束は三揃いにとどめ、墳墓は農耕の妨げになる土地を避けた。今の乱世はそうでなく、厚葬して棺を副葬品で飾る。ゆえに盗掘が起こるのである」と言う。だがこれは、統治の正道を知るに及ばず、盗掘される理由を洞察できない者の言い分である。およそ人が盗むのは、必ず何らかの目的のために行うものである。欠乏のためやむなく掘り返すのでなければ、富を重ねることが目的であろう。だが聖王が人民を養う道は、すべての人が財貨は十分に豊かであり心は余裕に満ちていることを知らせ、かつ富の蓄積が節度を越えなくさせないところにある。ゆえに、盗賊ですら盗んだりはしなくなるのであり、犬や豚ですら餌に足りて豆や穀物を与えても取ろうとはしなくなるのであり、農民や商人ですら皆貨財を譲り合って利を求めなくなるのである。風俗の美は、男女は正式の婚姻を得ない淫乱を行うことはなく、人民は落し物を拾うことを恥じるのである。故に、孔子はこう言われた、「天下に道有れば、盗賊からまず変わるだろう」と。珠玉を遺体に満載させ、華麗な刺繍を付けた装束を棺の中にあふれさせ、黄金をもって椁(かく。棺を囲う外枠)を豪華に飾り、丹砂の朱色と青銅の青色をもって塗り立て、犀(さい)の角・象の牙で副葬品の宝樹をこしらえ、そこに琅玕(ろうかん)・龍茲(りょうじ)・華覲(かきん)(注5)の宝玉を埋め込む。ここまで豪華であっても、なおかつ人は盗掘したりはしない。その理由はといえば、聖代においては利を求める邪心が少なくなり、分際を犯す恥辱が大きくなるからである。そもそも乱れた今の時代になってから、このような美しい時代に反することが始った。すなわち上は無法をもって下を使い、下は下で無軌道をもって行動し、知者ですら国家に熟慮を行うことができず、能ある者ですら国家を統治ができなくなり、賢者ですら下の者を使うことができなくなったのである。このようになれば、上は天から与えられた自然の本性を利用する機会を逸することになり、下は土地の生ずる利便を利用する機会を逸することになり、その間の人間の世界においては調和が失われて人の力を活用する機会を逸することになる。ゆえに全ての事業は行われなくなり、財貨は尽きて、争乱が起こることになる。王公は国家の財貨が不足して苦しみ、庶民は己の体が凍えて飢えて疲れて痩せて、やはり苦しむことになる。この末世に至って桀(けつ)・紂(ちゅう)の眷属どもが群居して現れ、盗賊を行い、襲撃略奪をほしいままにして上を危機に陥れるのである。連中は禽獣(けだもの)の行いをなし、虎狼の貪りをなし、大人を干し肉にして食らい、子供を火あぶりにして食らうのである。こんな状況であれば、他人の墓を盗掘して、死者の口から含玉(がんぎょく)を抉り出して一儲けを企んだとしても(注6)、誰も咎める者とていなくなるのである。こうなれば、たとえ死者を丸裸にして埋葬したとしても、必ず掘り返すであろう。こんなことでは、埋葬などできない。盗掘人どもは、死体の肉を食らって骨までかじろうとするからである。かの「いにしえの時代は薄葬であったので、誰も盗掘しなかった。今の乱世は厚葬であるので、盗掘するのである」という説は、姦悪の者が乱説に惑わされて、これによって愚者を欺き、これを泥の中に叩き込んで、愚者から利を詐取しようとしているのである。こういう輩こそ、大姦というべきである。言い伝えに、「人を危うくして自らを安んじ、人を害して自らを利す」とあるが、このような説を立てる者こそがこれに当たる。 (注1)丹朱は堯の皇太子、象は舜の異母弟。下のコメント参照。
(注2)羿(げい)も蠭門(ほうもん)も、伝説の弓の名手。 (注3)王梁(おうりょう)も造父(ぞうほ)も、御者の名手。 (注4)太皞(たいこう)は伏羲(ふくぎ)のこと。三皇の最初の者で、八卦を作ったという。燧人(すいじん)は伏羲の前の君主で、人間に火を教えたという。いずれも、堯・舜ら五帝よりもさらに前の時代の伝説上の存在である。 (注5)いずれも宝玉の名。 (注6)原文読み下し「人の口を抉(えぐ)りて利を求むる」。古代の葬礼では、死者の口に玉(ぎょく)を含ませた。玉には霊力があって死体を腐らせないという信仰があったからである。殷周代の陵墓からは、よく玉で蝉の形をかたどった含蝉(がんせん)が出土する。古代では蝉もまた、不老不死の象徴であった。 |
|
《原文・読み下し》 世俗の說を爲す者曰く、堯・舜は敎化すること能わずと、是れ何ぞや。曰く、朱(しゅ)・象(しょう)化せず、と。是れ然らざるなり。堯・舜は、至って天下の善く敎化する者なり。南面して天下を聽き、生民の屬、振動・從服して、以て之に化順ざること莫し。然り而(しこう)して朱・象獨り化せず。是れ堯・舜の過に非ず、朱・象の罪なり。堯・舜なる者は天下の英なり、朱・象なる者は、天下の嵬(かい)、一時の瑣(さ)なり。今世俗の說を爲す者、朱・象を怪しまずして、堯・舜を非とするは、豈に過つこと甚しからずや。夫れ是を之れ嵬說(かいせつ)と謂う。羿(げい)・蠭門(ほうもん)なる者は、天下の善く射る者なるも、撥弓(はつきゅう)・曲矢(きょくし)を以て中(あ)つること能わず。王梁(おうりょう)・造父(ぞうほ)なる者は、天下の善く馭(ぎょ)する者なるも、辟馬(へきば)(注7)・毀輿(きよ)を以て遠きを致すこと能わず。堯・舜なる者は、天下の善く敎化する者なるも、嵬瑣(かいさ)をして化せしむること能わず。何(いず)れの時にして嵬無からん、何れの時にして瑣無からん。太皞(たいこう)・燧人(すいじん)より有らざること莫きなり。[(猪飼補注が錯簡とみなす箇所:)故に作(な)す者は不祥にして、學ぶ者は其の殃(おう)を受け、非とする者は慶有り。詩に曰く、下民の孽(げつ)は、天より降るに匪(あら)ず、噂沓(そんとう)して背けば憎む、職として競うは人に由る、とは、此を之れ謂うなり。](注8) 世俗の說を爲す者曰く、太古は薄葬す、棺の厚さ三寸、衣衾(いきん)三領(さんれい)、葬[田](注9)は田を妨げず、故に掘らざるなり。亂今は厚葬して棺を飾る、故に掘るなりと。是れ治道を知るに及ばずして、抇(こつ)・不抇(ふこつ)を察せざる者の言う所なり。凡そ人の盜むや、必ず以て爲(ため)にすること有り、以て不足に備うるならざれば、[足](注10)則ち以て有餘を重ねんとするなり。而(しか)るに聖王の民を生ずるや、皆當厚(ふこう)(注11)・優猶(ゆうゆう)(注12)にして足ることを知りて、有餘を以て度に過ぐること得ざらしむ。故に盜は竊(せつ)せず、賊は刺(し)せず(注13)、狗豕(こうし)は菽粟(しゅくぞく)を吐きて、農賈(のうこ)は皆能く貨財を以て讓り、風俗の美、男女自から涂(みち)に取(めと)らず(注14)、百姓遺(お)ちたるを拾うを羞ず。故に孔子の曰わく、天下道有れば、盜其れ先ず變ぜんか、と。珠玉體に滿ち、文繡棺に充ち、黃金椁(かく)に充ち、之に加うるに丹矸(たんかん)を以てし、之に重ぬるに曾靑(そうせい)を以てし、犀象(さいぞう)以て樹(じゅ)と爲し、琅玕(ろうかん)・龍茲(りょうじ)・華覲(かきん)以て實(じつ)と爲すと雖も、人猶お且つ之を抇(ほ)ること莫きなり。是れ何ぞや。則ち利を求むるの詭(き)(注15)緩にして、分を犯すの羞(しゅう)大なればなり。夫れ亂今にして而(しか)る後是に反す。上は無法を以て使い、下は無度を以て行い、知者も慮(おもんぱか)ることを得ず、能者も治むることを得ず、賢者も使うことを得ず。是(かく)の若くなれば、則ち上は天性を失し、下は地利を失し、中は人和を失す。故に百事廢し、財物屈して、禍亂起る。王公は則ち不足を上に病(うれ)い、庶人は則ち下に凍餧(とうだい)・羸瘠(るいせき)す。是に於て桀・紂羣居(ぐんきょ)して、盜賊擊奪(げきだつ)し、以て上を危うくす。安(すな)わち(注16)禽獸の行、虎狼の貪、故(ことさら)に(注16)巨人を脯(ほ)して嬰兒を炙(しゃ)にす。是の若くなれば則ち有(また)何ぞ人の墓を抇(ほ)り、人の口を抉(えぐ)りて利を求むることを尤(とが)めんや。此れ倮(ら)にして之を薶(うず)むと雖も、猶お且つ必ず抇(こつ)せん、安(いずく)んぞ葬薶(そうばい)するを得んや。彼れ乃ち將に其の肉を食(くら)いて其の骨を齕(か)まんとするなり。夫(か)の太古は薄葬す、故に抇せざるなり、亂今は厚葬す、故に抇するなりと曰うは、是れ特(ただ)に姦人の亂說に誤られて、以て愚者を欺き之を潮陷(どうかん)(注17)して、以て利を偷取(とうしゅ)するなり。夫れ是を之れ大姦と謂う。傳に曰く、人を危くして自ら安んじ、人を害して自ら利す、とは、此を之れ謂うなり。 (注7)楊注は、「辟」は「躄」と同じという。「躄馬」で、いざり馬、まともに走らない駄馬。
(注8)猪飼補注は、「此れ邪説の害を言う。上文と相接せず。蓋(けだ)し錯簡なり。故に『作者』以下『此之謂也』に至る三十六字は、当(まさ)に篇末『見侮不辱』に応ずる章の下に移すべし」と言う。確かにこの文は、上の文と文意がつながらない。正論篇ではこの後に下で訳した墨家への批判、それから子宋子への批判が続く。たとえば富国篇(3)での墨家批判のように、最後に邪説の害を述べて『詩経』などの他書からの引用で締める、という書き方は、荀子の通常のスタイルである。子宋子への批判の末尾には他書からの引用がないので、猪飼補注の主張には説得力があると私は考える。よって、これを錯簡とみなして正論篇末尾に移したい。 (注9)増注は、「田」字は衍字と言う。 (注10)増注・集解の盧文弨は、「足」字は衍字と言う。 (注11)増注・集解の王念孫は、「當」字は「富」字となすべし、と言う。 (注12)増注は、疑うは「猶」字は「裕」の誤りであるかと言う。 (注13)「刺」を楊注は殺すことと取るが、集解の兪樾は采取の意と取る。「さがしとる。」兪樾の説を取る。 (注14)新釈の藤井専英氏は、「取」は「娶」であり、「涂に娶らず」とは正式の婚姻でないことはしない、と言う。これに従う。 (注15)「詭」を楊注は詭詐と言い、集解の郝懿行・王先謙は「責」となす、と言う。金谷治氏および新釈の藤井専英氏は楊注を取り、漢文大系は郝・王の説を取る。郝・王の説を取れば「盗掘の利に伴う刑罰を恐れる心が少なくなり、分際を犯す恥の心が大きくなる」となるだろう。しかしこれでは聖王の下では刑罰は厳格である、という正論篇(3)あたりの叙述と矛盾することになる。やはり楊注説を取ったほうがよいと考える。 (注16)集解本・増注本に拠る漢文大系の原文は「安禽獸行、虎狼貪、故脯巨人、、」であり、増注は「安」は語助、と言う。影宋台州本に拠る新釈は「安」字を「必」字に作る。すなわち読み下しは「禽獸の行、虎狼の貪を必(ひつ)するなり、故に巨人を脯して、、」となる。とりあえず漢文大系に従っておく。 (注17)増注および集解の盧文弨は、「潮」は「淖」たるべしと言う。 |
これまで「世俗の説」を一つづつ読んできたが、今回は二つまとめて読むことにしたい。
一つ目の「世俗の説」は、堯帝・舜帝の一族である丹朱と象が愚者であったという言い伝えを挙げて、堯・舜の教化能力は大したことはない、という主張である。これを誰が言ったのか、は明言されていない。おそらく道家、とりわけ慎到(しんとう)あたりの「勢」を重んじる論者であろうか。慎到は「堯も匹夫となれば三人を治むること能わず」(『韓非子』難勢篇)と言って、君主の教化力などは国家にとって何ほどの意味もなさない、国家を統合する力は君主の地位そのものがもっている「勢」すなわち家臣への強制力である、と言った。「勢」は君主の能力とはいささかの関係もなく、国家というシステムそのものが持っている。そんな論者にとって、堯が皇太子の丹朱すら教化できず、舜が弟の象ですら教化できなかった、というエピソードは、聖王の能力が身の回りにすら及ばなかった好例として儒家批判にとって格好の題材となったことであろう。
丹朱については、『書経』や『史記』において堯帝の後を継ぐにふさわしくない不肖者であった、ということが書かれている。よって堯帝の死後に人民は丹朱を慕わず、舜を次代の帝として推戴した。そのいきさつと儒家思想における意義は、さきの正論篇(5)で検討したところである。
象については、『孟子』萬章章句で詳しく検討されている。舜の父である瞽瞍(こそう)は、後妻との子であった象を愛して舜を憎み、父と弟といっしょになって舜を殺すことを望んだ。しかしながら舜は無体な父のことを怨むことはなかった(萬章章句上、一)。やがて舜は堯帝にその能力を見出されて、帝の娘を妻として与えられて将来の後継者として財産を与えられる幸福を得た。だがそれを見た瞽瞍と象は、舜を殺して財産を奪い取るあさはかな計画を立てた。瞽瞍は舜に屋根の修繕を命じて、下から火をつけた。舜はうまく飛び降りて、命を永らえた。父は殺すことに失敗したら今度は井戸の掃除を命じて、舜が中に入ったときに父と弟で上から土を投げ込んで生き埋めにした。しかし舜は井戸の横にあらかじめ穴を掘っておいて、逃げおおせた。弟の象が舜の妻を奪おうと小躍りして兄の宮殿に乗り込んだら、兄はなにごともなかったかのように宮殿に戻っていた。「あなたが生きていてよかった!」などと醜い言い訳をする弟に対して、舜はいつもと変わらず接したのであった(同、二)。舜は帝位につくと、父の瞽瞍を決して臣下にせず生涯これに仕え(同、四)、自分を殺そうとした象を処罰するどころか有庳(ゆうひ)の地に国を与えたのであった(同、三)。このように、舜は不肖者の家族に囲まれながらこれを怨まず、むしろ愛して優遇したという。
このように、孟子は舜が瞽瞍や象を教化したかどうか、はあまり問題とせず、むしろ不肖の家族でも怨まず愛し続けたことに評価の重点を置いた。それは、孟子の統治原理の根幹が舜の伝説を評価することに現れているからであった。孟子は、君主の最大の事業は仁義の徳を養い、それを周囲に及ぼすことであると考えた。その仁義の徳は、まず最初に親に仕えて家族を愛するところからはじまり、その愛を一般人民に広く及ぼしていく(たとえば離婁章句上、十一)。いわゆる「差別愛」の原理である。舜は、不肖の家族に囲まれながらも親によく仕えて、家族を愛する義務を最もよく果たした。よって、孟子はこれを自らの統治原理のモデルケースとして詳しく検討し、これに最大の評価を与えたのであった。孟子にとって、舜は親と家族を最も愛する者であったゆえに、仁義の君主となることができた聖王であった。
いっぽう荀子は、孟子のような家族への愛の延長線上に国家の統治がある、といった主張を取ることがない。荀子にとって堯・舜が聖王であったのは、ただ人に優れた知力と仁義があり、国家の礼法をよく制定してこれに従う統治能力があったからであった。荀子にとっては、家族だからといって優先的に教化しなければならない、という考えはない。単に丹朱や象は人間の屑の範疇に入る者であるから、これらまでを教化することは不可能であり、なおかつ教化せずとも国家の運営に支障はない、とさらりと言うだけである。孟子が君主の仁義の徳を重視する統治思想を展開するのに対して、荀子は君主の統治能力を重視する統治思想を展開する。その違いが、ここでの両者の議論の違いに現れている。もし孟子であれば、ここでの「世俗の説」の批判は孟子の主張にとって痛烈な打撃となりえるものであり、孟子はこれを無視するかあるいは何らかのエクスキューズを立てるか選択しなければならなかったであろう。しかし荀子にとっては、「世俗の説」の批判は反論可能なものであった。
二つ目の「世俗の説」は、明らかに墨家の節葬主義への批判である。富国篇(3)でもあったように、荀子は墨家の非楽・節葬・節用を批判し、身分高い者の豪奢は礼の制度として必要不可欠なのである、と主張した。ここでの荀子の墨家への批判は、葬礼が豪華であっても統治がよく行われている社会であれば盗掘などは滅多に起こらなくなるのだ、今の時代に盗掘が頻発しているのは礼法が社会を統制することなく、法の抑止力が働かず、社会に十分な財貨が行き渡らないからである、というものである。荀子は儒家として手厚い葬儀に文化的価値を見出しているから、これを擁護しなければいけなかったのである。