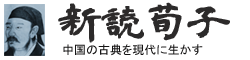かつて、人君において心が蔽われた者といえば、夏の桀(けつ)と殷の紂(ちゅう)であった。桀は末喜(ばつき)と斯觀(しかん)(注1)に心を蔽われてしまい、忠臣の關龍逢(かんりゅうほう)(注1)の価値を知ることができなかった。自らの心を惑わして、行いは乱れることとなった。紂は妲己(だつき)(注2)と飛廉(ひれん)(注3)に心を蔽われてしまい、賢人の微子啓(びしけい)(注4)の価値を知ることができなかった。これも自らの心を惑わして、行いは乱れることとなった。それゆえに群臣は忠勤を棄てて私事に走り、人民はこれを怨んでそしり、上の徭役をなすことを怠り、賢良の者は朝廷を辞官して野に隠れてしまった。これが、桀・紂が中華の九州(注5)の支配を失って、己の宗廟の国を滅亡させてしまった原因であった。すなわち桀は亭山(ていざん)に追われてそこで死に、紂は周の武王軍の赤旗に首をさらされることとなった。だが桀・紂は、自分が心が覆われていることに、とうとう最後まで気づくことがなかった。周囲の人もまた、そのことを諌めることがなかった。これが、心が蔽われ塞がれることのわざわいである。いっぽう湯王は桀を反面教師として、己の心をしっかりと正しく守って、慎んで心を治めた。これによって伊尹(いいん)(注6)を長年よく用い、自らは統治の正道を失わなかった。これが、湯王が夏王朝に代わって中華の九州を受け継いだ理由であった。また文王は紂を反面教師として、己の心をしっかりと正しく守って、慎んで心を治めた。これによって呂望(ろぼう)(注7)を長年よく用い、自らは統治の正道を失わなかった。これが、文王が殷王朝に代わって中華の九州を受け継いだ理由であった(注8)。こうして天下を受け継いだ者には、遠方から珍奇な産物が貢物としてどんどん運ばれてくる。ゆえに目には美色の極みを楽しみ、耳には美声の極みを楽しみ、口には美味の極みを楽しみ、身体は快適の極みである宮殿を楽しみ、名声は美称の極みを受け取り、生きている間は天下がこれを称えて歌い、死去したならば四海は悲しんで哭(な)くのである。これが、至盛(しせい)すなわち隆盛の極みというものである。詩には、この言葉がある。:
これが、心蔽われない王者の楽しみである。 かつて、人臣において心が蔽われた者といえば、唐鞅(とうおう)(注9)と奚齊(けいせい)(注10)であった。唐鞅は権力を欲することに心を蔽われてしまい、賢宰相の載子(たいし)(注11)を放逐してしまった。奚齊は国主となる欲に蔽われて、賢太子の申生(しんせい)(注10)を罪に追いやってしまった。結局、唐鞅は宋国で死刑となり、奚齊は晋国で暗殺されてしまった。だが両者とも、自分が心が覆われていることに、とうとう最後まで気づくことがなかった。これが、心が蔽われ塞がれることのわざわいである。ゆえに、下劣な貪欲、主君への謀反、権力争い、こういったことを行う者が己を危険に陥れ、己に恥辱を受け、己を滅亡させる結末とならなかったことは、古今にいまだかって存在したことがない。いっぽう鮑叔(ほうしゅく)・甯戚(ねいせき)・隰朋(しつぽう)(注12)は、その仁知が蔽われることがなかった。ゆえによく管仲を支持して、名利と福禄を管仲と分かち合ったのであった。また召公(しょうこう)(注13)と呂望もまた、その仁知が蔽われることがなかった。ゆえによく周公を支持して、名利と福禄を周公と分かち合ったのであった。言い伝えにはこの言葉がある、「賢人を知ることを、明察と言う。賢人を輔佐することを。有能と言う。これにひたすらに勉めるならば、必ずや福に永らえるであろう」と。これが、心蔽われない福なのである。 かつて、諸国を遊説徒食する者で心が蔽われた者といえば、邪説を立てる諸子百家の輩であった。すなわち墨子は実用主義に心が蔽われて、礼義の文飾が国家にいかに必要であるかを知らない。宋子(注14)は寡欲主義に心が蔽われて、生産して財貨を増やせば諸問題は解決するということを知らない。慎子(注14)は法家思想に心が蔽われて、賢人が国家にいかに必要であるかを知らない。申子(注14)は権勢の術に心が蔽われて、知者が国家にいかに必要であるかを知らない。恵子(注14)は詭弁術に心が蔽われて、言葉の奥にある実体が不変であることを知らない。荘子は天の無為自然に心が蔽われて、人間の成し遂げる力がいかに素晴らしいかを知らない。よって、墨子のように実用主義だけの視点をもってこれが正道だ、と言うことは、目先の便利さを追っているだけなのだ。宋子のように寡欲主義だけの視点をもってこれが正道だ、と言うことは、己の寡欲に自己満足する道を追っているだけなのだ。慎子のように法だけの視点をもってこれが正道だ、と言うことは、システムの統御術を追っているだけなのだ。申子のように権勢の術だけの視点をもってこれが正道だ、と言うことは、国家の能率を追っているだけなのだ。恵子のように詭弁術だけの視点をもってこれが正道だ、と言うことは、ひたすら空論を追っているだけなのだ。荘子のように天の無為自然だけの視点をもってこれが正道だ、と言うことは、放任して傍観する道を追っているだけなのだ。これらの考えは、いずれも真の正道のごく一部を語っているにすぎない。しかし真の正道というものは、常に恒常不変の実体を持ちながら、しかも全ての変化を言い尽くすものでなければならない。上の諸子百家たちのように真の正道のごく一部を語っているにすぎないものでは、万物を言い尽くすにはぜんぜん足りない。だがこのような偏った知識しか持たない者は、真の正道の一部だけは確かに見ているのであるが、(真の正道の全体図を分かっていないから、)その一部ですら完全な理解に届いていない。それで、不十分な理解なのにこれで十分だと切り上げて、後は文辞で飾り立てるのである。心中は不完全な理解ゆえに混乱に陥っていて、外に対しては人を惑わす説を撒き散らすのである。このような知識を人の上に立つ者が持てば、下の者の心まで蔽ってしまうだろう。また下にある者がこのような知識にかぶれるならば、上に立つ者の心を蔽ってしまうだろう。ただ孔子だけが仁知であり、心が蔽われないのである。ゆえに雑多な学術(注15)を学びながらも、ついに上達してわが国の文明を建てたいにしえの先王たちの原理を習得するに到ったのである。孔子の後を慕う儒家だけが、普遍的な真の正道を理解できるのであり、儒家の道を徹底的に究めることによって、流布しているもろもろの諸説に惑わされずに済むのである。ゆえに孔子の徳は周公に等しく、孔子の名声は禹・湯・文・武の聖王たちに並ぶのである。これが、心が蔽われない福なのである。
(注1)末喜は桀の妃。桀はその美色を寵愛して、政治を怠るようになったという。斯觀を楊注は未詳であり、けだし桀の佞臣であろうと言う。關龍逢は、桀を諌めたが用いられず捕らえて殺されたという。
(注2)妲己は紂の妃。紂もまたその美色を寵愛して、政治を怠るようになったという。このように桀と紂はほとんど同型のエピソードによって悪評が作られており、そのどちらか、あるいは両方ともにフィクションが大きく入っていることを印象させる。 (注3)飛廉は息子の悪来(あくらい、おらい)と共に紂に仕え、飛廉は足の速さで、悪来は怪力で仕えたという。『史記』秦本紀によると、武王が紂を討ったとき、悪来も殺した。しかしそのとき飛廉(史記では蜚廉)は北方に使いに行っており、死を免れた。飛廉は西方の秦の地を領有しており、秦国の祖先である。 (注4)微子啓は紂の庶兄で、紂を諌めて聞かれず野に下った。武王が紂を討った後にこれに仕え、殷の祭祀を継いで宋国の創始者となった。 (注5)原文「九牧之地」。いにしえの聖王の禹は、中華を九州に分けたという。それぞれに「牧」すなわち知事を置いたので、九牧と言う。 (注6)伊尹は湯王に仕えた賢人。『孟子』萬章章句上、七参照。 (注7)呂望は太公望呂尚のこと。文王・武王の軍師であり、斉国の開祖。 (注8)正確には、殷を亡ぼして周王朝を建国したのは、文王の後を継いだ武王である。 (注9)楊注は、唐鞅は宋の康王の臣という。唐鞅の名は『呂氏春秋』『論衡』に宋王の臣としてあらわれる。ところが『史記』の系譜に康王の名はあらわれない。宋国で王を名乗ったのは滅亡時の君主であった宋王偃(えん)だけである。下の注11で記した載子の考証から見れば、唐鞅は宋王偃、あるいはその前の君主であった剔成(てきせい)の時代の悪臣だったのであろう。康王というおくり名は、宋王偃が剔成に遡って王号を贈ったか、あるいは宋王偃の死後に宋の遺臣がおくり名を付けたか、どちらかである可能性がある。 (注10)奚齊は、晋の献公とその寵妃である驪姫(りき)との間の公子。献公の太子は申生であったが、奚齊に後を継がせたい驪姫の讒言に会って自殺した。奚齊は父の献公が死去したとき、その喪中に家臣によって殺された。献公の後はその別の子の恵公が継ぎ、その死後は献公のまた別の子である文公が継いだ。文公は斉の桓公に次ぐ覇者となり、両者あわせて「斉桓・晋文」と呼ばれて覇者の代表格とされる。以上が『史記』晋世家に書かれた経緯であり、申生を死に追いやったのはまだ若年であった奚齊の罪というよりは、その母の驪姫の罪である。 (注11)載子について楊注は、『孟子』滕文公章句下、六に出てくる戴不勝(たいふしょう)、および『韓非子』内儲説上下篇にある戴驩(たいかん)の二候補を挙げ、その時代に拠ればまさに戴驩たるべし、と言う。 (注12)鮑叔は桓公の傳(ふ。教育係)。管仲の親友であり、鮑叔は桓公の家臣となり管仲は桓公と斉の候位を争った公子糾の家臣となった。両者の抗争は桓公の勝利となって、管仲は罪を受けて捕らえられた。桓公は鮑叔を自らの宰相に上げようとしたが、鮑叔は管仲こそ天下を取らせる人材である、とあえて桓公に勧めた。桓公はこれを容れて管仲は罪を許され、以降桓公の下で宰相に昇った。甯戚・隰朋は桓公の大夫。宰相となった管仲の下で、よく働いたという。 (注13)召公は周の同族で、燕国の開祖。武王の後を継いだ成王の時代、周公は国の東半分を、召公は国の西半分を統治した。 (注14)宋子は宋鈃(そうけい)。正論篇(7)以下を参照。慎子は慎到(しんとう)。申子は申不害。両者は王制篇(1)のコメントを参照。恵子は恵施(けいし)。荘子の友人で、詭弁家。『荘子』に何度か現れて荘子と論争する。 (注15)原文「亂術」。増注の久保愛は、「下学上達の意」と言う。「下学上達」は、『論語』憲問篇にある。雑多なことを学んで、しだいに高級な原理の理解に達すること。孔子が常の師を持たず多芸であったことは、『論語』子罕篇で達巷党の人が「大なるかな孔子、博く学びて、名を成す所なし」と評価したエピソードや、同じ子罕篇で呉の大宰が「夫子は聖者か、何ぞ其れ多能なる」と言ったエピソードにも表れている。 |
|
《原文・読み下し》 昔人君の蔽わるる者は、夏の桀・殷の紂是れなり。桀は末喜(ばつき)・斯觀(しかん)に蔽われて、關龍逢(かんりゅうほう)を知らず、以て其の心を惑わして、其の行を亂る。紂は妲己(だつき)・飛廉(ひれん)に蔽われて、微子啓(びしけい)を知らず、以て其の心を惑わして,其の行を亂る。故に羣臣は忠を去りて私を事とし、百姓は怨非(えんぴ)して用せず、賢良は退處(たいしょ)して隱逃(いんとう)す。此れ其の九牧(きゅうぼく)の地を喪いて、宗廟の國を虛しくする所以なり。桀は亭山(ていざん)(注16)に死し、紂は赤旆(せきはい)に縣る。身先ず知らず、人又之を諫むること莫し。此れ蔽塞の禍なり。成湯は夏桀に監(かんが)み、故に其の心に主として愼んで之を治(おさ)む。是を以て能く長く伊尹(いいん)を用いて、身は道を失わず。此れ其の夏王に代わりて九有を受くる所以なり。文王は殷紂に監み、故に其の心に主として愼んで之を治む。是を以て能く長く呂望を用いて、身は道を失わず。此れ其の殷王に代わりて九牧を受くる所以なり。遠方其の珍を致さざること莫し。故に目は備色を視、耳は備聲を聽き、口は備味を食い、形は備宮に居り、名は備號(びごう)を受け、生きては則ち天下歌い、死しては則ち四海哭(こく)す。夫れ是を之れ至盛と謂う。詩に曰く、鳳凰秋秋、其の翼干(う)(注17)の若く、其の聲簫(しょう)の若し、鳳有り凰有り、帝の心を樂ましむ、とは、此れ蔽われざるの福なり。 昔人臣の蔽わるる者は、唐鞅(とうおう)・奚齊(けいせい)是れなり。唐鞅は權を欲するに蔽われて載子(たいし)を逐い、奚齊は國を欲するに蔽われて申生(しんせい)を罪す。唐鞅は宋に戮(りく)せられ、奚齊は晉に戮せらる。賢相を逐いて孝兄を罪し、身刑戮(けいりく)と爲る。然り而(しこう)して知らず、此れ蔽塞の禍なり。故に貪鄙(たんぴ)・背叛・爭權を以て危辱・滅亡せざる者は、古(いにしえ)自(よ)り今に及ぶまで、未だ嘗て之有らざるなり。鮑叔(ほうしゅく)・甯戚(ねいせき)・隰朋(しつぽう)は仁知にして且つ蔽われず、故に能く管仲を持して、名利・福祿は管仲と齊(ひと)し。召公(しょうこう)・呂望(りょぼう)は仁知にして且つ蔽われず、故に能く周公を持して名利・福祿は周公と齊し。傳に曰く、賢を知るを之れ明と謂い、賢を輔(たす)くるを之れ能と謂う、之を勉め之を强(つと)むれば、其の福必ず長し、とは、此を之れ謂うなり。此れ蔽われざるの福なり。 昔賓孟(ひんもう)(注18)の蔽わるる者は、亂家是れなり。墨子は用に蔽われて、文を知らず。宋子は欲に蔽われて、得を知らず。愼子は法に蔽われて、賢を知らず。申子(しんし)は埶(せい)に蔽われて、知を知らず。惠子(けいし)は辭に蔽われて、實を知らず。莊子は天に蔽われて、人を知らず。故に用に由りて之を道と謂うは、利を盡(つく)すのみなり。俗(よく)(注19)に由りて之を道と謂うは、嗛(きょう)を盡すのみなり。法に由りて之を道と謂うは、數(すう)を盡すのみなり。埶に由りて之を道と謂うは、便を盡すのみなり。辭に由りて之を道と謂うは、論を盡すのみなり。天に由りて之を道と謂うは、因を盡すのみなり。此の數具の者は、皆道の一隅なり。夫(か)の道なる者は、常を體して而(しか)も變を盡す、一隅以て之を舉ぐるに足らず。曲知の人は、道の一隅を觀るも、猶お未だ之を能く識らざるがごときなり。故に以て足れりと為して之を飾り、內は以て自ら亂り、外は以て人を惑わす。上は以て下を蔽い、下は以て上を蔽う。此れ蔽塞の禍なり。孔子は仁知にして且つ蔽われず。故に亂術(らんじゅつ)を學んで以て先王を爲(おさ)むるに足る者なり。一家のみ周道を得、舉げて之を用う。成積に蔽われざればなり。故に德は周公と齊しく、名は三王と並ぶ。此れ蔽われざるの福なり。 (注16)集解の王念孫は楊注の或説を是として「亭山」は「鬲山」である、と言う。しかし増注の久保愛は『竹書紀年』に「殷湯二十年夏桀卒亭山」とあることを引いて、亭山は誤りでない、と言う。久保説を支持する。
(注17)この詩は逸詩であって、現行の『詩経』にない。「干」について楊注は「楯」なり、と言う。猪飼補注は、「干」は「竽」に作るべし、と言う。逸詩であり他に参照するべき注釈がないので、最も古い楊注は尊重されるべきである。しかしながら、「竽」すなわち笙(しょう)の一種で「鳥翼に象る」笛である、と解釈する猪飼説は非常に説得力がある。よって、あえて猪飼説を取る。 (注18)「賓孟」を楊注は周景王の佞臣と言うが、集解の兪樾は人名ではなく、「孟」は「萌」となすべしと言い、「賓萌」は戦国時に諸侯の国を往来する遊士のこと、と言う。これに従う。 (注19)「俗」は明らかに「欲」である。 |
蔽われた心を持った君主、家臣、思想家たちを挙げる。最後に諸子百家をすべて蔽われた心の持ち主として批判して、ただ一人孔子だけを蔽われなかった思想家として激賞する。荀子は儒家だからこのように言うのであるが、「孔子がどうして蔽われない思想家なのか?」と問えば、荀子は「孔子は、いにしえの先王の道を説いたからだ」と答えるであろう。では、「いにしえの先王の道は、どうして蔽われない思想家だけが見出すことができるのか?」と問えば、荀子は「それが中華世界を統治できる唯一の道であり、歴史上この道を理解した者だけが統治に成功したからだ」と答えるであろう。その道とは、これまでにも検討したように、礼法に基づく法治官僚国家である。だがそれは歴史的に言えばおそらく正しくなく、王を頂点とした官僚国家は、中国では荀子の時代の戦国時代になってはじめて現れたはずである。戦国時代に入る前の春秋時代より以前の中華世界は、むしろ部族国家の範疇に入っていたと思われる。部族国家とは、君主と家臣の貴族たちが対等の同族として仲間意識を持って運営される国家である。部族国家において君主は絶対的な権力者ではなく、潜在的には同族間の第一人者として祖先神の祭祀を行うにすぎない。そのために、君主の宗教的な権威が衰えた春秋時代は、下克上が頻発したのであった。その下克上が収束して専制君主と官僚との支配―被支配の絶対的上下関係が現れたのは、戦国時代のことであった。
荀子の主張が歴史的には正しくなかったとしても、荀子の時代に中華を統一する国家を構想する場合ならば、荀子の案がやはり妥当であった。それは、荀子の構想する中華帝国が彼の生きた時代の直後に始皇帝によって開始され、以降二千年間中華世界で維持され続けたことが例証する。法治官僚国家が現実として最も妥当な統治法であることは、認めてもよい。しかし、人間の社会はそれだけでよいのだろうか。さきの柄谷行人氏の用語を再度用いるならば、「略取―再分配」の垂直的な交換様式だけに、人間は依存してよいのだろうか?人間同士の水平的な「互酬」の交換様式について、荀子は重視するところが少ない。むしろ孟子のほうが、君子が個人として他人にどのような善をなすべきか、というテーマに正面から取り組んでいて、水平的な「互酬」の交換様式のあり方を示唆する面を多く持っている。