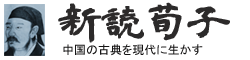|
大方は先王の正道に則ってはいるが、それを統一している原理を理解しておらず、見てくれはゆったりと構えながらその内心の性質は激烈で志は誇大であり、見聞はまことに雑にして広く、いにしえの歴史を考察して自説を打ち出し、「五行(ごこう)」(注1)と名付けている。だがその説はきわめて歪んで偏っていて、正しい名称の分類を行っておらず、深遠なことを言いながら明確な説明を欠き、難解なことを言って明解さがない。それゆえに自らの言辞を装飾してこれを恭しく担ぎ上げ、これこそ我らに先行する君子(注2)が言いたかったことである、などと吹聴する。子思(しし)(注3)がこれを提唱し、孟軻(もうか)(注4)がこれに唱和した。世俗の暗愚な儒者どもは大きな声で議論するが、どの説が過ちであるかを判断できない。よって連中は子思・孟軻の説を認めてこれを伝承し、仲尼(ちゅうじ)と子游(しゆう)(注5)は子思・孟軻のおかげで後世に重んじられることとなったのだ、と信じるのである。これが子思・孟軻の罪である。
いまもしここに人がいて、天下を治める方略を総合的に述べ、言葉と行動を一致させ、法の大綱と法判断(注6)を統一し、こうすることによって天下の英傑を集め、これらにいにしえの正道を語り、至順なることを教えたならば、部屋の中(注7)で敷物の上に座っていながらにして聖王の礼義法制が天下全てに普及して、天下泰平の風俗が勢いよく立ち起こることであろう。もはや六つの邪説などは入り込む余地すらなく、十二人の異端どもは近づくことすらできなくなるだろう。錐を立てる土地すら持っていないのに王公も名声を争うことができず、大夫程度の位階であっても一人の君主も手元に置き続けることができず、その名声は諸侯を凌駕して、諸侯は競ってこれを家臣とすることを願わずにはいられない。これが、仲尼・子弓(しきゅう)(注8)であり、彼らは権勢を得ることができなかった聖人なのである。天下を統一し、万物を差配し、人民を養い、天下の万民に利益をもたらし、天下を通行するもろもろの人民たちをすべて服従させ、六つの邪説はたちどころに消え去り、十二人の異端どもも教化されて正道に帰る。これが、舜・禹(注9)であり、彼らは権勢を得た聖人なのである。いまの時代、仁人は何を努めるべきであるか。上を仰ぐときには舜・禹の礼法の制度にならい、下を見れば仲尼・子弓の礼義の大義にならい、これを通じて十二人の異端どもの邪説を終わらせる努力をしなければならない。これを行うならば天下の害は除かれて、仁人の仕事はついに完成し、聖王の功績は天下にはっきりと記されることであろう。
(注1)荀子がここで「五行」として子思・孟子の何の説を指して言ったのかは、議論のあるところである。下のコメントおよび追記を参照。
(注2)原文「先君子」。つまり孔子のこと。
(注3)孔伋子思(こうきゅう・しし)。姓は孔、名は伋、字(あざな)は子思。孔子の孫で、孔子死後の儒家の中心人物の一人。孟子は子思の門人に学んだという。四書の一である『中庸』の作者と伝えられるが、異論もある。
(注4)孟子の姓は孟で、名は軻である。よって孟軻は孟子の本名。
(注5)仲尼は孔子の字(あざな)、子游は孔子の弟子である言偃(げんえん)の字である。だが荀子が孔子と並んで称える人物は、ここ以外の箇所ではすべて子弓である。なのになぜここだけ、子游を挙げているのか?子弓と子游との関係は?久保愛・郭嵩燾は、この子游は子弓の誤りと言う。あるいは別の説では、子游=子弓であると考える。私は、子游=子弓説は取り難いと考えるので、ここは子弓の誤りであるという久保愛・郭嵩燾の説に賛同したい。 非相篇(1)コメントの考証を参照。
(注6)原文「統類」。 解蔽篇(6)注3に合わせた訳とした。
(注7)原文「奧窔之閒」。「奥」の原義は室の西南隅、「窔」は室の東南隅。その間という意味なので、部屋の中のこと。
(注8)詳細不明。 非相篇(1)コメントの考証を参照。
(注9)このあたり、孟子ならば堯・舜と言うはずであるところを、荀子は舜・禹と言い換える。荀子は、性悪篇などにおいても禹を模範的聖人として称揚している。荀子は『書経』禹貢篇に見られる九州・服制を制定した禹の功績を、高く評価していると思われる。もとより『書経』における禹の行政制度は史実とは言えず、後世の伝説にすぎない。
|
《原文・読み下し》
略(ほぼ)先王に法(のっと)りて其の統を知らず、猶然(ゆうぜん)として(注10)材劇にして志は大、聞見雜博、往舊を案じて說を造(な)し、之を五行と謂い、甚だ僻違にして類無く、幽隱にして說無く、閉約にして解無し。案(すなわ)ち其の辭を飾りて、之を祇敬(しけい)して曰く、此れ眞(まさ)に先君子の言なり、と。子思之を唱え、孟軻之に和す。世俗の溝猶瞀儒(こうゆうぼうじゅ)(注11)、嚾嚾然(かんかんぜん)として其の非なる所を知らざるなり。遂に受けて之を傳え、以て仲尼(ちゅうじ)・子游(しゆう)茲(これ)が爲めに後世に厚(おも)んぜらると爲す、是れ則ち子思・孟軻の罪なり。
若し夫れ方略を總(す)べ、言行を齊(ひと)しくし、統類を壹(いつ)にし、天下の英傑を羣(ぐん)し、之に告ぐるに大古を以てし、之に敎うるに至順を以てせば、奧窔(おうよう)の閒(かん)、簟席(てんせき)の上、斂然(きゅうぜん)(注12)として聖王の文章具(そな)わり、佛然(ぼつぜん)として平世の俗起らん。六說なる者入ること能わず、十二子なる者親(ちか)づくこと能わざるなり。置錐(ちすい)の地無くして、而も王公も之と名を爭うこと能わず、一大夫の位に在るも、則ち一君も獨り畜(とど)むること能わず、一國も獨り容るること能わず。成名は諸侯より況(さかん)にして(注13)、以て臣と爲すことを願わざること莫し。是れ聖人の埶(せい)を得ざる者にして、仲尼・子弓(しきゅう)是なり。天下を一にし、萬物を財(さい)し(注14)、人民を長養し、天下を兼利し、通達の屬、從服せざること莫く、六說なる者立ちどころに息(や)み、十二子なる者遷化す。則ち聖人の埶を得る者にして、舜・禹是なり。今夫(か)の仁人や、將(まさ)に何を務めんとするか。上は則ち舜・禹の制に法り、下は則ち仲尼・子弓の義に法り、以て務めて十二子の說を息(や)めんとす。是(かく)の如くなれば則ち天下の害除かれ、仁人の事畢(おわ)り、聖王の跡著(あら)わる。
(注10)原文「猶然而」。楊注は「猶然」を舒遅の貌、と注する。ゆったりした様子を指す。ここが宋本では「然而猶」に作られている。集解の盧文弨は宋本に依るべし、と言う。宋本に依るならば、「然り而(しこう)して猶(なお)」と読むべきであろう。
(注11)集解の王先謙は、「溝猶瞀儒」は「溝瞀儒」のことであり、溝瞀は愚闇と訓じ、猶は語助なるのみ、と言う。これに従う。
(注12)集解の王引之は、「斂然」は古語になく、「斂」は「歙」となすべし、と言う。「歙然(きゅうぜん)」は、一致する様子。これに従う。
(注13)楊注或説は「況」はなお「益」のごとし、と言う。さかん。
(注14)「財」は「裁」の意味。
|
上に訳したくだりは、非十二子篇で最も謎の多いところである。
大きな二つの疑問がある。
- 荀子が批判した子思・孟子の「五行」とは、何の説を指しているのか?
- 荀子が孔子(仲尼)ともに並べて賞賛する「子弓」の正体は誰か?
以上のうち、子弓の正体については非相篇において重澤俊郎氏の整理を追ってレビューした。私の意見としては、子游説は受け入れることが難しく、かといって重澤氏が消極的な意味で比較的妥当性があると言う冉雍説もまた難しいと考える。『論語』に断片的に見える冉雍の思想と、荀子の思想の間に系譜関係を見出すことは難しい。それに冉雍=子弓であるならば、『荀子』書中に冉雍についてのエピソードがもっと多くてもよいのではなかろうか。孟子は、彼の学の系譜上の師に当たる曾参と子思について『孟子』書中で頻繁に言及しているのである。しかしながら、『荀子』書中において冉雍は他の孔子の弟子である曾参・子貢・子路・顔回・子夏に比べて、特別に取り上げられている形跡が見えない。私は、子弓はやはり詳細不明の思想家であると言うより他はない。
次に、子思・孟子への荀子の批判点である。
楊注は、「五行は五常、仁・義・礼・智・信」と言う。増注の久保愛は「豊島幹曰く、五行は中庸の天下達道五、及び孟子の親・義・別・序・信なり」と言う。
『中庸』の天下達道五、および『孟子』の親・義・別・序・信とは、以下のくだりである。
天下の達道は五、之を行う所以の者は三。曰く、君臣なり、父子なり、夫婦なり、昆弟(こんてい)なり、朋友の交なり。五者は、天下の達道なり。
(『中庸』第二十章より)
だが人民というのは飽食暖衣してぶらぶら暮らし、何も教化しなければ、ケダモノと変わりがない。聖人はまたこれを憂えた。そこで舜は契(せつ。殷王家の祖先)を司徒(しと。文部大臣)に命じて、人倫を教えさせた。すなわち父子の間には親(しん)を、君臣の間には義(ぎ)を、夫婦の間には別(べつ)を、長幼の間には敍(じょ)を、そして朋友の間には信(しん)を設定したのであった。
(『孟子』滕文公章句上、四より。現代語訳)
荀子の批判する「五行」は上の五達道・五倫であるという見解は、漢文大系もまたこれを是としている。
しかしながら、『荀子』を読めば、荀子自体が五達道・五倫と同じ用語を用いて同じ倫理を重視している例がいくつも見られる。
- 君臣の義、父子の親、夫婦の別は、則ち日に切瑳して舍かざるなり。(天論篇)
- 父子の義、夫婦の別に於ける、齊・魯の孝具・敬父なるに如かざる者は、何ぞや。(性悪篇)
- 君臣父子、兄弟夫婦は、、、夫れ是を之れ大本と謂う。、、、君は君、臣は臣、父は父、子は子、兄は兄、弟は弟たるは一なり。(王制篇)
ここから新釈漢文大系の藤井専英氏は、思・孟と荀子との間に何の差異があるのか、という点について説明を加える。
問題は一方が主観派の名将に対し、他方が客観派の驍将であることである。主観派が孔子・曾子・子思・孟子と忠信即ち誠を重んじて内省に力を注いだのに対し、荀子は、、、人間行為の外部的準則たる礼を重視し、荀子は人間が君・臣・父・兄・子・弟・夫・妻として人倫社会で持つべき心構えを論じ、、、それが皆同一人物の時処位を異にした接触面であり、したがって人はこのすべての面を同時に妥当する必要を述べ、これを兼ね併せて能くする法として「礼」を審かにすべきことを説いている。、、、(思・孟のような)主観に基づく君臣・父子・夫婦・昆弟・朋友の人倫関係の解釈が、「あんなものが行為・行動と言えるものか」「人倫はもっと地についたものでなくてはならぬ」と、思・孟を攻撃させる結果となったのであろう。
(新釈漢文大系『荀子』上巻、149ページ)
藤井専英氏はこのように込み入った説明で、なぜ荀子が言葉的には五達道・五倫と同じ用語を用いながら、この非十二子篇で思・孟の「五行」を批判するのか、に注釈しておられるのである。
しかしながら、荀子が孟子の主張を特に取り上げて批判する性悪篇において、その批判点は孟子の五倫の内容についてではない。批判されているのは、孟子の性善説である。性悪篇で検討したように、孟子の性善説はその根拠にいわゆる「四端説」がある。人間の性は善であり、その善である心中の始原的な衝動として、惻隠・羞悪・辞譲(または恭敬)・是非がある。この四つの端(はじまり)を自己努力によって伸ばすことによってそれぞれ仁・義・礼・智の徳に結実させるのが人間の目標である、と孟子は説いたのであった。
さて、ここで孟子の挙げる仁・義・礼・智の四つの徳に信を加えたならば、後世の用語でいう「五常」となる。『孟子』書中においては、仁・義・礼・智・信の五常を並列してこれを心中の端と結び付ける構成とはなっていない。だが、孟子の性善説に立てば、信の徳もまた心中の端に根拠を持つ善でなければならないはずである。『孟子』書中の構成では四端―仁義礼智の結びつきとして性善説が説明されているが、別のところで孟子学派は仁義礼智信の五つの徳を心中の端から説明する試みを行っていたのではないだろうか?そして孟子の性善説が彼の独創ではなく、先行する子思の思想を発展させた可能性は、孟子の思想系譜上から十分に考えられる。
私は、非十二子篇における「五行」は五達道・五倫であるという説にはあまり賛同できない。なぜならば五達道・五倫は荀子にとって反対する理由がなく、上に例を挙げたように荀子もまたこれらを守るべき礼義として称揚しているからである。むしろ楊注の言うように「五行」=五常であり、五常の説とは孟子学派の性善説を指していて、これを荀子は孔子の学を歪めて作った妄言であると批判した、と考えたほうが、性悪篇における性善説批判の内容と合致するのではないか、と思うところである。これがまず、私の「五行」への一つめの仮説である。
だが「五行」については、もう一つ別の仮説を立てることができるかもしれない。猪飼補注は、非十二子篇の「五行」は五行生克旺相の説、と注している。五行生克旺相の説とは、すなわち陰陽五行説のことである。猪飼補注は、子思と孟子の著作の中で散逸した部分の中に陰陽五行説に当たる記述がなかったとはいえない、と言う。猪飼補注が五行説ではないか、と疑問に思う理由は、荀子の子・孟への批判がここで激烈なところにある。五達道・五倫(性善説もそうであろう)などの主張であれば荀子とは大同小異であって、荀子が「深遠なことを言いながら明確な説明を欠き、難解なことを言って明解さがない」と言って正道と相容れないと罵るからには、荀子から見てそこまでの邪説であったのだろう、という推測がここで起こるのである。もし「五行」が陰陽五行説であったとすれば、「天人の分」(天論篇)を唱える合理主義者である荀子は、これを100%退けなければならなかったであろう。
漢代初期に編纂されたという『大戴礼記』および『礼記(小戴礼記)』は、当時伝えられていた儒家の礼に関するテキストが始原となっている。そこには『荀子』各篇とほぼ一致するテキストが収録されていると同時に、『大戴礼記』曾子天円篇あるいは『礼記』礼運篇などでは君子の政策と宇宙の陰陽・五行とを相関させる主張が展開されている。漢代の陰陽五行説や天人相関説は、このような儒家の宇宙論から発展したと考えられる。漢代以前に陰陽五行説や天人相関説が存在していたかどうかは、はっきりしたことは分からない。しかしながら、『史記』仲尼弟子列伝における有若のエピソードなどを見る限り、孔子の後継者たちの中には孔子を予知能力者とみなすオカルト的思想が存在していたことが推測される。だが、荀子学派はオカルト的思想とは無縁であり、陰陽五行説や天人相関説を唱えた形跡は全く見られない。
もしかしたら、荀子学派とは並行して別の儒家学派があって、それが陰陽五行説や天人相関説を信奉して漢代にまで伝えたのかもしれない。もしそれが子思・孟子の属する儒家の魯学派であったとすれば、どうであろうか?現存する子思・孟子のテキストの中には陰陽五行説や天人相関説説は見えないが、孟子は中華世界には五百年周期で聖王が現れる、という神秘主義的な歴史哲学を奉じていた(公孫丑章句下、十三)。孟子は君子の生き方に関しては外物に惑わされずに生きよ、と合理的な人間主義思想を掲げたが、自然現象や歴史に対しても合理的な推論を行うことができていたかは、分からない。もしかしたら五行説は孔子死後に子思あたりが理論化してそれが孟子に受け継がれ、漢代に至るまで魯学派の末裔によって継承されていたのかもしれない。だが斉で活動した荀子は魯学派に属しておらず、それで子・孟の末裔である魯学派の五行説を儒家にあるまじき邪説の残滓であると、最大級の攻撃を行ったのかもしれない。しかし、この説には証拠がないので、単なる憶測を超えることができない。
[追記]
1993年に、中国で『郭店楚簡』と名付けられた古代の竹簡文が発見された。
考証の結果、これらの出土文献は、孟子と同時代の紀元前300年ごろのテキストであるという説が現在有力視されている(もっと遅い年代のものであるという異論もある)。
その『郭店楚簡』には、『老子』の異本が収録されていて、これが紀元前300年ごろのテキストであるという考証に従うならば、これは現在確認された中で『老子』のもっとも古いバージョンである。
また『郭店楚簡』には、いくつかの儒家系のテキストも含まれていた。(1)『礼記』緇衣篇と一致するテキストが出土した。(2)「性自命出(せいはめいよりいず)」と名付けられた新発見の儒家系テキストがあった。および(3)「五行(ごこう)」と名付けられた儒家系のテキストがあり、これは20年前に発掘された馬王堆漢墓から出土した「五行」と内容が重なっていた。もしこれらが孟子と同時代のテキストであるとするならば、儒家思想の戦国時代中期の姿を示唆する文献となって、古代儒家思想の発展史として重要である。孔子とその弟子の曾子の没後から孟子が歴史の表舞台に登場するまでのおよそ1世紀間の儒家思想史は、これまで空白であった。その時代をつなぐ儒家思想家である子思、および孟子の若年時代の思想については、確実にその時代のものであると推定できるテキストが存在しなかった。たしかに『礼記』に所収の四篇(中庸篇、緇衣篇が含まれる)は、子思一派の著作『子思子』から収録されたものである、という記録はあった。だが『子思子』そのものが散逸してしまったので、現行の『礼記』テキストが子思一派の思想を本当に忠実に伝えているのか、それとも後世の改変を受けたものであるのか、という決することができない文献学的課題を抱えていた。いま『郭店楚簡』によって子思の作であると伝えられた篇の一つが出土したことの意義は、それゆえに大きい。『郭店楚簡』のテキストは、子思および初期孟子の思想を示している可能性が考えられるのである。
『郭店楚簡』所収の新発見のテキストには、先述のとおり「性自命出」および「五行」と名付けられたものがある。「性自命出」は『礼記』中庸篇の思想の原型といえる論理が見えて、子思一派のテキストである可能性が示唆されている。そして「五行」は、「仁・義・礼・智・聖」の五行を展開したテキストであった。この五行は孟子の「仁・義・礼・智」に「聖」を加えたものであり、後世の五常は「聖」のかわりに「信」を加えたものである。こうして、「五行」とは孟子の性善説の原型をなす主張であって、孟子は(おそらく子思の)「五行」説を継承発展させて自らの「仁・義・礼・智」説を形成させたものと思われるのである。
よって、戦国時代当時の思想であって後世には失われた『郭店楚簡』所収の「五行」が、戦国時代末期の荀子による子思・孟子学派への批判の真意を指し示している可能性が高い。ならば荀子の「五行」批判は結局子思・孟子学派の性善説(およびそれに先行する主張)への批判ということになり、性悪篇の孟子批判と整合するだろう。『郭店楚簡』テキストにおいては「性」から「五行」が生ずると読むことができる論理構成となっているのであって、人間の善なる「性」の発展形が人間道徳である、という性善説の構成と一致する。いっぽう荀子は性悪篇において「人の性は惡、その善なる者は僞(い)なり」と規定して、人間のナマの生物学的存在には「悪」つまり生存本能しかなく、人間道徳は後天的な学習を積み上げることによって獲得するものである、と主張した。荀子は、社会契約説になぞらえられる自らの社会統治論を立てるに当たって、社会と人間存在が人為による加工によって善に秩序付けられる、という点を強調したゆえに、子思・孟子の性善説的主張を批判したのであった。以上のことは、このサイトの富国篇・性悪篇のコメントにおいて、私が展開したところである。