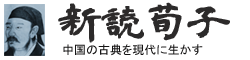|
孟子は、「人間の『性』は善である」と言う。これには、「そうではない」と答えよう。およそ古今において天下のいわゆる善といえば、正理(正しい道理)・平治(平らかな治世)のことである。いわゆる悪といえば、偏険(正道から偏って衝突すること)・悖乱(正道から外れて争乱すること)のことである。これが、善と悪との区分というものである。いま、本当に人間の『性』は本来的に正理・平治であると思うのであるか?それならば、どうして聖王が必要であろうか、礼義が必要であろうか。人間の『性』は本来的に正理・平治であるならば、聖王と礼義があったとしても、何もそれに付け加えることなどないではないか。しかし真実はそうではなく、人間の「性」は悪である。ゆえに、いにしえの時代、聖人たちは人間の「性」が悪であって、偏険にして不正であり、悖乱にして治まり難いことを直視したのであった。よってこの度し難い人間たちのために君主の威勢を設立し君臨し、礼義を明示してこれを教化し、公正な法を起草してこれを統治し、刑罰を厳重にしてこれを禁圧し、こうして天下すべてに治世をもたらし、人間を善に合一させたのであった。これが聖王の統治であって、礼義の教化であった。今、試みに君主の威勢を取り除き、礼義の教化をなくし、公正な法の統治を取り除き、刑罰の禁圧を無くしてみて、そのまま座って天下の人民が互いにどのような行動を取るか、観察してみたまえ。この状況の下では、強者は弱者を傷害してこれから奪い、多数者は少数者に暴力を加えてこれを引き裂くであろう。こうして天下が悖乱して、互いが互いを討ち合って滅びることは時間の問題となるであろう。これを見れば、人間の「性」が悪であることは明確であり、人間の善は「偽(い)」の結果なのである。ゆえに、いにしえの治世をよく説明できる者は、必ず今の時代に一致する内容を見出すのである。また天のなせるわざをよく説明できる者は、必ず人間の天与の性質からその徴候を読み取るのである。およそ論議というものは、論理的な整合性を貴び、かつ実証的な一致を貴ぶ(注1)。ゆえに座りながらにして正しい論議を立てることができるのであり、いざ立てばこの論議を実行することができるのであり、実行された政策が天下に広く施行されうるのである。論理的な整合性も実証的な一致もなくして、それで座りながら論議を立てたとしても、その論議は政策として実施不可能であり、そんな政策は天下に広く施行されることは不可能である。なんという間違いであろうか。ゆえに、「性」が善であると言う者は、聖王から去って礼義を捨てる者である。だが「性」が悪であると言う者は、聖王に与(くみ)して礼義を貴ぶ者である。木を矯(た)める器具が作られたのは、曲がった木があるからである。墨縄(すみなわ)が作られたのは、真っ直ぐでない材木があるからである。君主を立てて礼義を明示するのは、人間の「性」が悪だからである。これを見れば、人間の「性」が悪であることは明確であり、人間の善は「偽」の結果なのである。もともと真っ直ぐな木であるならば、器具を使わないでも真っ直ぐである。だがこれは、その「性」が真っ直ぐだからだ。曲がった木は、必ず器具で矯正したり熱を当てたりする作業を行うことによって、はじめて真っ直ぐとなる。これは、その「性」が真っ直ぐでないからなのだ。人間の「性」は悪なのであるから、必ず聖王の統治と礼義の教化を行うことによって、その後にはじめて天下すべてに治世をもたらされて、人間は善に合一するのである。これを見れば、人間の「性」が悪であることは明確であり、人間の善は「偽」の結果なのである。
(注1)原文の「弁合」を論理的な整合性、「符験」を実証的な一致、と訳した。楊注は「弁合・符験」を「論議之を別て合するが如く、之を符して験するが如くして、然る後に施行す可し」と言う。論議するときに区別してそれが内部的に整合し、論議が立てた説が検証して事実と一致して、それで始めて論議を実行できる、ということである。
|
|
《原文・読み下し》 孟子曰く、人の性は善なり、と。曰く、是れ然らず。凡そ古今天下の所謂(いわゆる)善なる者は、正理・平治なり。所謂惡なる者は、偏險・悖亂(はいらん)なり。是れ善惡の分なり。今誠に人の性は固(もと)より正理・平治なりと以(おも)えるか、則ち有(また)惡(いずく)んぞ聖王を用いん、惡んぞ禮義を用いんや。聖王・禮義有りと雖も、將(は)た曷(なん)ぞ正理・平治を加えんや。今然らず、人の性は惡なり。故に古者(いにしえは)聖人人の性は惡なるを以て、以て偏險にして正しからず、悖亂にして治まらずと爲す。故に之が爲に君上の埶(せい)を立ちて以て之に臨み、禮義を明(あきら)かにして以て之を化し、法正を起して以て之を治め、刑罰を重くして以て之を禁じ、天下をして皆治に出でて、善に合せしむるなり。是れ聖王の治にして禮義の化なり。今當試(こころみ)に(注2)君上の埶を去り、禮義の化を無くし、法正の治を去り、刑罰の禁を無くし、倚(い)して天下民人の相與(くみ)するを觀んか。是(かく)の若くなれば、則ち夫の强き者は弱きを害して之を奪い、衆(おお)き者は寡(すくな)きを暴して之を譁(か)す(注3)。天下の悖亂して相亡ぶや、頃(しばらく)を待たず。此を用(もっ)て之を觀れば、然れば則ち人の性惡なることは明かにして、其の善なる者は僞(い)なり。故に善く古を言う者は、必ず今に節(せつ)(注4)有り、善く天を言う者は、必ず人に徵(ちょう)有り。凡そ論なる者は其の辨合(べんごう)有り、符驗有るを貴ぶ。故に坐して之を言い、起ちて設く可く、張りて施行す可し。今孟子曰く、人の性は善なり、と。辨合・符驗無く、坐して之を言うも、起ちて設く可からず、張りて施行す可からず、豈に過つこと甚しからずや。故に性善なれば、則ち聖王を去りて、禮義を息(や)む。性惡なれば、則ち聖王に與(くみ)して、禮義を貴ぶ。故に檃栝(いんかつ)の生ずるは、枸木(こうぼく)の爲(ため)なり。繩墨(じょうぼく)の起るは、不直の爲なり。君上を立て、禮義を明かにするは、性惡なるが爲なり。此を用て之を觀れば、然れば則ち人の性の惡なること明かにして、其の善なる者は僞なり。直木は檃栝を待たずして直なる者は、其の性直ればなり。枸木は必ず將(まさ)に檃栝・烝矯を待ちて然る後に直ならんとする者は、其の性不直なるを以てなり。今人の性惡なれば、必ず將に聖王の治、禮義の化を待ちて、然る後に皆治に出で、善に合せんとするなり。此を用て之を觀れば、然れば則ち人の性の惡なること明かにして、其の善なる者は僞なり。 (注2)集解の王先謙は「當」は「嘗」の借字である、と言う。「嘗試」で、こころみに。
(注3)集解の兪樾は、「譁」は「華」となすべし、と言う。「華」はひきさくこと。 (注4)荻生徂徠は、「節」は符節なり、と言う。増注の久保愛、および集解の王引之はともに漢書董仲舒伝を引用する。すなわち董仲舒伝を読み下せば「善く天を言う者は、必ず人に徵有り、善く古を言う者は、必ず今に驗有り」とある。ここより王引之は「節」はすなわち「験」なり、と言う。「節」を符節と取れば、「一致する内容」の意味となるだろうし、これを「験」と取れば、「しるし」となるだろう。ここでは、徂徠を取る。 |
再び、孟子の批判に戻る。ここで荀子は、孟子の説に「その性善説を国家の統治に実際に適用する思考実験を行ってみよ。それで治世が実現できるのであれば、その説は実行可能である。だが実現できないのであれば、実行可能性のない空論にすぎない」と批判する。これは、痛烈な急所である。孟子に限らず、ほとんどのユートピア説はこの実験に耐えられない。
孟子の性善説を突き詰めると、人間は国家権力のないアナーキーでも自発的に秩序を立てることができる、という結論に導かれなければならない。なぜならば、人間には「四端」の一として恭敬(辞譲)の心があり、そこから人間は自発的に「礼」の徳を育んで秩序を形成できるはずだからである。しかし孟子は他方で王者と君子の秩序が社会に必要である、と主張している。これは孟子が気づかないところの矛盾であり、荀子はそれに気づいて孟子に対して「あなたの説では、国家がなくても秩序ができるというのですか?」と問い詰めるのである。できない、という前提に立つ荀子が儒家思想として統治論を論争したときに優位に立つのは、明確なことであろう。だがこれを国家がなくても秩序を作ることができる、と考えるのであれば、それこそ正名篇の最後で宋鈃の説を検討したときに想定した万人君子説に立たなければならないだろう。しかしこれは君子の特権性を無みする思想であるので、孟子にも荀子にも受け入れることはできないだろう。
しかしながら、荀子のこの性悪篇の主張にも、説明困難な問題がある。さきの性悪篇(3)の現代語訳を、再録しよう。
「性」が悪だとすれば、どうしてその人間が「性」から離れて善を目指すのであろうか?もしそれが自発的な動機であるとすれば、宋鈃が描くように人間はすべて自発的に「偽」を身に付けて寡欲となり、社会の衝突は回避されるのではないのか?そうでなくて人間は何もしないでいると「性」のままであって争うばかりであるならば、ひとり聖人と君子だけが(荀子の定義する語に従えば)「慮」を働かせて「知」・「能」を積み重ねて「偽」に到る、その動機はどこにあるというのであろうか?冒頭の勧学篇で荀子は学ぶ者により高みを目指すべし、と言って、君子の向上心を力説していた。その向上心の起源が、荀子の性悪説では十分に説明されているとは言い難い。
孟子が「四端」の説を挙げて人間の自発的な向上への意志を強調したのは、さきの伊藤仁斎が指摘したように、学ぶ人間に自らの可能性を自覚させる呼びかけを行うためであった。孟子の「四端」は、人間の他人に働きかける感情である点が重要である。すなわち「惻隠」は他人への憐れみであり、「羞悪」は自分と他人を比べた、あるいは社会総体に向けた不公正の感覚であり、「恭敬(辞譲)」はいうまでもなく他人より自己を低くする倫理感である。さきに私は互酬の原理を検討して、これが人間にとって国家以前の段階で発動する他人との交流の様式である、と書いた。孟子の「四端」もまた、人間の他人に働きかける感情であり、他人との交流を求める人間の始原的な動機であると言うことができるだろう。
私は、孟子の「四端」は、国家以前に人間が他人に働きかける始原的な動機を孟子的に整理した概念として、互酬の原理と通じるものがあると考える。孟子の理論的な弱さは、「四端」が人間の他人に働きかける善行為の側面だけを見ることに集中したことであり、それで荀子の批判を招くこととなった。しかしそれは、社会システムを構想するための理論としては不完全であるが、人間は本来的に他人に働きかけようとする動機を持っていることを指摘して、その中からあえて善なる動機だけを選んで行動すべし、と読むならば、それは倫理学として荀子よりも優れた分析であると評価することができるであろう。それは、国家による「法の支配」とは別個に考えるべき、人間の他人との交流を指摘するものだからである。