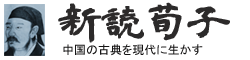小さなことをこつこつと積み上げていくには、一月ごとに行うのでは毎日行うことにはかなわず、一季ごとに行うのでは毎月行うことにはかなわず、一年ごとに行うのでは毎季行うことにはかなわない。だいたい人というものは、日々の小さなことをあなどって怠りがちである。そうしていざ大きな難事が起こってから、ようやく奮起して努力するものだ。こんな様子であるので、このような者は常に日々の小さなことをこつこつと行っている者にかなわないのである。どうして、差が出てくるのか。小さなことは、しばしば起こる。起こる日数は、極めて多い。よってそれに対処していったときの積み上がりは、きわめて大きい。いっぽう大きなことは、めったに起こらない。起こる日数は、多くない。よってそれに対処していったときの積み上がりは、しょせん小さなものである。ゆえに、毎日を惜しんで怠りない(注1)者は王者となり、ときどき努力する者は覇者となり、ミスに対処しているだけの者は危うく、荒れっぱなしで放置する者は滅亡するのである。ゆえに王者は毎日をつつしみ、覇者は一年に四回程度つつしみ、わずかに存続している国は危機に陥ってからようやく憂慮し、亡国は滅亡するときになってようやく滅亡するしかないことに気づき、死ぬときになってやっともう死ぬしかないことを知るのである。国のわざわいは、悔いても悔いきれない。覇者の善事はたとえ見えたとしても、季節ごとにしか起きないので記録することもできよう。しかしながら王者の功名は毎日のことであるので、小さなことが大量にあってとても記録することができない。財物や宝物は、大きければ大きいほど評価される。しかし政治・教化の功名はその逆で、大きければ大きいほど評価されないものだ。真実は、小さなことをこつこつと積み上げていく者こそが、もっとも速やかに功名を成し遂げるのである。『詩経』に、この言葉がある。:
ここに、真理がある。 およそ悪人が現れる理由は、上が礼義を尊ばず、礼義を敬しないところにある。礼義というものは、人が邪悪をなすことを禁止する装置なのである。いまもし上が礼義を尊ばず礼義を敬しなければ、下の人民はすべて礼義を捨てて邪悪に走ろうという心が起こるであろう。これが、悪人が現れる理由なのである。上に立つ者は、下の者たちの師である。下の者たちが上の者に和するのは、たとえるならば楽器の響きが人の歌声に合わせるようなものであり、また影が元の形をなぞらえるようなものである。ゆえに、人の上に立つ者は、慎まなければならない。そもそも礼義なるものは、人間の心の内においてこれを制御し、人間の外の万物においてこれを統御し、上に立つ者を安楽にして、下に従う者を秩序立てる原理なのである。内・外・上・下に規則があることは、礼義の本意である。ならばすなわち、およそ天下を治める要点は、礼義を第一として忠信をこれに次がせることにあるだろう。むかし禹・湯は、礼義を第一として忠信に励んで、天下は治まった。桀・紂は礼義を捨てて忠信に背いて、天下は乱れた。ゆえに人の上に立つ者は、必ずや礼義を慎み、忠信を務めて、それでようやく治まるのである。これが、人に君主たる者の大本である。部屋の中ですら掃除できていない状態では、外の庭が草延び放題であることに構っている暇がない。白刃が胸の前に突きつけられていては、目の前で流れ矢が飛んでいることに気づく暇がない。戟(げき。斧と槍が合体した武器)の刃が首筋に当てられていては、たとえ手の指を切られても構ってはいられない。これらのことを、しなくてもよいわけでは決してない。ただ、より痛い、より危ない、より先にしなければならない、ということが目前に迫っているからである。(ゆえに、大きなことが起こってから動くようでは王者とはなれない。王者となるためには、常に礼義の規則に従い、日々の忠信に務めるのである。) (注1)原文「日を善くする」。楊注は「善」を愛惜して怠らず、と言う。
|
|
《原文・読み下し》 微を摘むは、月(つきづき)は日(ひび)に勝らず、時(ときどき)(注2)は月に勝らず、歲(としどし)は時に勝らず。凡そ人好んで小事を敖慢し、大事至りて然る後に之に興り之に務む。是(かく)の如くなれば、則ち常に夫の小事に敦比(とんひ)する者に勝らず。是れ何ぞや、則ち小事の至るや數(さく)、其の日を縣するや博(はく)、其の積爲るや大なり。大事の至るや希、其の日を縣するや淺、其の積爲るや小なる。故に日を善くする者や王たり、時を善くする者や霸たり、漏(ろう)を補う者や危く、大荒なる者は亡ぶ。故に王者は日を敬し、霸者は時を敬し、僅に存するの國は危くして後に之を戚(うれ)い、亡國は亡に至りて而(しこ)うして後に亡を知り、死に至りて而して後に死を知る。國の禍敗は、勝(あ)げて悔ゆ可からざるなり。霸者の善は著(あら)わるるも、時を以て託(しる)す(注3)可きなり。王者の功名は、日に志(しる)すに勝う可からざるなり。財物・貨寶は大を以て重しと爲し、政教・功名は是れに反す、能く微を積む者は速(すみやか)に成る。詩に曰く、德の輶(かろ)きこと毛の如きも、民克く之を舉ぐること鮮(すくな)し、とは、此を之れ謂うなり。 凡そ姦人の起る所以の者は、上の義を貴ばず、義を敬せざるを以てなり。夫の義なる者は、人の惡と姦とを爲すを限禁する所以の者なり。今上義を貴ばず、義を敬せず。是の如くなれば、則ち天下の人・百姓、皆義を棄つるの志有り、姦に趨くの心有り。此れ姦人の起る所以なり。且つ上なる者は下の師なり。夫の下の上に和するは、之を譬(たと)うるに猶お響の聲に應じ、影の形に像(かたど)るがごときなり。故に人の上爲る者は、順(つつし)(注4)まざる可からざるなり。夫の義なる者は、內は人を節して、外は萬物を節する者なり。上は主を安んじて、下は民を調する者なり。內外・上下節ある者は、義の情なり。然らば則ち凡そ天下を爲(おさ)むるの要は、義を本と爲して、信之に次ぐ。古は禹・湯義に本づき信を務めて天下治まり、桀・紂義を棄て信に倍(そむ)きて天下亂る。故に人の上爲る者は、必ず將(は)た禮義を愼み、忠信を務めて、然る後に可なり。此れ人に君たる者の大本なり。堂上糞(ふん)(注5)せざれば、則ち郊草曠芸(こううん)を瞻(み)ず(注6)、白刃胷(むね)を扞(おか)せば、則ち目流矢を見ず、拔戟(ばつげき)首に加うれば、則ち十指も斷ずるを辭せず。此を以て務と爲さざるに非ざるなり、疾養・緩急の相先んずる者有ればなり。 (注2)ここでの「時」は一季、三ヶ月のこと。
(注3)集解の兪樾、増注ともに「託」は「記」の誤りと言う。 (注4)増注は「順」は「愼」に通ずと言う。 (注5)集解の郝懿行は「糞」字を仮借であると言う。掃除する。元の字は「拚」の異体。 (注6)集解の王念孫は「曠瞻」二字を衍文とみなす。漢文大系はこれを取って「郊草芸(くさぎ)らず」と読んでいる。楊注・猪飼補注・金谷治氏・藤井専英氏はすべて「曠瞻」二字を読んでいる。金谷・藤井説に従って読む。 |
彊国篇の末尾は、教訓の文で終わる。非常に技巧的な文章であり、『詩経』の引用から逆算して言葉を作ったかのような印象すらある。『荀子』の中には荀子作の賦(ふ)という形式の長詩を集めた賦篇第二十六も収録されている。荀子は礼の大家として、美文を作ることにも長けていた。つまりリズムある美文によって、真理を雰囲気で理解した気にさせようとしているのである。ただ現代の私が読むと、時にいささか冗長な表現が見える。
荀子は、毎日こつこつと積み上げて、目立たないが大きな功績があるのが王者の政治のしかけであり、王者以外はこれを行わない、と言う。しかしながら秦国の法が、時々の場当たり的な努力の結果であるはずはないのであるが。法というものは過去の小さな判例解釈の積み重ねの結果、合理的に運用できる中庸点が見出された結果現在の法体系がある、ということは法学の常識であろう。後世の実務を軽視する道学者たちは知らないが、こと荀子が秦の法とて小さな努力の積み重ねとして能率的に運営されていることを、知らないはずがない。荀子は儒家の中でも最も礼義の法的側面を重視する社会思想家なのである。
「悪法も法なり」という言葉がある。法の実証的(positive)な側面を重視するのであれば、法の最も重要な点はその論理的整合性であろう。システムとして運営されるときに矛盾が起きないのであれば、法が何を禁止して何を命じているかの内容は、不問に処してもよい。
しかし法の規範的(normative)な側面を重視するのであれば、法は悪法であってはならず、「正しい」価値観に基づいた法でなければ批判されなければならないであろう。何が「正しい」価値観であるか、というのが次の問題となるのであるが。
荀子は、秦国の法の実証的な側面に対しては、これを絶賛していると言ってよい。前回のくだりで見たように、秦国の法のシステムは荀子が想定する礼義のシステムのとおりに動いていたのである。
ただ、荀子は秦国の法を規範的に批判するのである。秦国の法は、儒家が推奨する「正しい」価値観に沿っていない。それは偽りの「強者」の法であり、「覇者」の法ですらなく、ましてや「王者」の法からは遠い。ゆえにそれは秦国では通用するが、中華世界全体では通用しない。荀子の批判点は、本来そこにあったはずである。実証的な側面と規範的な側面とをカント的に分離して論じないので、読む者には荀子がまるで秦国の全てを批判しているように見えてしまう。荀子じしんもまた、秦国の制度を規範的に批判しているのか実証的に批判しているのかを自覚して分離できていなかった、と私は読んで思う。思想家たちは両者を区別できなかったが、実際の実務家たちは区別していた。漢代の政治家たちは、秦国の政策を規範的に厳しく批判した。しかしながら、漢帝国のシステムは、秦国の遺した法と統治制度を実証的に全て継承して運営されたのである。秦国の統治全てが悪い、と批判するのは、空理空論の道学者であるにすぎない。
続いて、天論篇に進みたい。荀子の合理的自然観、つまり古代中国の合理的自然観が展開された、『荀子』中の白眉の一篇の一つである。