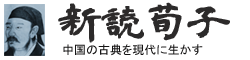国を乱す君主はいるが、ひとりでに乱れていく国というものはありえない。国を治める人材はいるが、ひとりでに国を治める法などはありえない。羿(げい。伝説の弓の名手)の射術の法は後世まで滅びなかったが、羿の射術の法に倣った後継者たちが歴代必ずしも百発百中たりえたわけではない。禹(う。夏王朝の創始者)の法はいまだに存続しているが、禹の後を継いだ夏王朝の君主たちは歴代必ずしも王者たりえたわけではない。ゆえに、法というものはそれ単独で成り立つことはできず、法判断(注1)もまた自ずから行われるわけにもいかないのである。しかるべき人材を得たならば法も法判断も存続するが、その人材を失えば亡んでしまうのだ。法というものは統治のはじまりであり、君子というものは法の源なのである。ゆえに君子がいれば、法が簡略であってもすみずみまで統治が行き渡る。しかし君子がいなければ、法が完備していても順序立った施策が行えず、事物の変化に対応することができず、よって国が乱れるための十分な要因を作ってしまう。また法の意義を理解せずに法の条文だけを正しく行おうとする者は、博学といえどもいざ事に臨めば必ず混乱するものである。ゆえに明主はしかるべき人を得ることに急ぎ、いっぽう闇主は大きな権勢を得ることに急ぐ。しかるべき人を得ることに急ぐならば、君主は身体を楽にしたままで国は治まり、功績は大きく名声は美しくなり、最上ならば王者となってそれに劣っても覇者となるであろう。だがしかるべき人を得ることに急がず大きな権勢を得ることに急ぐならば、身体を労苦させても国は治まらず、功績は亡んで名は辱められ、社稷(しゃしょく)(注2)は必ず危うくなるだろう。ゆえに君主たる者は、しかるべき人を求めるために労苦して、この人を用いるときには休むのである。『書経』に、この言葉がある。:
これが、王者の仕事を言っているのである。 割符を合せて契約書を分かち持つのは、互いの信用を担保するためである。しかし上の者が権謀を好めば、臣下に官吏たち、それにいつわりの言葉を好む大衆たちは、上の行為に乗じてやがて欺きを行うことであろう。くじを行うのは、公正な選抜を行うためである。しかし上の者が私事によって不正を行うならば、臣下に官吏たちもまた上に乗じてやがて不公正を行うことであろう。秤(はかり)と錘(おもり)を用いるのは、公平なつりあいを量るためである。しかし上の者が下の者を転覆させることを好むならば、臣下に官吏たちもまた上に乗じてやがて険悪な行為に出ることであろう。枡(ます)と概(ますかき。下の注8参照)を用いるのは、ひとしく公平な量を量るためである。しかし上の者が下の者から利を貪ることを好むならば、臣下に官吏たちも上に乗じてやがて収公する分を余分に増やして下に与える分を削り取り、規準なく人民から搾取することであろう。ゆえに、道具とか数量とかは統治の末流なのであって、統治の本源ではない。そういった道具や数量を用いる君子こそが、統治の本源なのである。官吏たちは法の条項を守るが、君子はそれらの本源を養うのだ。本源が澄めば末流も澄み、本源が濁れば末流も濁るであろう。ゆえに上の者が礼義を好み、賢人を貴んで能力ある者を登用し、利を貪る心がなければ、下の者もまた謙譲をきわめ、忠信をきわめ、臣下たる道・子たる道に謹むであろう。もしこのようであるならば、下賤の人民ですらも割符や契約書を用いることを待たずして信用を生み、くじを用いることを待たずして公正を生み、秤と錘を用いることを待たずして公平なつりあいを生み、枡と概を用いることを待たずして公平な量が量られることであろう。このゆえに褒賞を用いずして人民は励み、刑罰を用いずして人民は服し、官吏が労苦することなくして事は治まり、政令は煩雑でなくても風俗は美しくなり、人民は必ずや上の法に従い、上の意志にならい、上の企画した事業に励み、これらに安んじて楽しむことであろう。こうなれば人民は収税されてもその出費を考えなくなり、労役を課せられてもその労苦を考えなくなり、外敵の侵入があっても己の死を考えずに戦い、城郭は整備せずとも固く守られ、武器は研磨せずとも鋭くなり、敵国は服属させずとも屈服し、四海の人民は政令を待たずして統一されることであろう。これが、泰平の極地というのである。『詩経』に、この言葉がある。:
この言葉のように、天下が服するのである。 |
|
《原文・読み下し》(注3) 亂君有りて、亂國無く、治人有りて、治法無し。羿(げい)の法は亡ぶに非ざるも、而(しか)も羿は世(よよ)中(あた)らず。禹の法は猶お存すも、而も夏(か)は世(よよ)王たらず。故に法は獨り立つこと能わず、類は自ら行うこと能わず、其の人を得れば則ち存し、其の人を失えば則ち亡ぶ。法なる者は、治の端なり、君子なる者は、法の原(もと)なり。故に君子有れば、則ち法省くと雖も、以て徧(あまね)きに足るも、君子無ければ、則ち法具(そな)わると雖も、先後の施を失い、事の變に應ずること能わず、以て亂るるに足る。法の義を知らずして、法の數を正す者は、博(はく)(注4)と雖も事に臨めば必ず亂る。故に明主は其の人を得ることを急にして、闇主は其の埶(せい)を得ることを急にす。其の人を得ることを急にすれば、則ち身佚(いつ)して國治まり、功大にして名(な)美に、上は以て王たる可く、下は以て霸たる可し。其の人を得ることを急にせずして、其の埶を得ることを急にすれば、則ち身勞して國亂れ、功廢して名辱(はずか)しめられ、社稷(しゃしょく)必ず危し。故に人に君たる者は、之を索(もと)むるに勞して、之を使うに休す。書に曰く、惟(ただ)(注5)文王敬忌して、一人以て擇ぶ、とは、此を之れ謂うなり。 符節を合し、契券を別つ者は、信を爲す所以なり、上權謀を好めば、則ち臣下・百吏・誕詐(たんさ)の人、是に乘じて後に欺く。籌(ちゅう)を探り、鉤(こう)を投ずる(注6)者は、公を爲す所以なり、上曲私を好めば、則ち臣下・百吏、是に乘じて後に偏す。衡(こう)・石(せき)・稱(しょう)・縣(けん)(注7)なる者は、平を爲す所以なり。上覆傾を好めば、則ち臣下・百吏、是に乘じて後に險なり。斗斛(とこく)・敦槩(じゅんがい)(注8)なる者は、嘖(さく)(注9)を爲す所以なり。上貪利(たんり)を好めば、則ち臣下・百吏、是に乘じて後に豐取(ほうしゅ)・刻與(こくよ)し(注10)、無度を以て民より取る。故に械數なる者は、治の流(りゅう)なり、治の原(もと)に非ざるなり。君子なる者は、治の原なり。官人は數を守り、君子は原を養う。原清(す)めば則ち流清み、原濁れば則ち流濁る。故に上禮義を好み、賢を尚(とうと)び能を使い、貪利の心無ければ、則ち下も亦將に辭讓を綦(きわ)め、忠信を致(きわ)めて、臣子に謹まんとす。是の如くなれば則ち小民に在りと雖も、符節を合し、契券を別つことを待たずして信に、籌を探り、鉤を投ずるを待たずして公に、衝・石・稱・縣を待たずして平に、斗斛・敦槩を待たずして嘖なり。故に賞用いずして民勸(はげ)み、罰用いずして民服し、有司勞せずして事治まり、政令煩ならずして俗美に、百姓敢て上の法に順(したが)い、上の志に象(のっと)り、上の事に勸みて、之を安樂せざること莫し。故に藉歛(せきれん)には費を忘れ、事業には勞を忘れ、寇難には死を忘れ、城郭は飾を待たずして固く、兵刃は陵を待たずして勁(するど)く、敵國は服を待たずして詘(くつ)し、四海の民は令を待たずして一なり。夫れ是を之れ至平と謂う。詩に曰く、王猶(おうゆう)允(まこと)に塞(み)つれば、徐方既(ことごと)く來る、とは、此を之れ謂うなり。 (注3)以下の君道篇は、全篇に渡って楊注がない。したがって日本江戸時代および中国清代の各注釈者の見解を基礎とせざるをえない。
(注4)宋本には「博」の下に「傳(伝)」字があり、元本にはない。増注は「傳」を除く。宋本に従う新釈は「博(ひろ)く傳(つた)えらる」と読み下している。 (注5)宋本は「唯」字に作る。 (注6)原文「探籌投鉤」。集解の郝懿行は、探籌は竹をけずって書を書きそれをさぐりとらせること、すなわち「くじ」のことであり、投鉤は未詳であるが『慎子』に見えることを指摘する。漢文大系、新釈ともに探籌も投鉤も「くじ」の意と解している。 (注7)衝は秤(はかり)、石は錘(おもり)、稱・縣はいずれも秤のこと。つまり、全体で秤と錘の意。 (注8)集解の盧文弨は「敦槩は即ち準槩(じゅんがい)なり」と言う。「槩(概)」字の本義は枡(ます)に盛った穀物から上にはみ出た分をかき切ってならし、分量を正確に量るために用いる棒のことである。「ますかき」と訓ずる。そこから「おおむね」という意味が派生した。ここでは斗斛すなわち枡と合せて用いられているので、敦槩すなわち準槩は「ますかき」の意である。 (注9)増注の久保愛は、嘖は平生の義なり、と言う。ひとしく公平にすること。 (注10)原文「則臣下・百吏、乘是而後豐取・刻與、、」。元本には「後」字の後に「鄙」字があるが、宋本にはない。王念孫は、元本の「鄙」字は、先行する各文で「是に乘じて後に」の後に一字が続いているので、後人が意図的に追加したものであろう、と言う。なぜならば先行する各文は前半と後半が対比する意味となっているが、ここでの文の前半「嘖」字に対比されるべき語句は「豐取・刻與」であって、これで対比は十分であって「鄙」を加える必要はないからである。集解本は王説に賛同して「鄙」字を置かない。 |
君道篇に始まる三篇は、君主・家臣・賢士の三者について述べたシリーズである。直前の王制篇・富国篇・王覇篇では法治官僚国家のシステムが述べられたが、ここからの三篇はそのシステムの担い手である為政者たちの心得が説かれることになる。彼に先行する孟子は為政者の心得を主張することに熱心であったが、為政者が効果的に働くことができるためのシステムを描くことに疎漏であった。荀子は、その欠点を補正して両者を語ろうとするのである。
まずこの君道篇では、君主への教訓が述べられる。冒頭で述べられているように、その要点は、賢明な宰相を選んでこれに行政を一任するべし、ということである。君道篇の長大な文章は、この一点のために展開されている。しかし正直な私の印象を申すならば、「君主は優良な宰相を選ぶべし」という教訓を与えるための心得として、ここまで長大な理論を君主に説明することに意義があるとは思えない。荀子の論述は統治のための理論を延々と述べることに過ぎて、国のために人を正しく選ぶ、という国の頂点に立つ人間への倫理的教訓としては、孔子や孟子の短い金言の人を動かす力に遠く及ばない。理論的であることが荀子の長所であり、かつ欠点である。
なお君道篇は、楊注が完全に欠落している。散逸したことは、間違いない。