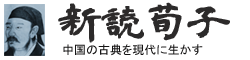|
礼とは、人の生まれるときと死ぬときとを厳粛に整えるのである。出生は人の始まりであり、死去は人の終わりである。始まりと終わりがともによくあれば、人の道はこれに尽きるだろう。ゆえに君子は万事始まりと終わりを慎んで行い、始まりも終わりも一貫して厳粛に行う。これが君子の正道であり、礼義の文飾である。例の、生きる者には厚く報いるが死んだ者は冷たくおざなりにする、というやり方は、知覚する力がある時期(つまり、生きている時期)は尊重するが、知覚する力が失せた後(つまり、死んだ後)には侮って扱うということだ。これはよこしまな輩の道であり、人の道にそむく心である(注1)。君子は人の道にそむく心が自らにあったならば、賤しい奴婢に接することですら自ら恥じる。いわんやそんな心で自らが貴び親しくする存在に仕えることができようか?仕える者の死を送る道とは、たった一回きりしか行えない。二回行うことはできないのだ。家臣として君主にその尊重の意を尽くす機会と、子として親にその尊重の意を尽くす機会は、ここにおいて最上のものとなるのだ。ゆえに、生者に仕えるときに忠節を厚くせず、恭敬を文飾で飾らない者は、これを粗野と言う。死者に仕えるときに忠節を厚くせず、恭敬を文飾で飾らない者は、これを礼知らずと言う。君子は粗野を賤しみ、礼知らずを恥じる。ゆえに天子は棺椁(かんかく。ひつぎと外囲い)を十重(注2)に作り、諸侯はこれを五重に作り、大夫は三重に作り、士は二重に作る。そうしてから葬礼の衣食については身分に応じて多寡と厚薄の区別が定められ、それぞれの翣菨(しょうしょう。ひつぎの装飾)の装飾の度合いに格差が定められて、死者を敬って飾り、生前から死後まで終始一貫した仕え方を守らせ、人としての願いをひたすらに満たしてやるのである。これがわが文明の建設者であった先王の正道であり、忠臣・孝子のきわみなのである。天子崩御の際の喪葬には、天下の人心を動員して諸侯たちを会葬させる。諸侯の喪葬には、その封国の関係国の人心を動員して大夫たちを会葬させる。大夫の喪葬には、一国内部の人心を動員して高潔な士たちを会葬させる。高潔な士の喪葬には、一郷(きょう。古代の行政区画で複数の州里を含む)の人心を動員して朋友たちを会葬させる。庶民の喪葬には、その一族を集合させて州里(しゅうり。古代の村単位)の人心を動員させる。だが刑を受けた罪人の喪葬には、一族を集合させることはできない。ただその妻子のみが会葬し、棺槨は厚さ三寸、屍衣は三着だけとなし、棺を飾ることはできない。昼間に葬送をすることはできない。ただ夕暮れに行き倒れを処分するようにこっそりと埋葬し、妻子は喪服せず日常の服装のままでこれを行わなければならない。家に戻っても哭泣の礼は行わず、喪服は着けず、親族だからといって服喪期間を礼のとおり守ることもせず、それぞれすぐに平常通りに戻り、それぞれ何ごともなかったかのように葬儀以前の状態に戻り、埋葬してしまった後には、喪中でもなんでもないかのように一切済ませてしまう。これぞ、死者への恥辱の最たるものである(注3)。礼というものは、吉事と凶事を慎重に取り扱い、その両者が衝突しないように取り計らう。纊(こう。綿)を鼻の下に着けて息がまだあるかどうかを確かめている段階では、かの忠臣・孝子はただ病気が重いことを心に思うだけであって、このときに殯(ひん。葬礼前のかりもがりの礼儀)とか斂(れん。納棺の礼儀)とかの道具を用意したりはしない。ただ涙を流して懼れつつしむばかりで、それでいてもっと生きて欲しいと願う心はやまず、生き永らえさせるための努力をやめはしない。そうして死去してから、ようやく葬礼の道具を用意し始めるのである。ゆえにたとえ裕福な家であっても、必ず死去してから一日置いた後に殯を行えるのであり、三日経ってから喪服が仕上がるのである。それから後に死去を遠方に告げる使者が出発し、葬礼の備品を作る者が作業を始めるのである。よって殯は長くても七十日以上を越えることはなく、短くても五十日より短いことはない。それは、これだけの期間の間に遠方からの弔問者が到着し、葬礼の備品が揃い、万事の準備が完了するからである。この段階に至ってその忠心は尽くされ、その礼節は大いに行われ、その文飾は備わるのである。そうした後に月始めに葬礼日を占い、その日の夕方に埋葬する地を占い、それから後に埋葬するのである。こうして日取りが決まってしまった後になっては、礼の規則において「行うべからず」とあれば、誰も行うことはならない。また礼の規則において「行うべし」とあれば、誰も止めることはならない。こうして三ヶ月後に行う葬礼は、生前の時と変わらないような備品を用いて死者を飾るのであり、この日までの三ヶ月間は、単に死者を家の中に置いておき生き残った遺族たちを慰めることだけが目的なのではない。この期間は、仕える者の死者への思慕を礼義の形によって尽くすという意味をもっているのである。
(注1)増注は「墨子を斥す」と注する。そのとおりであろう。
(注2)通説では天子の棺槨は「七重」が正しい、と言われている。ただ私は古礼に詳しくないので、その通りだと断言できる能力がない。なので原文のままにしておく。下の注5を参照。 (注3)ここの罪人の葬礼の叙述は、楊注も指摘するように『墨子』節葬篇への当てこすりである。つまり荀子は墨家がいにしえの美俗と推奨する簡便な葬礼をここで悪意を込めてなぞり、それを罪人を葬る方法だと揶揄しているのである。 |
|
《原文・読み下し》 禮なる者は、生死を治むるに勤む者なり。生は人の始にして、死は人の終なり、終始俱(とも)に善なれば、人道畢(おわ)る。故に君子は始を敬(つつし)みて終を愼み、終始一の如し。是れ君子の道にして、禮義の文なり、夫の其の生を厚くして、其の死を薄くするは、是れ其の知有るを敬みて、其の知無きを慢(あなど)るなり。是れ姦人の道にして、倍叛(ばいはん)の心なり。君子は倍叛の心を以て臧穀(ぞうかく)(注4)に接するも猶お且つ之を羞ず、而(しか)るを況(いわ)んや以て其の隆親する所に事(つか)うるをや。故に死の道爲(た)るや、一にして再復することを得可からざるなり、臣の重きを其の君に致す所以と、子の重を其の親に致す所以のものとは、是に於て盡(つ)く。故に生に事えて忠厚ならず、敬文ならざる、之を野と謂い、死を送りて忠厚ならず、敬文ならざる、之を瘠(せき)と謂う。君子は野を賤んで瘠を羞ず。故に天子は棺椁(かんかく)十重(注5)、諸侯は五重、大夫は三重、士は再重にして、然る後に皆衣衾(いしょく)(注6)に多少・厚薄の數有り、皆翣菨(しょうしょう)(注7)・文章の等有りて、以て之を敬飾し、生死・終始をして一の若くならしむれば、以て人願を爲すに足れり。是れ先王の道にして、忠臣・孝子の極なり。天子の喪は、四海を動かして諸侯を屬(しょく)し、諸侯の喪は、通國を動かして大夫を屬し、大夫の喪は、一國を動かして脩士を屬し、脩士の喪は、一鄉を動かして朋友を屬し、庶人の喪は、族黨を合して州里を動かす。刑餘(けいよ)の罪人の喪は、族黨を合することを得ずして、獨り妻子のみを屬し、棺椁(かんかく)三寸、衣衾(いきん)三領(さんれい)、棺を飾ることを得ず、晝(ひる)行くことを得ず、昏(こん)を以て殣(きん)し凡緣(はんえん)にして(注8)往きて之を埋(うず)め、反りて哭泣の節無く、衰麻(さいま)の服無く、親疏・月數の等無く、各(おのおの)其の平(へい)に反り、各其の始に復(かえ)り、已に葬埋すれば、喪無き者の若くにして止む。夫れ是を之れ至辱と謂う。禮なる者は吉凶を謹み、相厭(おお)わざる(注9)者なり。纊(こう)を紸(つ)け(注10)息を聽くの時は、則ち夫の忠臣・孝子、亦(また)其の閔(びん)なる(注11)を知るのみ、然り而して殯斂(ひんれん)の具、未だ求むること有らざるなり。涕(なみだ)を垂れて恐懼し、然り而して生を幸(ねが)うの心未だ已(や)まず、生を持するの事未だ輟(や)まざるなり。卒(しゅつ)して然る後に之を作具す。故に備家(びか)と雖も必ず日を踰(こ)えて然る後に能く殯(ひん)し、三日にして服を成す。然る後に遠きに告げる者出で、物に備うる者作る。故に殯は久しきも七十日に過ぎず、速(すみや)かなるも五十日を損せず、是れ何ぞや。曰く、遠き者以て至る可く、百求以て得可く、百事以て成る可し。其の忠至れり、其の節大なり、其の文備われり。然る後に月朝(げっちょう)日を卜(ぼく)し、月夕(げっせき)宅を卜し、然る後に葬るなり。是の時に當りてや、其の義止まれば、誰か死を行うことを得ん、其の義行かば、誰か是を止むることを得ん。故に三月の葬は、其の䫉(かたど)る(注12)こと生の設(もうけ)を以て死者を飾るなり、殆(ほと)んど直(ただ)に死者を留めて以て生を安んずるのみに非ざるなり、是れ隆を思慕に致(きわ)むるの義なり。 (注4)増注は、「臧穀」は王覇篇の「臧獲」であり賤役の名、と言う。奴婢のこと。
(注5)集解の王引之は、「十」は疑うはまさに「七」に作るべし、と言う。その理由は、礼では上位から下位に降りれば二ずつ減らしていくので、諸侯の上は七であるべきだ、ということである。増注は『荘子』の叙述に従い「七重」が正しい、という。そうかもしれないが、礼には別の規定があったのかもしれない。なので、そのままにしておく。漢文大系・金谷治氏・藤井専英氏はいずれも「七」が正しいと注している。 (注6)集解の盧文弨・王念孫は、楊注を根拠にして「衾」は「食」に変えるべきと言う。なぜならば楊注では「衣は衣衾を謂う、、、衾は錦衾を謂う、、、食は遣車を苞む遣奠を謂う」の構成で注が打たれているのであるが、この「食」に当たる本文がない。楊注の「衾は錦衾を謂う」以下は、もともと注の前文にある「衣衾」の説明であったのだが、誤って本文の「衾」字の説明であるとされて本文が「衾」字に誤られてしまった。このような推測である。盧・王説に従う。 (注7)楊注は、「翣菨」はまさに「翣蔞(しょうりゅう)」に作るべし、と言う。しかし新釈の藤井専英氏は「翣」「菨」は同じ意味であって変える必要はない、と注する。藤井説に従う。翣菨は棺の装飾。 (注8)楊注は、「昏殣は道路の死人を掩(おお)うがごとし」と言う。「殣(きん)」は行き倒れの死人。昼間に葬送せず夕暮れに行き倒れの死人を埋めるように葬らなければならない、と言う意味。「凡緣」については、増注は未詳と言う。楊注は、「凡は常にして緣は因なり、言うはその妻子常服する所のごとく之を埋む」と注する。つまり、罪人の妻子は日常の服装をもって葬る、という意味であるとみなす。ここは楊注に従っておく。 (注9)楊注は、「厭」は「掩」なり、と言う。おおう。 (注10)楊注は、「紸」は読んで「注」となす、と言う。「纊(こう)を注ける」とは、纊(綿)を鼻の下に付けて、それが動くか否かで息を引き取ったかどうかをうかがうことを言う。 (注11)集解の兪樾は、「閔」は「病」なり、と言う。 (注12)楊注は、「䫉」は「象」なり、と言う。䫉は貌と同じで、かたどる。「䫉」字はCJK統合漢字拡張Aにしかない。 |
礼論篇のここから後は、葬喪の礼の意義を論じることに費やされている。孟子は、墨家の夷之(いし)に対して葬礼の意義を説いてこれを論破しようとした(滕文公章句上、五)。荀子が葬喪の礼の意義を執拗に強調することもまた、節葬を主張する墨家を論破することが最大の目的だったはずである。