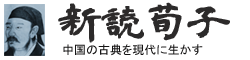|
「お国作りの、労働歌。 いにしえの、聖王たちこそ我が手本。堯(ぎょう)・舜(しゅん)(注1)賢者を尊んで、己は低くへりくだる。 許由(きょゆう)・善巻(ぜんけん)義の人で、王者の利すら欲しがらぬ、その行いはいと高し。 「堯は、賢者に禅譲し、 政治を民のためにした。天下を利して皆愛し、恩徳均しく施した。 上下の身分を区分けして、貴賤の位を規定して、君臣の差を確定す。 「堯は、能ある舜を得て、 帝位をこれに授くなり。舜堯帝とめぐり合い、尚賢・推徳、天下治まる。 たとい賢聖ありとても、時のめぐりが悪ければ、誰にも知られぬこともある。 「堯は、譲りて徳とせず、 舜は譲られ辞退せず。堯は二女をば降嫁させ、舜に政治を一任す。 ああ大人(たいじん)なり帝舜よ、帝位を継ぎて南面し、万物よろしく治めらる。 「舜は、己の天下をば、 有徳の禹(う)へとまた授く。徳を尊び賢を推し、身分秩序を失わず、 罪人の子でも抜擢し、己の子でもひいきせず(注2)、位を賢者に手渡した。 「堯は徳あり、天下のために、 心と力を費やした。干戈(かんか)用いることもなく、三苗(さんびょう)の族服従す。 舜を甽畝(けんぽ)(注3)に見出して、これに天下を一任し、わが身をようやく休ませた。 「后稷(こうしょく)農事をつかさどり、 五穀を豊かに実らせた。夔(き)は楽正(がくせい)に就任し、鳥獣すらも喜んだ。 契(せつ)は司徒(しと)にて民教え、民孝弟を学び取り、有徳の者を尊んだ。 「禹は大功あり、天下から、 洪水のもとを取り除き、民の大害取り去って、邪臣共工(きょうこう)追い出した。 北で九河を切り開き、十二渚(しょ。中州)砕いて流れを通し、三江(注4)もまた鎮まった。 「その禹は、天下を九州に、 分けて国制制定し、我が身を労して苦しんで、天下のために働いた。 益(えき)に皋陶(こうよう)、橫革(こうかく)、直成(ちょくせい)、禹を輔弼した臣なりき。 「契(せつ)玄王の、子は昭明(しょうめい)、 はじめは砥石(しせき)の地にいたが、後に遷って商(しょう)に居す。 十有四世経た末に、生まれた人が天乙(てんいつ)で、これぞ成湯(せいとう)、殷祖なり。 「天乙湯の、業績は、 人材論考抜擢が、すべて道理によく適い、王位はこれまた卞隨(べんずい)と、牟光(むこう)に譲らんと望まれた。 お国の基礎を築くには、これらむかしの賢聖に、拠れば必ずまちがいない。」 (注1)以下、歌に表れる中国の神話的聖王たちとその関係人物について説明する。堯は五帝の一で、いにしえの聖王。舜を見出してこれに二人の娘を与えて王子たちを仕えさせ、政治を一任した。死後、舜に位を禅譲した。舜は五帝の一で、凶悪な父と弟から命を狙われたがこれに耐えて、堯の下で政治を行いその死後に禅譲を受けた聖王。舜もまた、その死後に禹に位を禅譲した。許由・善卷は隠者で、『荘子』譲王篇によると堯は許由に天下を譲ろうとしたが許由は受けず、舜は善卷に天下を譲ろうとしたがやはり善卷は受けなかったという。三苗は、堯舜の時代に長江流域にあった民族。舜がこれを討ち、西方の三危(さんき)の地に追放したという。現代の苗(ミャオ)族の祖先であるという説もある。后稷は棄(き)のことで、堯舜に仕えて農事を担当した。その職名が后稷であり、棄の通称となった。后稷は周王室の祖である。夔は堯舜に仕えて典楽(てんがく)に任じられ、音楽を担当した。契は堯舜に仕えて司徒に任じられ、人民の倫理教化を担当した。契は殷王室の祖であり、玄王を追号された。益は堯舜に仕えて虞(ぐ)に任じられ、山林川沢の管理を担当した。禹とともに治水に当たって功績があり、禹はその死後に益に位を譲ったが、人民が禹の子の啓(けい)に就いたので益は位を啓に譲ったという(孟子萬章章句上、六を参照)。禹は堯舜の時代に治水に失敗して舜によって処刑された鲧(こん)の子で、舜はその子の禹に改めて治水を命じ、禹は中華の土地に水路を引いて洪水を鎮めることに成功した。その功績により、舜は禹に位を禅譲した。禹の後をその子の啓が継いで、世襲の夏王朝が始まった。皋陶は堯舜に仕えて士(し)に任じられ、訴訟・刑罰を担当した。禹は最初皋陶にその位を譲ろうとしたが、皋陶は先に死んでしまった。共工は堯に仕えていたが堯に嫌われ、北辺の幽州に追放された。橫革・直成(真窺)は『呂氏春秋』に表れる禹を補佐した人物であるが、詳細不明。成湯(湯)は契の子孫で、名は乙(いつ)。歌では天乙とされている。夏王朝の桀を倒して殷王朝の開祖となった。昭明は、契の子。卞隨・牟光について、楊注は『荘子』譲王篇の「湯は天下を卞隨・務光に譲るも、二人受けず。皆投水して死す」を挙げて、「牟」と「務」は同じ、と言う。すなわち卞隨・牟光(務光)は、湯が禅譲しようとしたがこれを受けずに入水自殺した人物という。
(注2)原文読み下し「外に仇を避けず、內に親に阿らず」。上に書いたとおり禹は舜によって処刑された鲧(こん)の子であったが、舜はこれを抜擢して治水を行わせた。舜には子の商均(しょうきん)がいたが愚か者であり、その死後、位は禹に禅譲した。 (注3)孟子に、「舜は畎畒の中より発す」(告子章句下、十五)とある。「甽」は「畎」の古字。畎畒とは田のみぞとうねのことで、卑賤な農夫の身分を指す用語。 (注4)増注は韋昭を引いて、松江・銭塘江・浦陽江と言う。新釈は明確でないと言う。 |
| 《読み下し》 請う相(そう)を成して、聖王に道(よ)らん、堯舜賢を尚(とうと)び身辭讓(じじょう)し、許由(きょゆう)・善卷(ぜんけん)、義を重んじ利を輕んじ、行顯明(けんめい)なり。 堯賢に讓りて、以て民の爲にし、氾利(はんり)・兼愛(けんあい)德施(とくし)均(ひと)しく、上下を辨治して、貴賤等有り、君臣を明(あきら)かにす。 堯は能に授け、舜は時に遇い、賢を尚び德を推して天下治まる、賢聖有りと雖も、適(たまたま)世に遇わずんば、孰(たれ)か之を知らん。 堯德とせず、舜辭せず、妻(めあ)わすに二女を以てし任ずるに事を以てす、大人(たいじん)なる哉(かな)舜や、南面して立ちて、萬物備わる。 舜禹に授くるに、天下を以てし、得を尚び賢を推して序を失わず、外に仇を避けず、內に親(しん)に阿(おもね)らず、賢者に予(あた)う。 [禹]心力を勞し(注5)、堯德有り、干戈(かんか)用いずして三苗(さんびょう)服し、舜を甽畝(けんぽ)に舉(あ)げ、之に天下を任じて、身休息す。 后稷(こうしょく)を得て、五穀殖(しょく)し、夔(き)樂正(がくせい)と爲りて鳥獸服し、契(せつ)司徒と爲りて、民孝弟を知り、有德を尊ぶ。 禹功有り、鴻(こう)を抑下し、民害を辟除(へきじょ)して共工(きょうこう)を逐い、北九河を決し、十二渚(しょ)を通じ、三江を疏(そ)す。 禹土を傅(し)きて(注6)、天下を平かにし、躬(み)親(みず)から民の爲にして勞苦を行い、益(えき)・皋陶(こうよう)、橫革(こうかく)・直成(ちょくせい)(注7)を得て、輔と爲す(注8)。 契玄王(せつげんおう)、昭明(せいめい)を生ず、砥石(しせき)に居り商(しょう)に遷る、十有四世にして、乃ち天乙(てんいつ)有り、是れ成湯(せいとう)なり。 天乙湯(てんいつとう)、論舉(ろんきょ)當(あた)り、身卞隨(べんずい)と牟光(ぼうこう)とに讓る、古賢聖に道(よ)れば、基必ず張る(注9)。 《原文》 ※[]内は原文にある字を削る。 (注5)原文「禹勞心力」。一字余分であり、荻生徂徠を引く増注、および王引之を引く集解は、「心」字を削るべきと言う。新釈の藤井専英氏は劉師培の説を採用して、「禹」字を削る。言うは、この句は「堯有德、勞心力(堯は徳有りて、心力を労す)」が本来の形で、後の「禹傅土、平天下」と対文となるべきものである。この一行はもっぱら堯舜の功績を述べたものであって禹は関係がないので、新釈の解釈は有力であると考える。
(注6)楊注は、「傅」は読んで「敷」となす、と言う。しく。 (注7)増注の久保愛、集解の盧文弨はともに『呂氏春秋』の「陶・化益・真窺・横革・之交の五人を得て、禹を佐(たす)く」を引いて、化益は伯益のことであり、真窺は直成のことである、と言う。これで正しいと思われる。ただし、直成(真窺)・横革は禹に仕えた人物であることは確かであるが、その事績はよく分からない。 (注8)集解の王念孫は、一字を脱す、と言う。藤井専英氏は、「為(爲)」は「之交」の脱字と転訛である可能性を挙げる。之交は上の呂氏春秋において禹に仕えた家臣の一人である。 (注9)猪飼補注は、四字を脱する、と注する。確かに、最後の行は四字少ない。だが、それらの字を推測する術はない。もしかしたら最後の行を破格にして一句少なくした技巧であるのかもしれず、このままでも押韻的には歌は成立している。 |
第三歌は、堯・舜・禹・湯王の聖王たちの業績を称えた中華文明建国の叙事詩となっている。述べられているエピソードはほぼ孟子や史記のものと同じであるが、この歌では『荘子』に表れる隠者たちもまた有徳の者として称えられているところが違っている。しかし荀子が『荘子』に描かれているような隠者を、どうして称えたのであろうか。堯・舜・湯といった聖王たちが己の位に固執せず、有徳の者に後を継がせようと望んでいたことを強調するために、道家が称える隠者たちにご登場いただいたのであろうか。正論篇で検討したように荀子は世襲を肯定せず有徳有能の者が君主の座に就くことを正義とするので、この歌ではひたすら禅譲伝説を強調したのかもしれない。しかしそこで隠者たちを出したのは、まずかったのではないか。隠者たちは君主の位を欲しいとは思わなかったので辞退したのであるが、君主の位は富貴の頂点であって誰もが欲しがる地位である、ということは荀子の統治論の要にあって、ゆえに墨子を批判したのではなかったのであろうか。隠者たちの存在は、宋鈃(そうけい)の人間寡欲説に有利であって、荀子の性悪説に不利な反証となるであろう。
いにしえの黄金時代の神話を後世の人間のための模範として信じるのが、儒家のスタンスであった。聖王たちの偉大な政治も、堯舜の禅譲伝説も、もとより神話にすぎない。しかし後世の儒家は、これらを政治の理想として真剣に論じたのであった。一方わが日本では、中華文明のように神話時代の登場人物を倫理的模範として尊重する文化は成立しなかった。アマテラスオオミカミや神武天皇を神社に祀ることはするが、彼らの生きざまや統治方法が後世の模範とはならなかった。よってわが国の倫理的模範のあり方は、中国やインドから輸入した形を採用するのが常であった。模範的人間像の最古の起源は、釈迦や孔子のような外国人に求められることになった。