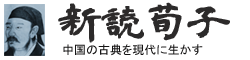孟子は、「人間が学ぶことができるのは、その『性』が善だからである」と言う。これに答えよう、「そうではない。この説は人間の『性』を理解できておらず、人間の『性』と『偽(い)』の区分を洞察していないのである」と。およそ「性」というものは、天が与えて作ったものである。これを学ぶことも、成し遂げることもできない。いっぽう礼義というものは聖人が作ったものであり、人が学んで身に付けることができて、成し遂げることができるものである。学ぶことも成し遂げることもできないが人が属性として持っているもの、これを「性」と言うのである。学んで身に付けることができて成し遂げることができるもので、人が属性として持っているもの、これを「偽」と言うのである。これが、「性」「偽」の区分である。いま人の「性」について見ると、目は対象を見ることができて耳は対象を聴くことができる。目の視覚能力は目と離して取り出すことはできず、耳の聴覚能力は耳と離して取り出すことはできない。目は生得的に視覚能力を持ち、耳は生得的に聴覚能力を持つ。これらが学んで得るようなものではないことは、明らかである。孟子は、「本来人間の『性』は善なのであるが、人々はその『性』を喪失してしまうのだ」と言う(注1)。これに答えよう、「そう考えるのであれば、それは誤りである。人間の『性』は、生まれた時点の素朴な身体の素材から時とともに離れていって、成り行きのままでいけば必ず生まれた直後の無欲な状態を喪失するものである。これを見るならば、人間の『性』が悪であることは明白である」と。いわゆる「性善説」とは、人間がその素朴な状態から離れずにいることを美しいと考え、素材のままの状態から離れずにいることを有益と考える主張である。つまり、目の視覚能力が目と離して取り出すことができず、耳の聴覚能力が耳と離して取り出すことができず、したがって目は生得的に視覚能力を持ち、耳は生得的に聴覚能力を持つのであるが、人間の善もまたこれら視覚と聴覚のように天与の属性であると考えるのが、「性善説」なのである。しかし人間の「性」は、空腹ならば飢えを感じ、腹いっぱい食べたいと欲するものであり、寒ければ暖かくなりたいと欲するものであり、疲れたならば休むことを欲するものである。しかしいま人が飢えを感じていても、年長者がいたならばこれに譲ってあえて先に食べようとはしない。これはどうしてかといえば、謙譲の意志を持つからである。また疲れているのに年長者がいたならばあえて休もうとしないのは、目下が仕事を代わらなければならないという意志を持つからである。子が父に譲り、弟が兄に譲り、子が父の代わりに汗を流し、弟が兄の代わりに汗を流す。これらの行為は、すべて「性」に反して「情」にさからう行為ではないか。だがここにこそ孝子の道があり、礼義の規則があるのだ。ゆえに、「情」「性」に従えば、人間は謙譲をしない。逆に謙譲をするのは、「情」「性」にさからっている。これを見れば、人間の「性」が悪であることは明確であり、人間の善は「偽」の結果なのである。
(注1)人間が本来の性善を欲心によって失う、というテーマは『孟子』告子章句上篇で繰り返し表される。たとえば孟子告子章句上八、九、十五など。
|
《原文・読み下し》
孟子曰く、人の學ぶ者は其の性善なればなり、と。曰く、是れ然らず、是れ人の性を知るに及ばずして、人の性・僞(い)の分を察せざる者なり。凡そ性なる者は、天の就せるなり、學ぶ可からず、事とす可からず。禮義なる者は、聖人の生ずる所なり、人の學んで能くする所、事として成る所の者なり。學ぶ可らず、事とす可からずして、而(しか)も人に在る者は、之を性と謂う。學んで能くす可く、事として成る可きの人に在る者は、之を僞と謂う。是れ性・僞の分なり。今人の性、目は以て見る可く、耳は以て聽く可し。夫の以て見る可きの明は目と離れず、以て聽く可きの聰は耳と離れずして、目は明にして耳は聰なり。學ぶ可からざること明(あきら)かなり。孟子曰く、今人の性は善なり、將(は)た皆其の性を失喪するが故なり、と。曰く、是(かく)の若くんば則ち過(あやま)てり。今人の性、生れて其の朴を離れ、其の資を離れ、必ず失いて之を喪す。此を用(もっ)て之を觀る、然れば則ち人の性の惡なること明かなり。所謂性善とは、其の朴を離れずして之を美とし、其の資を離れずして之を利とするなり。夫の資朴の美に於ける、心意の善に於けるをして、夫の以て見る可きの明は目を離れず、以て聽く可きの聰は耳を離れず、故に目は明にして耳は聰なりと曰うが若くならしむるなり。今人の性は、飢えて飽かんことを欲し、寒くして煖ならんと欲し、勞して休まんことを欲するは、此れ人の情性なり。今人飢うるも長を見れば敢て先ず食せざる者は、將(まさ)に讓る所有らんとすればなり。勞して敢て息(そく)を求めざる者は、將に代る所有らんとすればなり。夫れ子の父に讓り、弟の兄に讓り、子の父に代り、弟の兄に代る、此の二行なる者は、皆性に反して情に悖(もと)るなり。然り而(しこう)して孝子の道、禮義の文理なり。故に情性に順(したが)えば則ち辭讓せず、辭讓すれば則ち情性に悖る。此を用って之を觀る、然れば則ち人の性惡なること明かなり、其の善なる者は僞なり。
|
性悪説の宣言が行われた後に、孟子の性善説への批判が続く。『孟子』テキストの中で「性善」の議論が集中的に表れるのは、告子章句上篇である。告子章句上篇は荀子の叙述のように段階を追った論理的なものではなく、個別の問答を連ねた印象批評的である。その中でも一番組織立った叙述としては、同篇の六を挙げてよいであろう。
弟子の公都子が言った、
公都子「告子(こくし。注)は、『性』には善も不善もないと言います。またある人は、『性』は善をなすこともできれば不善をなすこともできると言います。だから周代において、文王・武王が立てば人民は善を好むようになり、幽王・厲王が立てば人民はデタラメを好むようになったと言うのです。また別のある人は、『性』が善の人もあれば『性』が不善の人もあると言います。だから堯舜が統治する時代においてすら象(しょう)のような輩が現れ、瞽瞍(こそう)のような者が父親でありながら舜が現れた。また殷の紂王が甥であって君主でありながら、微子啓(びしけい)や王子比干(おうじひかん)が現れたと言うのです。今、先生は『性善説』を唱えています。ならば、彼らの言うことはことごとく誤りだということなのでしょうか?」
(注)告子は『孟子』書中で表れる論述家。『孟子』の記録によれば、人間の「性」は善でも不善でもないと主張したと言う。
孟子「だいたい、人間の『性』『情』というものは、本来善をなすことができるものなのだ。このことを、いわゆる『善』と定義しているのだ。もし不善をなす者がいたとしても、それは人間本来の資質の罪ではない。惻隠・羞悪・恭敬・是非の心は、人が皆持っている。惻隠の心は仁に、羞悪の心は義に、恭敬の心は礼に、是非の心は智につながる。だから仁・義・礼・智は、外から我に鍍金(めっき)したものではなくて、我固有のものなのだ。(不善なのは、)ただただそれらを思うまでに至らないだけのことなのだ。だから求めれば得られるし、捨てれば失う。そうやって善と不善が何倍にも隔たって比較もできない差ができるのは、自らの資質を尽さないからなのだ。詩経にこうある、
天は、もろもろの民を生ぜしめた
万物には、必ず法則がある
それゆえ民が正常なるときには
この至高の徳を好むだろう
(大雅『蒸民』より)
と。孔子は『この詩を作った者は、道をよく知る者だ』と言った。だから万物には必ず法則があって、人民が正常であるならば、仁・義・礼・智の至高の徳を好むはずなのだ。」
上の引用でアンダーラインをしたところは、
孟子公孫丑章句上、六で現れるいわゆる「四端説」である。孟子は、人間が普遍的に生得している心中の善なる衝動として、惻隠・羞悪・恭敬(公孫丑章句上六では「辞譲」)・是非の四つの端(たん。はじまり)があると言う。その「端」は可能性としての善であり、それを現実的な善である仁・義・礼・智の徳に発展させるのは、各人の努力次第である。孟子は「堯・舜は之を性のままにす」(
盡心章句上、三十)と言う。堯・舜が聖人として天下の王者となったのは、彼らは「性」である四端をそのまま保持して伸ばしたからであり、そのところに聖人の偉大さがあったのだ、と主張する。よって孟子は「人はだれでも堯・舜になれる」(
告子章句下、二)と主張したのである。以上が、孟子の性善説の組み立てであった。
孟子の性善説を正名篇(1)の荀子の定義に沿って整理するならば、おそらく孟子は「四端」が人間の「情」レベルの衝動であって、荀子の定義で言う「慮」の判断を待たずに行われるものであり、ゆえに生得的な「性」に属するものである、と考えているはずである。「四端」の一つである「惻隠」について言えば、公孫丑章句、六の以下の叙述がそれを説明している。
人間が誰でも他の人間に対して放っておけない心があるという理由は、こういうことだ。
今、ちっちゃい子供が井戸に落ちかけていたとする。これを見たらどう行動するか?誰でもこれはいかん!とあせってかわいそうだ!と思って助けるだろう。その瞬間、これをネタに子供の父親母親に取り入ってやろう、などとと考えないだろう。地元の英雄になって友達から賞賛されたい、などと考えないだろう。見殺しにした薄情者めと悪名を受けるのはいやだ、などと考えないだろう。こうやって考えれば、惻隠の心(かわいそうだ、と思う心)がないのは、人間でない。
孟子が「惻隠」を「慮」の判断を待たずに行われるものである、と考えているだろうことは、上の説明によって理解できるだろう。しかし他の三つ「羞悪」「恭敬(辞譲)」「是非」について、孟子は説明を省略している。
類推するならば、「羞悪」は「惻隠」と同様の説明を加えることが可能であろう。「是非」は正名篇(1)の荀子の定義に沿えば、「知」を指していると考えることができる。「知」はすなわち人間の認知能力であり、心中の「慮」を発動させる生得的能力であろう。荀子はこの「慮」を人間の「情」を制御する機能と位置づけて、「偽(い)」の範疇に入れている。孟子は「是非」を「性」に属するものである、と主張するのであるが、これを荀子の定義に沿って言うならば「是非」は「情」の衝動のレベルにおいて起こらなければならないことになるだろう。孟子は人間には生得的な「良知」「良能」があると言う(盡心章句上、十五)。荀子は「知」・「能」が人間の生得的な認知能力および行為能力であることを定義するが、これらを「性」のそのままの発露である「情」から区別して「偽」を成立させる要因とみなすのである。
さらに困難なのは、孟子の「恭敬(辞譲)」である。これも「四端」の一である以上、「慮」のはたらきを得ずして行われる「情」レベルの衝動でなければならない。しかしこれは、直観的にいってもありえそうにない。目上の人間を謹んで敬い、辞して譲る精神は中国や日本の文化ならば確かにあるが、いざ西洋諸国のような異文化の中に入るならば、ほとんど消えてしまう。よって「恭敬(辞譲)」は人間の生得的な感情ではありえず、単なる東アジア世界固有の文化的な作為であるはずだ。これに対して孟子は、人間は幼児の頃に両親を慕うが、成長すると親のことを構うことがなくなる、といったことを言及する(萬章章句上、一)。だから「赤子の心を失わない」(離婁章句下、十二)ならば「恭敬(辞譲)」の「性」を成長しても保ち続けることができる、と孟子ならば言うであろう。しかし幼児の時期に両親を慕うのは、両親への「恭敬(辞譲)」であろうか?もっと言えば、「恭敬(辞譲)」は両親に対してだけでなく、家族の年長者やコミュニティーの年長者にまで発露すべき善なのであるが、幼児が親からのしつけもなしに自発的にこれらを慕って譲ることなどは、幼児を実際に観察してみればあるはずがない。幼児が両親を慕うのは、単に最も近しい保護者であるから依存するのであり、自己保存の欲求のレベルであると考えたほうがよい。その依存する親からの命令であるから、幼児ですら次第にルールをしつけられていくのである。よって、「恭敬(辞譲)」に関しては、孟子の性善説は全く正当化できないと私は考える。そして荀子が彼の性悪説において「偽(い)」の範疇として最重視するのが、この「恭敬(辞譲)」を明文化した社会的ルール、すなわち「礼法」なのである。こと「恭敬(辞譲)」に関しては、荀子の主張が完く正しい。
孟子と荀子の「性」の相違点をまとめると、下の表となるだろうか。孟子と荀子は、「性」に含める内容が異なっている。なので、潜在的「性」と顕在的「性」に分類してみた。両者の性善説・性悪説の差は、このうち顕在的「性」に対する見解の相違となっているはずである。
|
生得的に持つ潜在的能力
(潜在的「性」) |
生得的に行う顕在的行為
(顕在的「性」) |
後天的に獲得すべき高次の能力 |
| 孟 子 |
四端(惻隠・羞悪・恭敬[辞譲]・是非)(※)
|
四端から表れる衝動的な善行為=性善説(※) |
仁・義・礼・智 |
| 荀 子 |
情・知・能 |
情(慮を働かせず知・能を発現させない利己的行為)=性悪説 |
偽(慮を働かせて情を選択し、知・能を積み重ねて得られる成果) |
(※)ただし、孟子は耳目の欲、すなわち荀子の定義で言えば「情」もまた、定義上は人間の「性」のうちに入っていると考えているはずである。
告子章句上、十五「耳や目の感覚器官は何も意思を持たないから、外物からの刺激になすがままに覆われる。感覚器官が外物と交流すれば、引き付けられざるをえないのだ。しかし心の器官は、意思を持っている。だから、意思をすれば正しい心を得られるし、意思しなければ正しい心を得られないのだ。人の体は、天が我々に与えたものだ。しかしまずその大事な箇所(原文、「大者」)をしっかりと働かせれば、つまらない箇所(原文、「小者」)がそれをだめにすることもできなくなるのだ。」ここにおいて孟子は人間の身体には「小者」と「大者」があり、「大者」を働かせれば善の行為をなす大人となって「小者」に任せれば欲に負けた小人となる、と言うのである。したがって孟子の性善説は人間の生得的能力が全て「善」であると言っているわけではなくて、人間の生得的能力には「善」が含まれているという主張なのであり、荀子は孟子の言うその「善」は後天的学習であって生得的ではない、と対立するのである。
上の表において、右端の列については孟子も荀子もほとんど変わるところがない。最大の相違点は中央の列であって、人間には生得的に善を行う衝動があるか否か、という点で孟子と荀子は別れている。江戸時代中期に活動して日本儒学に画期的業績を残した伊藤仁斎(寛永四年、1627 – 宝永二年、1705)は、朱子学から距離を置いて『論語』『孟子』の二書の古義を学ぶべしと提唱して古義学派の開祖となった。その仁斎は初学者用の入門書である『童子問』(元禄四年、1691に第一稿本完成)において、孟子の性善説を推奨した。その理由は、上表でいえば中央の列にある人間の生得的な善への能力を指摘することが、学ぶ者に教育的効果をもたらすことを期待するからである。
孟子が、性は本来善であるという説を主張するのも、ただその理由を明らかにしようとするばかりではなく、人びとにその性は本来善であることを知らせ、その性を拡大充実させようと望んだからである、、、性は本来善であるという説は、仁義の心が自己に固有のものであることを明らかにしようとする説であるが、その実は、自暴自棄の者(自からの性を害しすてさろうとする者)のために考えだされたものである。
(伊藤仁斎『童子問』第十五章より、貝塚茂樹現代語訳)
仁斎は、学ぶ個人の教育的効果ゆえに孟子の性善説を取る。だが荀子は、人間は利己的な行動を行うのが本来であって国家がこれに礼法を適用して制御するのであるという社会契約説に立つために、性悪説を取るのである。仁斎の後に続いた荻生徂徠(寛文六年、1666 – 享保十三年、1728)は、仁斎と孟子を批判して、荀子をむしろより高く評価した。徂徠は、仁斎とは学問の主眼点を違うところに置いていた。仁斎の学は個人の倫理を学ぶ道であり、徂徠の学は国家の政治経済を学ぶ道であった。徂徠が荀子を評価したのは、彼の学問と荀子とが方向を一にしていたからであった(ただし、徂徠は荀子を全面的に賞賛したわけではない)。
孟子と荀子の説を、ここまでに整理した。上の表における中央の列の荀子の主張について、それが妥当であるか否かをさらに読み進んでいきたい。人間の「性」には、他者と良好な関係を結ぶ能力が本当にないのであろうか?