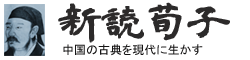五、論語学而篇はどのように編集されたのであろうか?
武内先生の説を(仮に)採用して、学而篇を論語二十篇の中で比較的遅くに成立した章であり、斉スクールと魯スクールとの和解総合の結果、記念的著作として整理された篇と考えてみよう。
加えて、私はここに孟子の魏遊説の成果として、子夏を源流とする魏スクールとの和解総合も学而篇で意図されていた、と想像してみたい。
学而篇は、ランダムな語録の寄せ集めであるのか、それとも編集者の意図があるのだろうか。
朱子は、簡単に言う。
此れ書の首篇爲り。故に記する所、本を務むるの意多し。乃ち道に入るの門、德を積むの基にして、學者の先務なり。
また武内義雄先生は、『論語之研究』でこう言われる。
学而篇は凡そ十六章から成って居て、その第一章と末章が前後相照応し、毎章の順序にも脈絡相貫通して一定の意図のもとに編集されたもののように見える。(pp232)
私は、朱子や武内先生とは少し違って、まずは学而篇の形式的な構成に注目したい。
すなわち、「子曰」で始まる孔子の言葉に挟まれて、弟子たちの言葉があることが分かる。
子曰
有子曰
子曰
曾子曰
子曰
子曰
子夏曰
子曰
曾子曰
子禽問於子貢曰
子曰
有子曰
有子曰
子曰
子貢曰
子曰
里仁篇のように孔子のモノローグの連続ではなく、顔淵篇のように孔子と他者との問答がひた押しに続くがごとき、固定した形式ではない。学而篇は、孔子の言葉と弟子の言葉が交互に飛び交う、生き生きとしたリズムが保たれている。
曾子・子夏・子貢は、孔子死後に三つの国で一家を成した、独立した論者である。彼らの言葉が独立した格言として置かれるべき価値は、孟子の時代のようなはるかな後世から見れば、十分にある。そして、そのようなやがて大家を為した弟子たちのさらなる師の孔子は、ますます偉大な師なのである。
中間の第十章「子禽問於子貢曰」の章が、リズム的に特異である。
思うに、この章は子貢が第三者と語った、間接的な孔子の賛歌であろうか。
斉スクールの源流として最も尊重された子貢が、孔子のことを「温・良・恭・倹」の徳を以って仰ぐばかりであり、その真意を知るには至らない。
中間にこの章を挟むことによって、末尾直前の孔子による子貢への称賛の言葉が、より味わいを帯びて来るだろう。子貢は、やはり孔門の賢者であり、孔子のよき弟子であった。
この学而篇が編纂された現場は孔子や弟子たちの生きた時代より、はるかな後世である。そしてその時期には、孔子死後に各国で分裂した各スクールの確執が、時代の果てにようやく乗り越えられた後のことであっただろう。ようやくこの学而篇において、かつての派閥間のわだかまりを超えて、子貢を孔子の高弟として正当に称賛できるようになった。
この「子禽問於子貢曰」の章の後に、孔子の言葉で「三年父の道を改むることなきを、孝と謂うべし」の章が置かれている。
この言葉は、孔門としておそらくありふれた格言に過ぎなかったであろう。早くから両親と死別して親の顔を知らずに大人となった、孔子である。彼がこんな言葉を言ったところで、そこにはいっさいのリアリティがない。この言葉を重視して後世に伝えたのは、実際に親子二代で孔子の弟子となり、目上の者に対する愛憎を感じながら大人となっていった、曾子のしわざであっただろう。いっぱんに、『論語』においてこの章のような誰が言っても成立するような具体的背景を欠いた格言は、孔子の創作した言葉であるはずがなくて、当時のごくありふれた格言を孔子に仮託したものであると考えたほうがよい。
だが、この言葉を学而篇で子貢の言葉の後に置いたことには、もう一つの隠された意図がなかっただろうか。
孟子の報告によると、子貢は孔子の死後、三年の喪を行い、他の弟子たちが去って行った後にまだ足りずに自発的にさらに三年の喪に服したという(滕文公章句上篇第四章)。
もとより、子貢は孔子の子ではない。
なのに、子貢は師の偉大さを追慕して、義務などに御構いなしに六年の喪に服した。これこそ、儒家の言う「孝」の真髄ではないか。孝は、形式が本質ではない。追慕する心情を形とすることであり、それに尽きるはずではなかったろうか?
後世、三年の喪が形式的な儀式に堕落し、形式的だから省略したほうがよいという主張が現れた。すでに孔子時代に宰我が主張し、儒家から分かれた墨家は、さらにラディカルに薄葬を主張して、死者のために生者の富を浪費するな、死者を葬る労働を省いて生きた人間を救え、と唱えた。このような後世の時代において、子貢が孔子に捧げた精神の意義を、もう一度問い直そうではないか。
私は、二つの章の配列には、後世の儒家の思想再確認の意図があったのではなかったか、と想像する。加えて、斉スクールの源流であった子貢に対して、魯スクールが強調する「孝」の高度な実践者としての側面を再確認して、魯スクールにとっても受け入れられる子貢の姿を取り戻した、とも言えるのではないだろうか。こうして、斉スクールの源流の子貢を魯スクールに取り込む形で、両派の総合は成り立った。付け加えるならば、学而篇で子貢は独白をしない。第十章で第三者と対話して孔子の計り知れぬ偉大さを示唆し、そして末尾一つ前の章で孔子と問答して共に学問を讃える。あくまでも孔門全体を慮った孔子の高弟・子貢であり、派閥の源流として自己主張する儒家思想の後継者・子貢ではない。
次に、曾子の第一の言と、子夏の言は、両者を源流として奉ずるスクールから、取っておきのエッセンスとして提出されたものかもしれない。
そして、それぞれに続く孔子の言もまた、それぞれのスクールの末裔が撰じた格言なのかもしれぬ。
子夏の言と、続く孔子の言は、子張篇に見られる子夏の言葉とその趣意がよく一致しているように思われる。孔子の言は、おそらく複数の格言の集合であろう。
また、曾子の第二の言である第九章は、もしかしたらその言が暗喩する対象は、孔子なのかもしれない。
遠くに去った孔子を追慕すれば、天下の民をいずれ治める理想の世がやって来るだろう。おそらく、学而篇の編集をリードしたのは、孟子以降の魯スクールであっただろう。編者は、彼らの源流である曾子の言をここにおいて、自分たちの道がきっと正しいことを、確かめる言葉としたのかもしれぬ。
しかしながら、有若の三つの言葉は、私にとっていまだに説き難い。
有若の三つの言葉はいずれも儒家のセオレティカルな議論であるが、ここで断片的に採用されても正直言って説得力が薄いように見える。
有若は、魯スクールの源流の一人である。
ゆえに、この学而篇でのみ「有子」と尊称されているのであろう。それは分かる。
この篇は、編集が成った後で各地の儒家スクールに持ち帰り、暗誦に用いられたことであろう。初学者から上達者に至るまで、儒家のエッセンスが込められるべく言葉が磨かれたに違いない。
今は、魯スクールの有力者であった有若の言をもって儒家の理論的骨子を与え、入門の言葉とした、と私は仮に解しておきたい。初学者は別に理解できなくとも、後で上達して理解できればよく、最初は言葉だけ覚えておけばよい。そのため、わざと高度な理論を断片的に置いたと考えるのも、よいかもしれぬ。内容を理解できなくとも般若心経を音だけで覚えるのを仏教の入門とする勉強方法と、同様なものか。この点は、いずれ真意を考えてみたい。
有若の言葉に続く孔子の言葉のうち最初の言葉「巧言令色云々」は、確かに言語だけで君子の道を理解しようとする傾向への戒めとして置かれたのかもしれない。この言葉もまた、孔門ではありふれた格言であったろう。
後半の有若の二言に続く孔子の言葉もまた、言に慎み、ひたむきに努力することが君子の道であると説き、机上の学問に終始することを戒めた言葉となっている。有若の言がいずれもセオレティカルな議論の断片であることと、鋭い対比を為している。私は何も有若への当てこすりとして孔子の言が置かれたというよりは、理論も重要でありかつ理論だけが重要ではない、という儒家の教育の真髄がまた、有若と孔子の言葉を続けて挙げていることの意味であろうか、と仮に想像してみる。
ともあれ、学而篇においてついに有若の言が採用されたことは、魯スクールによって彼が復権されたことを記念していたのかもしれない、と私は仮に想像してみよう。
『孟子』や史記仲尼弟子列伝の記事によると、有若は孔子の死後に弟子たちによって一旦後継者に祭り上げられて、後に失脚したそうである(注)。
しかし魯スクールに学んだ孟子がその公孫丑章句上篇第一章と第二章において、斉スクールで学んだであろう弟子の公孫丑の主張を一々斥けたことは、すでに述べた。その孟子は、くだんの章において自らの長大な発言の末尾において、有若の言葉による孔子賛歌を取り上げている。その孔子賛歌はあまりに誇大に過ぎる感が読後に否めないが、ともかくも孟子はここでそれまで儒家によって沈黙されていた有若を、宰我・子貢と並んで「智は以て聖人を知るに足る」と評した。
この宰我・子貢は、論語先進篇において言及される、言語に秀でる孔門十哲の二人である。そして武内先生の類推によれば、この先進篇は斉論語七篇の一であり、斉スクールの伝承する語録であったという。
孟子は、斉スクールで学んだ弟子の公孫丑の前で、彼らが最も評価する宰我と子貢に、魯スクールの有若を対等的に並列させたのである。これは、魯スクールが主導権を取って斉スクールと和解総合すべき方針を、宣言したものであると言えなくもないであろうか?
さて、学而篇の冒頭を飾る、古今に著名な格言について考えたい。
私は、この格言が必ずしも孔子自身の言葉であったかどうかは、分からないと思う。
この格言の最後の文はともあれ、一つ目と二つ目の文は、論語の他の箇所に類似した言葉が、どうも見当たらない。「温故知新」(為政篇)「徳孤ならず」(里仁篇)「これを知る者はこれを好むものに如かず」(雍也篇)などは近いが、しかし学問と友を得ることの喜びを謳歌したこの学而篇冒頭の二文は印象的であり、かつ論語全体で孤立しているように見られる。
私はむしろ、学而篇第一章は孔子自身の言葉であったかどうかは問題でなく、むしろ孔門に集まった同学たちにとって、常に明記すべき座右の銘であったと言った方が、適切ではなかったろうか、と思いたい。毎日の同学たちの合言葉であって、孔子の言葉としては意識されていなかったので、論語の他の伝承には見当たらない。それを今学而篇を編むに当たって、孔門が伝承すべき言葉の筆頭に、孔子の言葉として置いたのではないだろうか、と考えてみたいのである。
それほどにこの冒頭の言は完成されており、暗誦に容易で、洗練されている。時間をかけて磨き上げられた、孔門の合言葉的な格言であったであろう、と想像してみたい。学而篇はこの言葉から初め、自分たちが学を志す同志であることを確かめた。その調子は自信に満ち、学を志す者に明るい展望を開き、励ましているようだ。
冒頭の言葉の後、有子、曾子、子夏、再び曾子、子貢、有子の言葉が続き、それぞれの言葉の間に孔子の言葉が挟まる。これは各々一家を成した弟子たちと、彼らのさらに源に立つ孔子との間との間で交わされた、仮想的な議論の姿を再現したようではないか。これが里仁篇のように孔子の言葉だけで埋め尽くされていたならば、印象はどうであったろうか。顔淵篇のように孔子がもっぱら至らぬ弟子や諸侯を教え諭す老婆的教師像に終始していたならば、どれほどの印象を与えたであろうか。学而篇が生き生きとして読者に映るのは、すでに一家を成した弟子たちの自信に満ちた格言と、彼らの師である孔子の高次の対決とが緊張感を持って続けられる、そんなところにあると私は勝手な一読者として、感想を持つのである。
末尾一つ前の章は、子貢と孔子との問答である。おそらくこれは子貢を信奉する徒にとって、子貢を讃えた、取っておきの問答であっただろう。
これまで(子貢と子禽との問答を除いて)各弟子の独言が続いた最後に、師と弟子との問答が置かれる。これは、学而篇の中で各人が入れ違いに登場しては議論を進めて来た軌跡の、総合である。この章で初めて、師と弟子が一章の中で対話する。その結論は、周知のとおり「切磋琢磨」すべきということであり、孔子が子貢の聡明を褒めた言挙げである。
学而篇末尾一つ前の章は、その冒頭の章と見事に対を成している。
孔門に入り、共に学を目指すことの喜びの姿が、冒頭に続いて再びリフレインされているのである。
最後に登場する弟子が、学而篇のこれまでの章のごとく独言ではなくて、孔子との対話を行っていることは、きっと偶然ではない。弟子たちと孔子の独言が続いて緊張した果てに、弟子と孔子との問答が置かれる。その結果は論語の他篇を埋め尽くすような訓戒ではなく、学の上達への称賛である。緊張の果てにカタルシスとして子貢と孔子のとっておきの対話を置いた編者の文学的手腕は、絶妙である。しかしこれもまた、魯スクールと斉スクールとが和解総合された結果として、子貢を派閥の歪みなく評価できる道が開けたゆえに収録することができたと、言えはしないだろうか?
孔子と子貢との明るい問答が終わった後に、全ての弟子たちの師である孔子の最後の言葉が置かれる。この学而篇最終章もまた、冒頭の章の第三文「人知らずして云々」と対になっていることは、私が読むに明らかに見える。これまで大家を為した弟子たちとの仮想の問答をくぐり抜けて、彼らの成長を確かめた後に、孔子が静かに一場の塾を閉じる言葉を告げているかのようはないか。
-二三子、よくぞ各々が各国で大家を為した。しかし、吾が門の理想への探求の道は、まだまだ遠いぞ。さらに切磋琢磨して、吾が身を省み、食飽かんことを求めず、己が人を知らざるを患えよ。
この学而篇を諳んじる後世の儒家たちへの、教訓をもって一篇がここに終わる。諳んじる者は、さらに繰り返して、冒頭の章に向かうだろう。そして再び、学ぶことの説(よろこ)びと学友を得ることの楽しみを、孔子と高弟たちの言葉から追体験するであろう。
(注)
原文:
孔子既沒,弟子思慕,有若狀似孔子,弟子相與共立為師,師之如夫子時也。他日,弟子進問曰:“昔夫子當行,使弟子持雨具,已而果雨。弟子問曰:‘夫子何以知之?’夫子曰:‘《詩》不云乎?“月離于畢,俾滂沱矣。”昨暮月不宿畢乎?’他日,月宿畢,竟不雨。商瞿年長無子,其母為取室。孔子使之齊,瞿母請之。孔子曰:‘無憂,瞿年四十后當有五丈夫子。’已而果然。問夫子何以知此?”有若默然無以應。弟子起曰:“有子避之,此非子之座也!”
試訳:
孔子の没後、弟子たちが彼を思慕して、有若の状(すがた)が孔子に似ていたため、弟子たちは相共に彼を立てて師事した。師事するに、孔子先生に仕えたように行った。後日、弟子(の一人)が進み出て有若に質問した。
「昔、先生は外出しようとなされたとき、弟子に雨具を持参させました。結果、本当に雨が降りました。弟子が問いました。『先生、どうして雨が降ることが分かったのですか?』と。先生は答えました。『詩経に、「月畢(ひつ)に離(かか)り、滂沱ならしむ」とある。昨晩は、月の位置が畢になかったか?』と。しかし、別の日に月が畢にあった日には、ついに雨が降りませんでした。また、商瞿氏はすでに中年なのに子がなく、その母親は彼のために嫁を世話しようと考えていました。しかし孔子は商瞿氏を斉に使者に派遣しました。商瞿氏の母が、孔子に思いとどまるように頼みました。しかし孔子は答えました。『心配なさるな。瞿は、四十以降に男子五人を得るでしょうよ』と。結果、本当にそうなりました。有子先生にお尋ねしますが、孔子先生はどうしてこれが分かったのですか?」
有若は、黙然として答えなかった。
弟子は、立ち上がって言った。
「有子よ、そこから降りたまえ。そこは、あなたの座る席ではない!」
————————————————————————————
有若は、上の弟子の質問に対して、こう答えたかったかもしれない。
「それは、諸君が孔子の的中した予言だけを取り出して記憶に残しているだけではないか。孔子だって、外れた予言がきっと沢山あったであろう。周囲の者たちは、孔子のそんな外した予言について都合よく忘れているか、あるいは別の解釈を施して当たったことにしているのだ。人間の信奉する対象への記憶とは、そのように歪みがかかるものなのだ、、、」
しかし、有若はそのような言葉を言うことはできない。
神聖なる孔子に対する、誹謗中傷の言となるからだ。
多くの弟子たちの信念の中には、孔子は予知能力者であり、中国の将来まで予言することができた神がかった天才であるという信仰が、抜き難いものとしてあったであろう。
だが理性派の有若には、そんな予言をできはしないし、おそらく彼は信じてもいなかったであろう。孔子の偉大な点は、そんな予知能力にあったのではない。もっと大きな文化人としての、教育者としての巨人であった点こそが、評価すべき点なのに、、、
だが、有若は自分の考えを弟子たちに説得することが、ついにできなかった。彼は理性人であったが、文化人、教育者としての器量は、孔子にとても及ばなかった。だから、彼は沈黙するより他はなかった。かくして、有若には孔子の才能なし、と断言すべき証拠を、この弟子に与えてしまった。
この弟子は、有若に対して、答えることができない質問を投げかけて、失脚させようと巧妙な罠を張ったのであろう。果たして有若は孔子に及ばないことが暴露されて、後継者の座から失脚した。しかし失脚させた弟子の名前を、仲尼弟子列伝は伝えていない。誰であろうか?