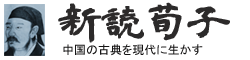|
君主の道とは、手元に近いものを治めるものであって自分から遠くにあるものを治めるものではない。君主の道とは、自らが明らかに見えるものを治めるのであって自らがよく見えないものを治めるものではない。君主の道とは、一つのことを治めるものであって二つのことを治めるのではない。君主がよく手元に近いものを治めることができたならば、結局遠くに有るものも治まるのである。君主が自らにとって明らかに見えるものをよく治めることができたならば、結局自らがよく見えないものも教化されるのである。君主が一つのことに適切な措置を施すことができたならば、結局その他の百事もまた正されるのである。そもそも天下の政治を全て聞きながら、日が余って仕事が少ないようにするためには、以上のように行えばよいのである。これが、統治の極地である。しかしすでに手元に近いものが治まっているのに自分から遠くにあるものまで治めることに努力したり、すでに自らが明らかに見えるものが治まっているのに自らがよく見えないものまで見ようと努力したり、すでに一つのことに適切な措置を施しているのに二つのことを正すことに努力したりするのは、やりすぎというものである。やりすぎは、足りないことに等しい。これを譬えるならば、真っ直ぐな木を立てておきながらその影が曲がることを期待するようなものである。だが手元に近いものがよく治まっていないのに遠くにあるものを治めようと努力したり、明らかに見えるべきものを明らかに察することができていないのに自らでは見ることが難しいものを見ようと努力したり、一つのことにすら適切な措置を施すことができていないのに百事を正そうと努力するのは、正道から外れているというものである。これを譬えるならば、曲がった木を立てておきながらその影がまっすぐになることを期待するようなものである。ゆえに明主は要点を押さえることを好み、闇主は詳細なことまで努力することを好むのである。君主が要点を好めば、結局百事が詳細に治まるだろう。だが君主が詳細を好めば、結局百事が粗略となるだろう。君主というものは一人の宰相だけを考慮し、一つの法だけを述べ、一つの指示だけを明らかにすることによって、すべてのことを兼ねて覆い、すべてのことを兼ねて照らし、事業の成功を見るのである。宰相というものは百官の特長を考慮し、百事の政務を聞いてまとめることによって、朝廷の臣下百吏の身分を整え、それらの功労を計量し、それらの慶賞を考慮し、年度の終わりにそれらの成績を君子のもとに上げて、これを報告するのである。成績がよければこれを認め、成績が悪ければこれを罷免する。ゆえに君主たるものは、直下の宰相に有能な人材を求めることに努力するのであって、いざ宰相が得られたならばそれを用いるときには休息できるのである。
国を治める者は、人民の力を得る者は富み、人民が死を捧げる者は強く、人民から栄誉を受ける者は栄える。この三つの徳が備われば天下はこの者に帰し、この三つの徳を失えば天下はこの者から去るであろう。天下が帰す者を王者と言い、天下が去る者を亡者と言う。湯王・武王は、正道に従い、正義を行い、天下共通の利益を進め、天下共通の害悪を除き、天下の人心が彼らに帰したのであった。ゆえにその名声を厚くして人民の先頭に立ち、礼義を明らかにして人民を導き、忠信を極めて人民を愛し、賢者を貴び能ある者を用いてこれらを序列し、爵位と服装と褒賞をこれらに加えて賜い、事業は正しい時に行い、役務を軽減し、人民を調斉して、ひろびろと人民をまとめて覆い、赤子を養うように人民を養育して、政令と制度を熟慮して、天下の人民に接するやり方の中で道理に合わないものがほんのわずかでもあったならば、孤(みなしご)・独(子のない老人)・鰥(妻のいない老男)・寡(夫のいない老女)のような弱者であっても、これを決して適応することはなかった。そのために人民が湯王・武王を大帝のように尊び、これを父母のように親しみ、これのために生を望むことなく、決死の思いで力を尽くした。それは他でもない、彼らの道徳が誠に明らかで、彼らのもたらす利益の恩沢が誠に厚かったからである。しかし乱世の君主は、このようでない。不潔なことを行って、他人を押しのけて利益を奪うことを率先して行い、権謀を行って人を倒す道を人に示し、俳優とか侏儒(しゅじゅ。こびと)とか婦女とかの頼みごとを容れて政治を乱し、愚者が知者に指図するようにさせ、無能者を賢者の上に立たせ、人民の生活を貧窮に追い込み、人民を使役するには労苦を極めさせる。そのために人民がこのような君主を賤しむことは匡(せむし)を賤しむようであり、これを憎むことは鬼(バケモノ)を憎むようであり、人民は日々その隙をうかがって皆でこれを投げ捨てて追い払うことを望むのである。このありさまでは、今にわかに外敵の攻撃があったならば、人民が己のために死を捧げることを望んでも、誰もそのようにしないであろう。このような君主のことを肯定する主張は、存在しない。孔子が「私が他人に接する態度を慎重に考慮するのは、それが他人が私に接する態度となるからである」と言われたのは、まさに以上のことを指しているのである。 国を傷つけるものは、何であろうか。小人を高位に付けて人民にこれを貴ばせ勢威あらしめ、取るべきでないものを人民から巧妙に取ることは、国を傷つける大災である。大国の君主でありながら、小さな利益を見ることを好むのは、国を傷つけることである。音楽や映像、展望台や狩場について、次々に厭いて新しいものを求めるのは、国を傷つけることである。いま保有している資産を整えて活用することを行わずに、飽くことなく他人が保有しているものを奪おうと常に望むのは、国を傷つけることである。これさ三つの邪悪な心が胸の中にあって、さらにまた権謀を行い人を倒すことを行う人物を登用して政治を処断させる。このようであれば、君主の権威は軽くなって名は辱められ、社稷は必ず危うくなるであろう。これが、国を傷つける者である。大国の君主でありながら、大本である行為を貴ばず旧法を敬うことなくして、詐欺を好む。このようであれば朝廷の群臣たちもまた上に従い、風俗は礼義を貴ばず、他人を倒すことを好むようになるだろう。朝廷の群臣たちの風俗がこのありさまとなれば、一般庶民たちもまた上に従い、風俗は礼儀を貴ばず、私利を貪ることを好むようになるだろう。君臣上下の風俗が全てこのありさまとなってしまうならば、いかに領地が広くても君主の権威は必ず軽くなり、いかに人口が多くても兵は必ず弱くなり、いかに刑罰が煩瑣であっても命令は下に通じなくなるであろう。これを危国と言い、これは国を傷つける者である。しかし儒者が国を治めるやり方はこのようではなく、儒者はこれらの国の治める道について、必ず詳しく述べることができる。つまり朝廷は必ず礼義を貴んで、貴賤の身分をはっきりと区別する。このようにすれば、士大夫はすべて節義につつしんで職務に命を賭すであろう。百官はその制度を整えて、その禄を重く与える。このようにすれば、その下の下級の官吏たちはすべて法を畏れて規則に従うであろう。関所と市場は検査をするにとどめて課税はせず、質律(しつりつ)(注1)によりごまかしを禁止して利益が偏らないようにさせる。このようにすれば、商人はすべて敦厚誠実となって詐偽を行わないであろう。工匠たちは時宜に応じて伐採を行わせ、納期をゆるやかにして、技能ある者には厚く手当てを行う。このようにすれば、工匠たちはすべて忠信となって粗悪品を納入しなくなるであろう。農村においては田野への税を軽くし、銭納の税を少なくして、労役を課する頻度をまれにして、農作業の時期を奪わない。このようにすれば農夫はすべて農事に朴訥に力を尽くして、他のことに多能とならなくなるであろう(注2)。士大夫は節義に務めて職務に命を賭すので、兵は強くなるだろう。下級の官吏たちは法を畏れて規則に従い、そのあかつきには国は乱れないことが常態となるであろう。商人が敦厚誠実となって詐偽を行わないならば、商人たちは安心して旅行を行い、財貨は流通して、国の需要は満たされるであろう。工匠たちが忠信となって粗悪品を納入しなくなれば、道具類は器用で便利となって財貨が乏しくなることはないであろう。農夫が農事に朴訥に力を尽くして他のことに多能とならなくなれば、上には天の時を失わず、下には地の利を失わず、中には人の和を得て、万事が頓挫せずに行われるであろう。これが、政令が行われて風俗が美であると言うのである。このようであれば国を守れば堅固であり、外に攻めれば強力であり、留まっていれば名声が挙がり、動いたならば功績が挙がるであろう。これがいわゆる、儒家が詳しく述べる政策の内容なのである。 (注1)「質律」について、楊注はこれは「質劑(しつざい)」のことであり、鄭康成を引いて、一つの札に署名してこれを二つに別ける、と注している。すなわち割符のことであり、売買の際に両者を分け持ってごまかしがないようにする制度のこと。
(注2)農民を多能にさせないのは、農民の他業種への転業を阻止して農業人口の減少を防ぐためである。前近代社会では農業生産が経済の圧倒的な基盤であったので、このような農民抑留政策が正当化された。近代の諸国家においても、しばしば農村人口の流動化を規制する反自由主義的政策が見られる。 |
|
《原文・読み下し》 主たるの道は近きを修めて遠きを治めず、明を治めて幽を治めず、一を治めて二を治めず。主能く近きを治むれば、則ち遠き者理(おさ)まり、主能く明を治むれば、則ち幽なる者化し、主能く一を當(あた)れれば、則ち百事正し。夫れ天下を兼聽し、日餘り有りて治足らざる者は、此(かく)の如くすればなり、是れ治の極なり。既に能く近きを治めて、又務めて遠きを治め、既に能く明を治めて、又務めて幽を見、既に能く一に當りて、又務めて百を正すは、是れ過ぐる者にして、猶お及ばざるがごときなり。之を辟(たと)うるに是れ猶お直木を立てて其の影の枉(まが)らんことを求むるがごときなり。近きを治ること能わずして、又務めて遠きを治め、明を察すること能わずして、又務めて幽を見、一に當ること能わずして、又務めて百を正す、是れ悖(もと)る者なり。之を辟うるに是れ猶お枉木(おうぼく)を立てて其の影の直(なお)からんことを求むるがごときなり。故に明主は要を好んで、闇主は詳を好む。主(しゅ)要を好めば則ち百事詳なり、主(しゅ)詳を好めば則ち百事荒(すさ)む。君なる者は、一相を論じ、一法を陳じ、一指を明(あきら)かにし、以て之を兼覆(けんふ)し、之を兼炤(けんしょう)し、以て其の盛(せい)(注3)を觀る者なり。相なる者は、百官の長(注4)を論列して、百事の聽を要し、以て朝廷の臣下・百吏の分を飾り、其の功勞を度(はか)り、其の慶賞を論じ、歲終(さいしゅう)に其の成功を奉じて、以て君に效(いた)す。當れば則ち可とし、當らざれば則ち廢す。故に人に君たるは、之を索(もと)むるに勞して、之を使うに休す。 國を用(おさ)むる者は、百姓の力を得る者は富み、百姓の死を得る者は强く、百姓の譽(よ)を得る者は榮ゆ。三得なる者具わりて、天下之に歸し、三得なる者亡くして、天下之を去る。天下之に歸す、之を王と謂い、天下之を去る、之を亡と謂う。湯・武なる者は、其の道に循(したが)い、其の義を行い、天下の同利を興し、天下の同害を除きて、天下之に歸す。故に德音(とくいん)を厚くして以て之に先んじ、禮義を明(あきら)かにして以て之を道(みちび)き、忠信を致(きわ)めて以て之を愛し、賢を賞(たっと)び能を使いて以て之を次(じ)し、爵服・賞慶以て之に申重(しんちょう)し、其の事を時にし、其の任を輕くして、以て之を調齊し、潢然(こうぜん)として之を兼覆(けんふ)し、之を養長すること赤子を保(ほう)するが如く、民を生(せい)せしむるには則ち寬を致(きわ)め、民を使うには則ち理を綦(きわ)め、政令・制度を辨じて、天下の人百姓に接する所以、非理なる者豪末(ごうまつ)の如き有れば、則ち孤獨鰥寡(こどくかんか)と雖も必ず加えず。是の故に百姓の之を貴ぶこと帝の如く、之に親しむこと父母の如く、之が爲に出死・斷亡(だんぼう)して愉(とう)せざる(注5)者は、它(た)の故無し、道德誠に明(あきら)かに、利澤(りたく)誠に厚ければなり。亂世は然らず、汙漫(おまん)・突盜(とつとう)以て之に先んじ、權謀・傾覆以て之に示し、俳優・侏儒(しゅじゅ)、婦女の請謁(せいえつ)以て之を悖(みだ)し、愚をして知に詔(つ)げしめ、不肖をして賢に臨ましめ、民を生(せい)せしむるには則ち貧隘(ひんあい)を致(きわ)め、民を使うには則ち勞苦を極む。是の故に、百姓の之を賤むこと㑌(おう)(注6)の如く、之を惡(にく)むこと鬼の如く、日に間を司(うかが)いて相與(とも)に之を投藉(とうせき)し、之を去逐(きょすい)せんと欲す。卒(にわか)に寇難(こうなん)の事有れば、又百姓の己の爲に死せんことを望むも、得可からざるなり。說以て之を取ること無し。孔子の曰(のたま)わく、吾が人に適(ゆ)く所以を審(つまびら)かにするは、[適](注7)人の我に來る所以なればなり、とは、此を之れ謂うなり。 國を傷つくる者は何ぞや。曰く、小人を以て民に尚(しょう)として威あらしめ、非所を以て民に取りて巧なるは、是れ國を傷つくるの大災なり。大國の主にして、好んで小利を見るは、是れ國を傷つくるなり。其の聲色(せいしょく)・臺榭(たいしゃ)・園囿(えんゆう)に於けるや、愈(いよいよ)厭きて新を好むは、是れ國を傷つくるなり。其の以(すで)に有する所を循正することを好まずして(注8)、啖啖(たんたん)として常に人の有を欲するは、是れ國を傷つくるなり。三邪なる者匈中(きょうちゅう)に在りて、又好んで權謀・傾覆の人を以て、事を其の外に斷せしむ、是の若くなれば、則ち權輕く名辱しめられ、社稷(しゃしょく)必ず危し、是れ國を傷つくる者なり。大國の主にして、本行を隆ばず舊法(きゅうほう)を敬せずして、詐故(さこ)を好む。是の若くなれば、則ち夫の朝廷の羣臣(ぐんしん)も、亦從いて俗を禮義を隆ばずして傾覆を好むに成すなり。朝廷羣臣の俗是(かく)の若くなれば、則ち夫の衆庶・百姓も、亦從いて俗を禮義を隆ばずして、貪利(たんり)を好むに成すなり。君臣・上下の俗是の若くならざること莫ければ、則ち地廣しと雖も權必ず輕く、人衆(おお)しと雖も兵必ず弱く、刑罰繁(しげ)しと雖も令下に通ぜず、夫れ是を之れ危國と謂う、是れ國を傷つくる者なり。儒者の之を爲すは然らず、必ず將(は)た曲辨(きょくべん)す。朝廷必ず將(は)た禮義を隆びて貴賤を審(つまびら)かにす。是の若くなれば、則ち士・大夫は節に敬み制に死せざる者莫し。百官は則ち將(は)た其の制度を齊え、其の官秩(かんちつ)を重くす。是の若くなれば、則ち百吏は法を畏れて繩(じょう)に遵(したが)わざること莫し。關市(かんし)は幾(き)して征(せい)せず、質律は禁止して偏ならず。是の如くなれば、則ち商賈(しょうこ)は敦愨(とんかく)にして無詐ならざること莫し。百工は將(は)た時に斬伐し、其の期日を佻(ゆるやか)にして、其の巧任を利す。是の如くなれば、則ち百工は忠信にして不楛(ふこ)ならざること莫し。縣鄙(けんぴ)は將(は)た田野の稅を輕くし、刀布の斂(れん)を省き、力役を舉(あ)ぐることを罕(まれ)にし、農時を奪うこと無し。是の如くなれば、則ち農夫は朴力にして寡能ならざること莫し。士・大夫は節を務め制に死す、然而(かくのごとくして)(注9)兵勁(つよ)し。百吏は法を畏れて繩に循(したが)い、然る後に國常に亂れず。商賈は敦愨にして無詐なれば、則ち商旅安んじ、貨財通じて(注9)、國求(こくきゅう)給す。百工は忠信にして不楛なれば、則ち器用巧便にして財匱(とぼ)しからず。農夫は朴力にして寡能なれば、則ち上は天の時を失わず、下は地の利を失わず、中は人の和を得て、百事廢せず。是を之れ政令行われ風俗美なりと謂う。以て守れば則ち固く、以て征すれば則ち强く、居れば則ち名有り、動けば則ち功有り。此れ儒の所謂(いわゆる)曲辨(きょくべん)なり。 (注3)楊注は、「盛は読んで成と為す、その成功を観るなり」と言う。
(注4)原文「百官之長」。これを新釈の藤井専英氏は「すべての役人の特長」と訳している。王制篇で冢宰すなわち宰相の職分として「其の慶賞を論じ、時を以て順脩し、百吏をして免盡(べんじん)」すべきことが述べられている。よって宰相の職分は単に各省庁の長官についての論功行賞だけにとどまらず、百官の論功行賞の総括を行うべきことが想定されている。よって藤井氏の解釈でも通ると、私は考える。金谷治氏は「多くの長官」と訳している。こちらがオーソドックスな解釈であろう。上の訳では、藤井説に従っておく。 (注5)富国篇(2)注6を参照。ここも「愉」字を「偸」字に通じるとみなす。 (注1)「㑌」は匡(おう)で、せむしのこと。なお楊注には「新序は、之を賤しむこと虺豕の如しに作る」とあり、ここから集解の郝懿行は「㑌」字は「虺」であるべきで、虺(き)と鬼(き)で韻が合う、と言う。虺は、蝮(まむし)のこと。「㑌」字のままでも解釈できるので、このままとする。なお、「㑌」字はCJK統合漢字拡張Aにしかない。 (注6)増注、集解の王念孫ともに『群書治要』の引用では後ろの「適」字がないことを指摘して、衍字と言う。これらに従う。新釈の藤井専英氏は、後ろの「適」字を「適(まさ)に」と読み下している。 (注7)原文「不好循正其所以有」。王覇篇(1)注13と同じく、「以」を「すでに」と読んでおく。 (注8)楊注は、「然而」を「然後」と読むべしと言う。下の文と合せているのである。集解の王念孫は、「然」は「如是」なり、と言う。王説に従えば、「然而(かくのごとくして)」と読み下すであろう。王説を取りたい。 (注9)原文「貨通財」。集解の王念孫は、王制篇に従って「貨財通」となすべし、と言う。これに従う。 |
王覇篇は、以上である。
荀子が理想とする王者の統治術とは、礼法を整えて官吏と人民を規則に応じて働かせ、能力に応じて身分と官職に昇進・罷免を当てはめ、君主は瑣末な事務を行うことなく、天下の詳細な情報まで知り尽くすこともなくして、しかも統治がスムーズに行われる、というものである。つまり王者の統治術とは、法に仕事をさせ、システムに仕事をさせることに尽きる。孟子は統治者の善なる心こそが国家を強くする要因であると言ったが、統治者の心情にこだわること多大であったが具体的に国家システムをどのように動かすべきか、という考察に欠けていた。荀子の統治術は、彼に続く儒家としてそれを補うものであった。
しかしながら、荀子が儒家の思想に沿って案出した具体的な統治術は、彼の弟子である韓非子や李斯の法家思想と、どれほどの隔たりがあるだろうか。いくら荀子が彊国篇で秦国の政治には儒家の推奨する道が足りないと批判したとしても、荀子は秦国の法による統治システムを賞賛するより他はなかった。この王覇篇で荀子は覇者を不足であると批判して王者を推奨するが、その描く王者の統治術は法治官僚国家のシステムそのものである。それは、長くて無意味な戦乱が続いた中華世界の戦国時代を終わらせるために、荀子が描いた理想であった。だが、国家とは必要悪であり怪物リヴァイアサンであるというホッブスの認識とは違って、荀子が法治官僚国家を美しい王者の理想として描くことに終始してしまっているのは、思想史的に残念なことである。