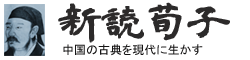|
一 要点を申すならば、人君なるものは礼を尊び賢人を尊べば、王者となる。法を重んじて人民を愛すれば、覇者となる。利を好んで詐りが多ければ、危険に陥る。 二 ※楊注は、其の朝貢道里の均しきを取る、と注する。納税を首都に集めるために最適な土地は国の中央に置くのが礼である、と言う意味。
三 ※たとえば、王覇篇(6)の議論を参照。「君主の道とは、手元に近いものを治めるものであって自分から遠くにあるものを治めるものではない。君主の道とは、自らが明らかに見えるものを治めるのであって自らがよく見えないものを治めるものではない。」
四
また天子が諸侯を召し出したならば、車を厩まで引っ張って馬に繋げ急いで駆け付けるのが、礼である。『詩経』に、この言葉があるとおり。
※『論語』郷党篇にも、「君、命じて召さば、駕を俟たず行く」とある。『孟子』公孫丑章句下二にもこの語は表れて、そこでは孟子が斉の宣王の呼びつけに応じなかったことを斉臣の景丑が非礼であると非難した言葉の中で用いられている。孟子は、「天下の王者となることをを目指す君主ならば、賢者を師として敬うべきであって呼びつけなどにはしない」と反論して、自らの非礼は非礼ではないと逆襲した。
五 |
| 《読み下し》 大略(たいりゃく)人に君たる者は、禮を隆(とう)とび賢を尊びて王たり、法を重んじ民を愛して霸たり、利を好み詐多くして危うし。 四旁(しほう)に近からんと欲すれば、中央に如(し)くは莫し。故に王者は必ず天下の中(ちゅう)に居るは、禮なり。 天子は外に屏(へい)(注1)し、諸侯は內に屏するは、禮なり。外に屏するは、外を見んことを欲せざるなり、內に屏するは、內を見んことを欲せざるなり。 諸侯其の臣を召せば,臣駕を俟(ま)たず、衣裳を顛倒して走るは、禮なり。詩に曰く、之を顛し之を倒する、公自(よ)り之を召せばなり、と。天子諸侯を召せば、諸侯輿(よ)を輦(れん)し馬に就くは、禮なり。詩に曰く、我我が輿(注2)を出す、彼の牧に于(おい)てす、天子の所自(よ)り、我に來れと謂う、と。 天子は山冕(さんべん)し、諸侯は玄冠(げんかん)し、大夫は裨冕(ひべん)し、士は韋弁(いべん)するは、禮なり。天子は珽(てい)を御し、諸侯は荼(じょ)を御し、大夫は笏(こつ)を服するは、禮なり。天子は彫弓(ちょうきゅう)、諸侯は彤弓(とうきゅう)、大夫は黑弓(こくきゅう)なるは、禮なり。 (注1)集解の郝懿行は、「今の照壁のごとし」と言う。照壁とは、中国建築で門の前あるいは後ろに置く目隠し塀のこと。
(注2)現行本『詩経』では、「輿」字を「車」字に作る。 |
大略篇は『孟子』の盡心章句に相当する篇であって、荀子の断片的な語録が中心となっている。楊注は、「此の篇蓋(けだ)し弟子荀卿の語を雑録し、皆其の要を略挙す。一事を以て篇を名づくる可からず、故に總(そう)じて之を大略と謂うなり」と冒頭に記す。やや長い論述も若干含まれているが、その大半は一あるいは二文ぐらいで完結している。『孟子』盡心章句は最末尾二章を除いて配列にはっきりした傾向が見られないが、この大略篇については少なくとも前半の各章は礼に関する言葉が集中して置かれている。荀子の最も重視する礼についての覚書を、まとめて置いたのであろう。だが後半は、前半ほどに一貫したテーマが見られない。
漢文大系は、大略篇を101章に分けている。新釈漢文大系は、90章に分けている。本サイトでは、新釈漢文大系に沿った章割りを採用することにしたい。読み下しと訳は、複数の章をまとめて1ページで行う。コメントは、本文の下に小さい文字で加えることとしたい。