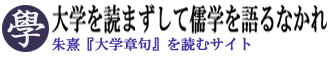『中庸或問』跋・題名二~なぜ「中和」でなくて「中庸」なのか~
|
出典:国立国会図書館デジタルコレクション『四書集注大全』(明胡廣等奉敕撰、鵜飼信之點、附江村宗□撰、秋田屋平左衞門刊、萬治二年)より作成。 〇各ページの副題は、内容に応じてサイト作成者が追加した。 〇読み下しの句読点は、各問答の中途は読点、末尾は句点で統一した。 〇送り仮名は、原文から現代日本語に合わせて一部を変更し、かつ新かなづかいに変えた。 |
|
《読み下し》 曰、此の篇首の章に先ず中和の義を明す、次の章に乃ち中庸の切に及ぼす、其の篇名づくるに至りては、乃ち中和と曰わずして中庸と曰う者は何ぞや。 曰、中和の中は、其の義精(くわ)しと雖も而(しこう)して中庸の中は、實に體用を兼ぬ、且つ其の所謂(いわゆる)庸は、又平常の意有るときは、則ち之を中和に比すれば、其の該(か)ぬる所の者尤も廣し、而して一篇の大指に於て、精粗本末、盡さずという所無し、此れ其の中和と曰わずして中庸と曰う所以なり。 曰、張子(注1)の言(こと)如何。 曰、其の須く句句理會して其の言をして互に相發明せしむべしと曰う者は、眞に書を讀むの法、但だ此の篇に施す可きのみにあらず。 曰、呂氏(注2)己が爲にし人の爲にするの説如何。 曰、人の爲にする者は、程子以て人に知ら見(れ)んと欲すと爲る者是なり、呂氏は功名に志すを以て之を言いて、而して今の學者未だ此に及ばずと謂うときは、則ち是れ人の爲にし物に及ぼすが爲にするの事を以て、渉獵(しょうりょう)徼幸(ぎょうこう)(注3)して以て其の私を濟(わた)らんと求むる者は、又此より下一等なり、殊に知らず夫子の所謂人の爲にす(注4)という者は、正に此の下等の人を指すのみ、若し未だ己を成すこと能わずして、遽(にわか)に物を成さんと欲すと曰うは、此れ特(ただ)に以て先後する所を知ること能わざるの罪に坐す可し、其の心を設くるを原(たず)ぬるに、猶お愛して公なるがごとし、彼の人の知らんことを求めて以て一己の私を濟らんと欲して、而して後に學ぶ者に視(くら)ぶれば、日を同じて語る可からず、其の所謂喜怒哀樂未發の中を立てて以て之が本と爲し、學者をして善を釋きて固く之を執らしめんという者に至りては、亦學者をして務めて存養を先にして以て理を窮むるの地を爲さしめんと欲すと曰うのみ、而して之を語るに未だ瑩(きよ)からず、乃ち聖人强いて此の中を立てて以て大本と爲して、人をして是を以て準と爲して中を取らしむるに似たり、則ち中は、豈に聖人の强いて立つる所ならんや、而して未だ發せざるの際、亦豈に學者其の間に擇び取る所有る容(べ)けんや、但だ其の全章大指は、則ち以て切に今時の學者の病(へい)に中(あた)ること有り、誠に能く三たび復して思を致さば、亦以て感悟して興起す可し。 (注1)張子は、張横渠のこと。大学或問・伝五章の四の注を参照。四書大全の引用に、「學者中庸の文字の輩の如きは、直に須らく句句理會し過ぎて、其の言を互に相發明せしむべし」。朱子は、程子・張子を引用するときには敬称の「子」を用いる。
(注2)呂氏は、呂大臨のこと。題名一の注を参照。四書大全の引用に、「己の爲にする者は、心德行に存して功名に意無し、人の爲にする者は、心功名に存して未だ德行に及ばず、後世の若きは未だ人の爲にするに及ばずして、人其の私欲を濟(な)す者有り」 (注3)徼幸は、運よく。僥倖と同じ。中庸章句、第十四章本文「小人は險を行いて、以て幸を徼(もと)む」 (注4)論語憲問篇「古(いにしえ)の学者は己の為にし、今の学者は人の為にす」より。 |
《要約》
|