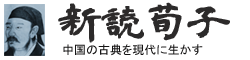|
雑多な案件を対処するためには、法判断によってまとめあげる。一人の判断力で、万人を処断する。この調子で始まれば終わり、終われば始まると事物を決裁していき、ぐるぐると環を回るように天下を運営するのである。これを中断させたならば、天下は衰亡するのである。天地なるものは生命の始まりであるが、礼義なるものは統治の始まりであり、そして君子なるものは礼義の始まりなのである。礼義を実践し、礼義を習い、礼義を重ねて学び、礼義を好むことは、君子の始まりである。ゆえに天地は君子を生じ、その君子が天地を統治するのである。君子なるものは、天地の補佐人(注1)なのである。万物の指揮官なのである。人民の父母なのである。君子がいなければ、天地は統治されず、礼義には統制がなくなり、上には君主の師なく、下には父子の秩序もない。これを、乱の極みと言う。君臣父子、兄弟夫婦は、始まれば終わり終われば始まる、連綿と続く人間関係である。天地と理を共有していて、何代経ってもその理は不変である。これを、大本と言う。ゆえに喪礼と祭礼、朝覲(ちょうきん。諸侯の君主への拝謁式)と聘問(へいもん。諸侯の他国への訪問式)、師・旅の軍隊編成は、すべて理によって一つなのである。また貴賎の差、生殺の刑、与奪の処分もまた、すべて理によって一つなのである。また君は君、臣は臣、父は父、子は子、兄は兄、弟は弟の人倫秩序もまた、すべて理によって一つなのである。
水や火には気(注2)があるが生命はない。草や木には生命はあるが知能はない。禽獣(ケダモノ)には知能はあるが義はない(注3)。しかし人には気も生命も知もあり、かつ義もある。ゆえに最も天下で尊い存在なのである。人間の力は牛にかなわず、走れば馬にはかなわない。なのに、どうして牛馬は人間に使役されるのであろうか?それは、人は社会生活ができるが、牛馬はできないからである。人は何によって、社会生活ができるのであろうか?それは、区分によってである。区分は、何によってよく実施されるのであろうか?それは、義によってである。ゆえに義によって区分すれば社会は調和し、調和すれば一つに固まり、一つに固まれば大きな力となり、大きな力となれば強力となり、強力となれば、万物に勝利するのである。人間が家屋の中に住まうことができて、四季に応じて秩序立って生活ができて、万物を統御することができて、天下をすべて利用することができるのは、他でもない、人間が社会を義に応じて区分するからなのである。 次に、王者の官職について述べる。
以上である。ゆえに、政治が乱れるのは百官の総帥である冢宰(ちょうさい)の罪であり、国家が良風美俗を失うのは各地の封建君主である辟公(へきこう)の過失であり、そして天下が斉一されずに諸侯が離反するのは、諸侯の長である天王がその位に就くべき器ではないからである。 (注1)原文「参」猪飼補注は「なお参佐のごとし」と言う。(注2)「気」は元気、空気など現代日本語では熟語化してしまって、それ自体では意味のない字となっている。古代には明確に万物にひそむ何らかのエネルギー活動の素を指す用語としてあった。朱子学は「気」を抽象化して「理」と対比する宇宙の構成・生成原理とみなし、「理」と「気」の関係は進んで人間内部にもあって倫理学のテーマとなる。理気の存在学・倫理学は朱子学の最重要概念の一つなのであるが、現代科学の認識とは異なっている。(注3)禽獣に「知」があるというのであるが、集解の郝懿行は匹(つが)う能力があると言う。楊注の言う「性識」つまり同種の異性を見分ける能力は禽獣にもあるが、「義」はない。その例として郝懿行は『曲礼』の「麀(ゆう)を聚(とも)にす」を引き、鹿は父子で雌鹿を共有するので義がない、という例を引く。当然ながら、このような儒家の認識はただのアントロポセントリズム(人類中心主義)でエスノセントリズム(自民族中心主義)な独断である。この認識から、儒家はレビラト婚(兄の死後に実弟が兄の寡婦を娶る婚姻制度)を習俗として持つ遊牧民たちを禽獣視するのである。(注4)原文読み下し「君なる者は、善く羣するなり。」猪飼補注が言うように、ここは「君」と「羣(群)」の音で意味をひっかけた言い方である。意訳した。(注5)富国篇(3)の注2参照。(注6)原文読み下し「天地の閒に塞備(そくび)し」。集解の王引之は「備」は「満」にすべしと言う。ここは前の句を受けて、天地の利用できる機会をすべて見逃さない、という意味に訳した。(注7)このあたりは、意図的に法家思想的に訳した。(注8)原文「一與一是爲人、謂之聖人。」難解。猪飼補注は「是」は「奪」の誤りかと言い「一与(與)一奪して人を爲(おさ)める」と読む。言うは、聖人の政策は人民に禁令を布くが後で豊富を得させるためだ、という解釈であろう。集解の王先謙は「與」を「擧(挙)」と読み替えて「一にして一を挙ぐる」と読む。言うは、聖人は一人の指令で人民を統一する、という意味であろう。『新釈漢文大系』および金谷治氏は猪飼補注を取るが、私は王先謙の説のほうがここでいう聖人の政策に近いと考える。(注9)天論篇で、荀子は天文占いの的中性や雨乞いの儀式の効果を完全に否定している。それでも王者の官職に占い担当官を置くのは、ひとえに迷信を信じる人民を信頼させる効果があるにすぎない。(注10)五種類の体刑。軽い順から、墨(ぼく、入れ墨)、劓(ぎ、鼻削ぎ)、刖(げつ)または剕(ひ、足切断)、宮(きゅう、去勢)、大辟(たいへき、死刑)のこと。荀子は体刑を統治のために必要とみなす。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《原文・読み下し》 類を以て雜に行き、一を以て萬に行き(注11)、始まれば則ち終り、終れば則ち始まり、環の端無きが若し。是を舍(お)いて而(しこう)して天下以て衰う。天地なる者は生の始(はじめ)なり、禮義なる者は治の始なり、君子なる者は禮義の始なり。之を爲し、之を貫(かん)し、之を積重し、之を致好する者は、君子の始なり。故に天地君子を生じ、君子天地を理(り)す。君子なる者は天地の參(さん)なり、萬物の摠(そう)なり、民の父母なり。君子無ければ、則ち天地理せず、禮義統無く、上君師無く、下父子無し。夫れ是(注12)を之れ至亂と謂う。君臣父子、兄弟夫婦は、始まれば則ち終り、終れば則ち始まり、天地と理を同じうし、萬世と久を同じうす。夫れ是を之れ大本と謂う。故に喪祭・朝聘(ちょうへい)・師旅は一なり。貴賤・殺生・與奪(よだつ)は一なり。君は君、臣は臣、父は父、子は子、兄は兄、弟は弟たるは一なり。農は農、士は士、工は工、商は商たるは一なり。 水火は氣有りて生無く、草木は生有りて知無く、禽獸は知有りて義無く、人は氣有り、生有り、知有り。亦(また)且つ義有り。故に最も天下の貴と爲すなり。力は牛に若かず、走ることは馬に若かず、而(しか)も牛馬用を爲すは何ぞ。曰く、人は能く羣(ぐん)し、彼は羣すること能わざればなり。人何を以て能く羣す。曰く、分あればなり。分何を以て能く行わる。曰く、義(注13)あればなり。故に義以て分(わか)てば則ち和す。和すれば則ち一なり、一なれば則ち多力なり、多力なれば則ち强なり、强なれば則ち物に勝つ、故に宮室得て居る可きなり。故に四時を序し、萬物を裁し、天下を兼利するは、它の故無し、之が分義を得ればなり。故に人生羣無きこと能わず、群して分無ければ則ち爭う、爭えば則ち亂れ、亂るれば則ち離れ、離るれば則ち弱し、弱ければ則ち物に勝つこと能わず、故に宮室得て居る可からず。少頃(しばらく)も禮義を舍(す)つ可からざるの謂いなり。能く以て親に事(つか)うる、之を孝と謂い、能く以て兄に事うる、之を弟と謂い、能く以て上に事うる、之を順と謂い、能く以て下を使う、之を君と謂う。君なる者は、善く羣するなり。羣道(ぐんどう)當れば、則ち萬物皆其の宜しきを得、六畜(りくきく)皆其の長を得、羣生皆其の命を得(う)。故に養長時(とき)なれば、則ち六畜育す。殺生時なれば、則ち草木殖す。政令時なれば、則ち百姓一に、賢良服す。聖王の制なり。草木、榮華・滋碩(じせき)の時なれば、則ち斧斤(ふきん)山林に入らざるは、其の生を夭せず、其の長を絕たざるなり。黿鼉(げんだ)・魚鼈(ぎょべつ)・鰌鱣(しゅうせん)、孕別(ようべつ)の時は、罔罟(もうこ)・毒藥(どくやく)、澤に入らざるは、其の生を夭せず、其の長を絕たざるなり。春耕・夏耘(かうん)・秋收・冬藏、四者時を失わず。故に五穀絕えずして、百姓餘食(よしょく)有るなり。汙池(おち)・淵沼(えんしょう)・川澤、其の時禁を謹む、故に魚鼈優多(ゆうた)にして、百姓餘用(よよう)有るなり。斬伐・養長、其の時を失わず、故に山林童(どう)ならずして、百姓餘材有るなり。聖王の用なり。上は天に察に、下は地に錯(そ)し、天地の間に塞備(そくび)し、萬物の上に加施(かし)す。微にして明、短にして長、狹にして廣、神明・博大にして以て至約なり。故に曰く、一にして一を與(あ)ぐる(注14)、是をもて人を爲(おさ)むる者、之を聖人と謂う、と。 序官。宰爵は、賓客・祭祀・饗食・犧牲の牢數を知(つかさど)る。司徒は、百宗・城郭・立器の數を知る。司馬は、師旅・甲兵・乘白(じょうはく)の數を知る。憲命を脩め、詩商を審(つまびらか)にし、淫聲を禁じ、時を以て順脩(じゅんしゅう)し、夷俗・邪音をして敢えて雅を亂らざらしむるは、大師の事なり。隄梁(ていりょう)を脩め、溝澮(こうかい)を通じ、水潦(すいりょう)を行(や)り、水臧を安んじ、時を以て決塞(けっそく)し、歲凶敗・水旱すと雖も、民をして耘艾(うんがい)する所有らしむるは、司空の事なり。高下を相し、肥墝(ひこう)を視、五種を序し、農功を省し、蓄藏を謹み、時を以て順脩し、農夫をして樸力(ぼくりょく)にして寡能ならしむるは、治田の事なり。火憲(かけん)を脩め、山林・藪澤(そうたく)・草木・魚鼈、百索(ひゃくさく)(注15)を養い、時を以て禁發し、國家をして用に足りて財物屈せざらしむるは、虞師(ぐし)の事なり。州里を順にし、廛宅(てんたく)を定め、六畜を養い、樹藝を閒(ならわ)し、敎化を勸め、孝弟を趨(うなが)し、時を以て順脩し、百姓をして命に順い、安樂して鄉に處らしむるは、鄉師の事なり。百工を論じ、時事を審にし、功苦を辨じ、完利を尚(とうと)び、備用を便にし、雕琢(ちょうたく)・文采をして敢えて家に專造せざらしむるは、工師の事なり。陰陽を相し、祲兆(しんちょう)を占し、龜を鑽(さん)し卦(か)を陳し、攘擇(じょうたく)・五卜(ごぼく)を主(つかさど)りて、其の吉凶・妖祥を知るは、傴巫(うふ)・跛擊(ひげき)の事なり。採清(さいせい)を脩め、道路を易(おさ)め、盜賊を謹み、室律(しつし)(注16)を平らかにし、時を以て順脩し、賓旅をして安んじて貨財をして通ぜしむるは、治市の事なり。急(げん)を抃(わか)ち(注17)悍を禁じ、淫を防ぎ邪を除き、之を戮(りく)するに五刑を以てし、暴悍以て變じ、姦邪作(おこ)らざらしむるは、司寇の事なり。政敎に本づき、法則を正し、兼聽して時に之を稽(かんが)え、其の功勞を度(はか)り(注18)、其の慶賞を論じ、時を以て順脩し、百吏をして免盡(べんじん)して衆庶をして偷(とう)せざらしむるは、冢宰(ちょうさい)の事なり。禮樂を論じ、身行を正し、敎化を廣め、風俗を美にし、兼覆して之を調一するは、辟公(へきこう)の事なり。道德を全くし、隆高を致し、文理を綦(きわ)め、天下を一にし、毫末(ごうまつ)を振い、天下をして順比・從服せざること莫からしむるは、天王の事なり。故に政事亂るるは、則ち冢宰の罪なり。國家俗を失うは、則ち辟公の過なり。天下一ならず、諸侯俗反するは、則ち天王其の人に非ざるなり。 (注11)「類」を楊注は「統類」と言い、『新釈漢文大系』もこの語で訳しているが、意味がよくわからない。「一」を楊注は一人と言う。ここは君子官僚の統治術について述べていると考えて上に訳した。(注12)宋本は「下父子夫婦是」となっているが元本は「婦」字がない。『漢文大系』『新釈漢文大系』ともに「婦」字を取り除いて「夫」を「それ」の意味に読み、続く文と語調を合わせている。(注13)宋本には義の前に「以」字があり、元本にはない。(注14)「與」を「擧」と読み替える。注8参照。(注15)「百索」を楊注は百物と言い、集解の王引之は「索」は「素」の誤りで蔬菜(野菜)の意と言い、猪飼補注は「百求」の意と言う。猪飼補注を取る。(注16)「室律」を集解の郝懿行は「律」は「肆(し)」の誤りとして「室肆」で旅客・商人のための施設であろうと言う。増注は「室」は「質」の誤りとして王覇篇(6)にある「質律」であると言う。すなわち売買の際の割符であり、売買の約定を破らせないことによって物価を平均化すると言う。ここは郝懿行に従う。(注17)楊注「抃はまさに析と為すべく、急はまさに愿と為すべし。」王制篇(4)の語句。(注18)王制篇は、ここの「其の功勞を度り、、」から以降、楊注が全くない。藤井専英氏は、ここから以降相当の脱誤があるのではないか、と疑っている。
|
身分秩序・官僚制度の理論と細目である。この篇で、荀子は結局このくだりが言いたかった。来るべき中華帝国のシステムである。だが現代となっては、もはや歴史的意義しかない。荀子の時代においては、これこそが人間に生命と繁栄を与える、夢の国作りであった。ゆえに、マルクシズムが共産主義の到来を歴史的必然として描いたように、荀子もまた王者の革命を必然の未来として確信していたことであろう。それは、私もまた理解することにやぶさかではない。しかしながら、現代に生きる私にとっては、これが理想だと言われても困ってしまう。これは理想ではなくて、目の前の社会が完備している現実の法治官僚国家の姿なのである。我々は荀子よりも前に進みたいという、ぜいたくな希望を持たずにはいられないのだ。
荀子は人間を社会的動物であると考えるが、人間は社会を作るときに必然的に上下の差別を作る、とも考える。この考えは、経済人類学の知見から言えば、人間のほんの一面しか見ていない。荀子が人間の必然的性質とみなす身分秩序は、国家の成立によって国家内部で生じた略取―再分配の交換様式を指している。それは、力による支配が既定事実化したときに、支配者が被支配者から税を略取し、その対価として支配者が被支配者を保護育成する福祉政策を行う交換様式である。これが支配関係の中に縛られている人間にとってギブ・アンド・テイクに表象されて、被支配者が支配者を恵み深い君主として崇め、かつ支配者の政策を実行する官僚の身分的経済的優位が正当化されるのである。しかしこれは、人間の交換様式の全てではない。
国家以前の交換関係として、人間には互酬の交換様式がある。これは人間同士が対等の関係で向き合ったとき、一方が財貨やサーヴィスを他方に無償で贈与することによって、贈与された側に負債感を感じさせる交換様式である。このとき贈与した側は一時的に二人の間で強者となり、贈与された側は負債感を償うためのアクションを強いられることとなるだろう。それは倍返しの贈与となるか、第三者に贈与して互酬の輪を広げるか、あるいは贈与した者への負けを認めて服従するか、である。この互酬関係は略取―再分配の関係とは違って贈与する側と贈与される側の上下関係は固定されておらず、贈与された側は具体的に贈与された分だけ負債感を感じるにすぎない。お世話を受けた人への恩返しの感覚、と言えばわかりやすいであろう。これは国家秩序を伴わない自発的な人間の上下関係であって、国家が作る支配―被支配関係とは違うものである。対等の市民が集まっているという建前を重視する都市国家や、受けた御恩の限り奉公する主従関係を軸とした封建国家では、国家の中に互酬関係が強く残留している。つまりこのような国家では、王といえども、家臣に絶対的な支配権を持つようには表象されない。(あともう一つ、人間の交換様式には商品交換があるが、これは疎遠な人間同士を貨幣という一般的交換手段でつなぐ関係であり、疎遠な人間同士が戦争せずにギブ・アンド・テイクする関係として重要であるが、ここではとりあえずおいておく。)
疎遠でない人間同士をつなぐ関係は、荀子の言うような身分秩序ある国家だけではない。そう見えるのは、国家を支持する側の人間である。荀子の視点からは、人間は国家以前に互酬関係によってつながる欲求がある、ということが見えなくなってしまう。春秋時代の感覚を残していた孟子はまだ国家以前の互酬関係を認識していたと私は考えるが(孟子のときおり見せる君主への不遜な態度は、君主と賢人は対等のギブ・アンド・テイク関係でなければならない、という考えがあったからである)、荀子はもう全く国家内部での支配者―被支配者間の略取―再分配の関係だけに注目してしまっている。
(経済人類学については、私は栗本慎一郎氏およびK.ポランニーの著作から主に知見を得てきました。しかし経済人類学の互酬、略取―再分配、商品交換の三つの交換様式の組み合わさり方を人類史の各段階として一挙に叙述した仕事として、私はやはり柄谷行人氏の『世界史の構造』を挙げたいと思います。以上の叙述も、柄谷氏の概念に負っています。)