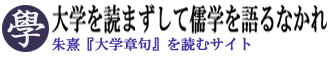題名:南宋道学の展開(プリミエ・コレクション96)
著者:福谷彬(ふくたに・あきら)
発行所および初版発行年:京都大学学術出版会、2019年
先日ブログ筆者が参加する論語読書会において、先生からご著書をいただきました。京都大学で教鞭を取られておられる先生の著作を、門外漢である私が書評するなどおこがましいことです。それを承知の上で、「阿らず読む」(吉田松陰)ことを心がけて、あえてここに残します。
令和甲辰芒種の頃 河南人
本書の概要
「道学」と聞くとああ朱子学のことか、と思いがちであるが、本書が扱う範囲は宋代の時期に意味されていた「道学」、すなわち朱子(朱熹)の学を一派として含んだ近接する各スクールにまで及んでいる。本書は、それら南宋期に並び立っていた道学各派の論争の経過を辿る試みである。北宋期に活動したいわゆる周張二程、あるいは邵康節・司馬光らの新しい儒学研究は、大きく分けて四つのスクールをもって南宋に受け継がれた。すなわち①朱子の閩学、②胡宏・張栻の湖南学、③呂祖謙・陳亮の浙学、④陸九淵(陸象山)兄弟の江西学である。本書では、朱子が他派の胡宏・陳亮・陸九淵と行った論争の内容が解明される。面白いことに四派は互いの思想的立場をもって厳しく論争した(というより、朱子が非妥協的に他派を排斥しようとした)にも関わらず、宋朝政界においては四派はまとめて「道学」とみなされて、政界の反道学派と弾圧反撃の政争を行っていたのであった。本書が解明するところでは、陸九淵は道学派全体の利益を考えてより反対派にも融和的であるべきと考え、朱子の異端を排斥する狭量な姿勢に学問の内容とは異なるレベルで批判的であった。浙学を継いだ陳亮は、先達の呂祖謙から思想的に離れて「事功派」と呼ばれ、朱子から批判を受けた。その陳亮は、漢唐代の皇帝は統治の実績を残したがゆえに道徳的であったと論じ、周の没落以降の王朝はすべて覇道で道徳はない、と論じる朱子と対立した。陳亮はその晩年に科挙で首席合格したが、その際に提出した殿試の答案は、新皇帝の光宗に対してへつらう内容であると朱子たちには捉えられた。だがここは韓非子以来の政治の難問であって、まず最高権力者の信任を得なければ国政を取ることもできず、自らが抱く政治の理想を実行するよすがもない。最高権力者が聡明であれば善言を喜び佞言を斥けることもできるだろうが、歴史が証明するようにそのような明君が現れることははなはだ稀であって、大抵の最高権力者は良くも悪くもない凡庸な存在である。その凡庸な君主にとりあえずも信任され、その範囲内で善政を積み上げていく戦略は、朱子が批判するよりは現実的であろう。その現実への妥協が、朱子は許せないのであろうが。へつらいにも捉えられ兼ねない陳亮の論、君主の欠点ばかりを責める朱子の論、両者の論は「驕君乱臣の地たるを免れず」(297ページ、陳傳良からの引用より)という批判は、もっともな意見である。
ともあれ、南宋期の「道学」各派が互いに論争を行う星雲の状態であったことは、当時の思想が健全に運動していたことの証左となるであろう。学問思想が発展している時代は、こちらからの作用に対して相手からの反作用が働き、それがさらに弁証法的に進化させていく。南宋代の道学にはそれがあったことを示すのが、本書の内容である。ブログ筆者は島田虔次『朱子学と陽明学』、および三浦國雄『朱子伝』を読んできたが、本書を併せることによって南宋代の思想状況をより立体的に捉えることができるようになった。元明代に入って朱子学だけが勝利することとなって作用反作用が止まり、朱子学以外は異端あるいは朱子学の補足とみなされるようになって、前の時代の思想状況が見通せなくなってしまった。
さて本書の最終章は、朱子の『資治通鑑綱目』(以下『綱目』)の編集方針を論じている。朱子の『綱目』における「正統」は倫理的含意を持たない、という指摘はすでに成されているところである(土田健次郎『江戸の朱子学』)。「正統」に倫理的意味を持たせて「正統」でない王朝を指弾する歴史論は、後世の朱子学から始まった。だが朱子じしんの立場では、陳亮との論争にあったように、周の没落以降の中国の政権にはいずれも完全な道徳的正義を見出すことができない、ということなのであろう。疑問なのは、ならば朱子自身が生きていた宋王朝はどうなのであろうか。宋の太祖は明らかに後周柴氏の臣であったにもかかわらず、自ら即位して主家を終わらせた。その政権移行は平和的であったと記録されているにしても、これは簒奪というべきなのではないか。朱子は、その後裔の宋王朝をどのように倫理的に位置づけようとしたのであろうか。正義を以て手続きすれば、宋の太祖のように現王朝を簒奪することはやむをえないと考えるか。それとも現王朝の下で禄を食む臣は、少なくとも現王朝を支え続けてこれに殉ずるべきと考えるか。朱子の現政権への姿勢もまた、興味をもって知りたいところである。
宋代思想を日本で学ぶことの難しさ 常識化した『孟子』
道学の成立には『孟子』の受容が大きく関わっている(342ページ)
本書が取り扱う宋代儒学思想史の背後に流れる、通奏低音が『孟子』の受容史である。
『孟子』が諸子の一書から飛躍して、論語と並ぶ聖典の地位を得たのは宋代であった。宋代の儒者たちはそれぞれの思想的立場を正当化するために、それぞれ『孟子』から養分を吸収した。王安石は、道学者たちからは敵とみなされる。その王安石その人が、北宋代に孟子を諸子から引き上げ聖人として尊ぶことを始めた。王安石は『孟子』の「召さざる所の臣」(公孫丑章句下)という言葉を神宗皇帝との君臣関係の理想に置いたのであった。こうして「孟子から論語の意味を読み解く」読書は、宋代にその始原を持つ。
だがこの「孟子から論語の意味を読み解く」読書は、わが伊藤仁斎と同じではないか。仁斎は朱子学を批判して古学を提唱し、朱子学の解釈によって歪められる以前の孔子・孟子の真意を遡って読み解こうとした。ところが仁斎が『孟子』を尊重して、この書を「論語の津筏(しんばつ)」と称えたその読書、それ自体が宋代の産物ではないか。もし『論語』が唐代以前の読み方、人間には上中下の三等級があるという人間不平等説を引き継いでいたならば、わが国が江戸時代以降に広く『論語』を受容することなどあったであろうか。『孟子』の中に流れる強い万人平等指向を通り抜けてこそ、次第に近代に近づいていったわが国の読者に訴えかけることができたのであろう。そして「孟子から論語の意味を読み解く」読書は宋代に始まったことであり、わが国の儒学は宋代以降の読書を前提としているのである。仁斎は古代の読書を復活させたのではなく、南宋孝宗時代に戻って朱子とは異なる道学の一分派を立てた、と評してよいのではないだろうか。
こうしてわが国では『孟子』を通り抜けた『論語』読書が常識となっていて、それが宋代儒学の創始であることをもはや意識しない。宋代儒学の仕事はわが国の読書では電気か水道のようになってしまっているため、わが国ではその見えやすいあら捜しはするが、その知的インフラを作った功績まで意識が届きにくいのである。
宋代思想を日本で学ぶことの難しさ 聖典解釈の違いが政争となる異文化
中国王朝の政治史(李氏朝鮮も同様)で、日本人に最も分かりづらいところは、政治思想の違いが四書五経の解釈の違いとなって表明され、その解釈の違いによって朋党が形成されて、弾圧反撃の政治劇が行われるところである。日本人から見れば政治とは統治の技術であって、争いは思想というよりもどうすれば民生・国防をよく達成できるかの効果を競うところにある。聖典の解釈を巡って徒党が組まれて政治闘争が行われる、ということは、わが国ではマルクスレーニン主義を信奉する左派の間だけで行われてきたことであって、そして左派の政治闘争は日本人の常識に寄り沿っているとは到底言い難いものがある。
日本人にとって四書五経は、あくまで個人のための倫理書である。しかし中国王朝(李氏朝鮮も)にとって四書五経は、政治経済倫理すべての規範をここから導き出さなければならない、文字通りの聖典であった。その解釈の違いが政治思想の違いとなり、時事問題への対処法の違いともなった。それで弾圧反撃の政治劇となったのであるが、日本人から見ればたかが書物の解釈の違いで争ってあげくは敗者を流刑に処したりするなど、「頭のええ人たちほどアホなことする」のたぐいで、まず尊敬されることはない。ところが、中国王朝(李氏朝鮮も)では、これが政治生命を賭けた戦いとなるのだ。ここに、思想の違い・聖典解釈の違いで政争を続けてきた文化と、そのような歴史を持たない文化の溝があるように思える。中国王朝(李氏朝鮮も)の政治史の争いが、日本人にはどうにも理解し難いのである。
朱子学の勝利は歴史の必然だったのか?
「道学」と言えば朱子学のことを指すようになったのは、元明代に朱子学が勝利した結果のことであった。しかし南宋代に四派あった「道学」の中から朱子の閩学が勝利したことは、歴史の必然であったのだろうか。本書で触れられている胡宏の思想や、あるいは陳亮の思想は、朱子からすれば異端でしかないがその論は道徳論・統治論としてそれほどグロテスクなものとは思えない。胡宏の道徳論は、先秦時代の孟子・荀子が取っていたはずの立場にむしろ近いと考えられる。朱子の道徳論、天理と人欲を相対立するものとして後者を厳しく斥ける考えは、四書の『中庸』の極端な解釈に由来するようで、むしろ禅仏教的と言えないだろうか。歴史のIFとなってしまうが、もし張栻や陳亮といった研究者がもう少し長命であって、朱子の一派に倣いかつ対抗するために浩瀚かつ綿密な四書五経の逐条注釈を遺す作業を終えていたならば、あるいは元明代に朱子集注とは別の集注として採用されて、春秋三伝のような併論とされることもあったかもしれない。
歴史は、朱子集注だけが科挙の科目として国家に採用され、それが科挙の制度と見事に一致したために国学として固定されることとなった。だがそれは朱子が後世の科挙の制度にたまたま合致する逐条注釈を遺したからであって、思想の優位性とは違った要因が寄与したところが大きかったのではないだろうか。もし胡宏や陳亮の思想に沿った別の集注があったとしても、おそらく国家の統治政策の妨げとなるものではなかったことであろう。