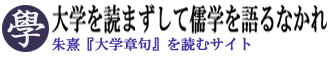『中庸或問』跋・第一章後段三~中は性か否か、未発已発の論~
|
出典:国立国会図書館デジタルコレクション『四書集注大全』(明胡廣等奉敕撰、鵜飼信之點、附江村宗□撰、秋田屋平左衞門刊、萬治二年)より作成。 〇各ページの副題は、内容に応じてサイト作成者が追加した。 〇読み下しの句読点は、各問答の中途は読点、末尾は句点で統一した。 〇送り仮名は、原文から現代日本語に合わせて一部を変更し、かつ新かなづかいに変えた。 |
|
《読み下し》 曰、子思の中和を言うこと此の如し、而して周子の言に則ち曰く、中は和なり、節に中(あた)るなり、天下の達道なり(注1)、乃ち中を擧げて之を和に合す、然らば則ち又將に何を以てか天下の大本と爲さんや。 曰、子思の所謂中は、未だ發せざるを以て言う、周子の所謂中は、時に中(ちゅう)するを以て言う、愚篇首に於て之を辨す、學者涵泳(かんえい)(注2)して之を別識せば、其の竝び行われて相悖らざるを見て可なり。 曰、程呂問答如何。 曰、之を文集に考うるに、則ち是れ其の書蓋し完からず、然れども程子初め謂えらく凡そ心を言う者は、皆已發を指して言う、而るに後書に乃ち自ら以爲(おもえ)らく未だ當らずと、向(さき)に呂氏之を問うことの審かなるに非ずして、完からざるの中に又此の書を失わば、則ち此の言の未だ當らざること學者何に自(よ)りて之を知らんや、此を以て又知んぬ聖賢の言、固(まこと)に端を發して未だ竟(お)えざる者有ることを、學者尤も當に心を虛し意を悉くして以て其の歸を審かにすべし、未だ其の一言を執りて遽(にわか)に以て定と爲す可からず(注3)、其の中の字を説くことは、過不及に因りて名を立つ、又倂せて時中の中を指すに似たり、而して中に在るの義と少しき異なり、蓋し未發の時は、中に在るの義、之を偏倚する所無しと謂わば則ち可なり、之を過不及無しと謂わば、則ち此の時に方(くら)べて未だ節に中り節に中らざるの言う可きこと有らず、過不及の名無くんば、亦何に自(よ)りて立たんや、又其の下の文、皆不偏不倚を以て言うことを爲すときは、則ち此の語は、又或は未だ定論と爲すことを得ず(注4)、呂氏又允(まこと)に厥(そ)の中を執れ(注5)ということを引きて以て未發の旨を明す、則ち程子の書を説くや、固に謂わく允に厥の中を執るは之を行う所以、蓋し其の所謂中は、乃ち時中の中を指す、未發の中に非ず、呂氏又之を喜怒哀樂未發の時に求む(注6)、則ち程子蘇季明の問に答うる所以、又已に旣に思うこと有らば、即ち是れ已發の説なり(注7)、凡そ此れ皆其の決して呂が説を以て然りと爲せざる者なり、獨り知らず其れ此に於て何か故にか略して辨ずる所無きことを、學者亦當に之詳かにすべし、未だ其の辨ぜざるを見て遽に以て是と爲すべからず。 曰、然らば則ち程子卒(つい)に赤子の心を以て已發と爲することは何ぞや(注8)。 曰、衆人の心未發の時有らずということ莫し、亦已發の時有らずということ莫し、老稚賢愚を以て別つこと有らず、但だ孟子の指す赤子の心は、純一にして僞り無しという者は、乃ち其の發に因りて而して後に見つ可し、若し未だ發せずんば則ち純一にして僞り無き、又以て之名づくるに足らじ、而して亦獨り赤子の心のみ然りと爲るに非ず、是を以て程子夫の心皆已發の一言を改むると雖も、而も赤子の心を以て已發と爲ることは、則ち得て改む可からず。 (注1)四書大全の注に、「周子通書の中の語」。周子は周敦頤。
(注2)涵泳は、ひたっておよぐ様。 (注3)四書大全に引く、「藍田呂氏問うて曰く、先生謂えらく凡そ心を言う者は、皆已發を指して言うと。然らば則ち未發の前之を無心と謂いて可ならんや。竊(ひそか)に謂わく未發の前は、心體昭昭として具在す、已發は乃ち心の用なり。」「程子曰く、凡そ心を言う者は、已發を指して言う。此れ固に未だ當らず。心は一なり。體を指して言う者有り、寂然として動かざる是なり。用を指して言う者有り、感じて遂に天下の故に通ずる是なり。惟だ其の見る所何如と觀るのみ。」 (注4)四書大全に引く、「藍田呂氏曰く、中は即ち性なり。」「程子曰く、中は、性の體段を狀(かたど)る所以、猶お天圓(えん)に地方なるを稱して方圓即ち天地と謂う可からざるごとし。中の義爲る、過不及無き自りして名を立つ。而るに中を指して性爲る可ならんや。」これに対する朱子の問答、「問う、渾然として中に在る、恐らくは是れ喜怒未だ發せざれば此の心虛に至りて、都(すべ)て偏倚無く停停當當として恰(あた)か其の中間に在り。所謂獨立して四旁に近からずんば、心の體地の中なり。」「朱子曰く、中に在る者は、未だ動かざる時恰好の處。時に中する者は、已に動く時恰好の處。未発の時、喜に偏らざれば、則ち怒に偏る。之を中に在りと謂うことを得ず。然れども只要に偏倚する所の一事に就きて之を處して恰好を得れば、則ち過不及無し。蓋し過不及無きは、乃ち偏倚無き者の爲る所にして、而して偏倚無き者は、是れ能く過不及無き所以なり。」「如し喜びて、節に中らば、便ち是れ喜に倚る。但だ喜の中に在りて過不及無し。怒哀樂も亦然り。故に之を和と謂う。」「問う、程子の曰く、中は性の體段を狀る所以、猶お天の圓(えん)に、地の方なるがごとし。故に天圓地方と謂うは則ち可なり、方圓以て天地を盡すに足りと謂うは、則ち不可なり。」「晦翁の謂わく、喜怒哀樂未だ發せざるは、則ち性なり。愚意亦謂わく、性と中と一物のみ。天の命ずる所自りは則ち之を性と謂う。四の者の未だ發せざる自りは則ち之を中と謂う。若し程子の論ずる所の如きは、豈に性は是れ虛物、中は是れ著實些箇と謂うにや。其の不同或は此に在り。」 (注5)偽古文尚書、大禹謨篇に「允に厥の中を執れ」。同じ句が論語堯曰篇に見える。朱子は「允に厥の中を執れ」を含む大禹謨篇の言を中庸章句序に引用してそこに中庸の思想による解釈を与え、中庸の思想が道統の伝であって堯舜から後世に伝えられた文献的根拠として用いる。しかし大禹謨篇じたいが偽篇であって、朱子や先行する宋代学者たちの議論の根拠はすでに失われている。 (注6)四書大全に引く、「藍田呂氏曰く、大人其の赤子の心を失わず、乃ち所謂允に厥の中を執るという者なり。又曰く、聖人の學、中を以て大本と爲す。中は過不及無しの謂なり。何を準則する所あって過不及を知らんや。之を此の心に求むるのみ。此の心の動、出入時無し。何に從いて之を守らんや。之を喜怒哀樂未發の時に求むるのみ。」 (注7)四書大全に引く問答、「蘇氏喜怒哀樂の前に於て中を求むる可否を問う。程子曰く、不可なり。旣に喜怒哀樂未發の前に於て之を求むることを思う、又却て是れ思なり。旣に思わば即ち是れ已發、思と喜怒哀樂と一般、纔(わずか)に發する之を和と謂う、之を中と謂う可からず。問う、呂氏當に喜怒哀樂未發の前に求むべしと言う。斯の言を信ずるときは、恐らくは著落無し。如之何(これをいかん)して可ならん。曰く、喜怒哀樂未發の時に存養するを言うは、則ち可なり。若し中を喜怒哀樂未發の前に求むと言わば、則不可なり。」蘇氏は蘇季明、程子の門人。これに対する朱子の言、「朱子曰く、程子纔に思わば即ち是れ已に發すという一句、能く子思言外の意を發明す。蓋し言は喜怒哀樂の發を待らず。但だ思う所有らば即ち是れ已發、此の意已に極めて精微、説を未發の界に到り、十分盡頭に至りて、以て加うること有る可らず。」 (注8)四書大全に引く、「程子曰く、喜怒哀樂未だ發せざる之を中と謂う。赤子の心、發して未だ中に遠からず。若し便ち之を中と謂わば、是れ大本を失わず。」これに対する朱子の言、「朱子曰く、赤子の心は動靜常無し。寂然不動の謂に非ず。故に之を中と謂う可からず。然も榮欲知巧の思無し。故に未だ中に遠からずと謂う。未發の中は、本體自然にして、窮索を須(もち)いず。」 |
《要約》
|